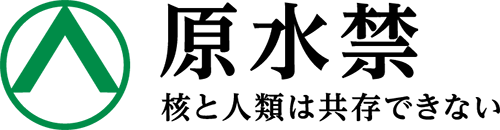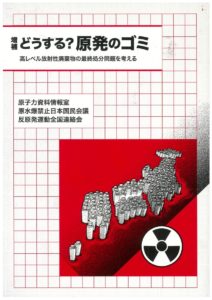原水禁 - 原水禁 - Page 5
2020年10月06日
「9.6老朽原発うごかすな!大集会in大阪」に1600人が参加
熱中症の心配も残る暑さの中、「9.6老朽原発うごかすな!大集会in大阪」集会が大阪市内のうつぼ公園で開催され、全国各地から多くの参加者が集まりました。
集会参加者は1600人。

- 主催挨拶 中嶌哲演氏(福井県小浜市 明通寺住職)
- スピーチ 木原壯林氏/末田一秀氏(関電の原発マネー不正還流を告発する会)/草地妙子氏(老朽原発40年廃炉訴訟市民の会、名古屋市)/井戸謙一氏(福井原発訴訟〈滋賀〉弁護団長、元裁判官)/東山幸弘氏(録音メッセージ、高浜町)/松下照幸氏(文書メッセージ、美浜町議会議員)/披田信一郎氏(東海第2原発の再稼働を止める会)
- プラカードアピール/実行委から/若狭の声紹介/原発賠償関西訴訟原告団から/全国の団体紹介/団体アピール/労働組合ほかから/集会決議提案・採択

集会後、大阪市内のうつぼ公園から御堂筋を歩く長距離のパレードを行い、沿道の人々に脱原発の必要性を訴えました。

各地の連帯する動きなどは、こちらのブログをご覧ください。
「老朽原発うごかすな!大集会 in おおさか」実行委員会Blog
集会の様子がわかる動画はこちら(IWJ)
2020年10月06日
「9.18さようなら原発首都圏集会」に1300人が参加

「9.18さようなら原発首都圏集会」が9月18日に、日比谷野外音楽堂にて開催されました。3月に予定されていた全国集会が中止となり、さようなら原発1000万人アクションとしての屋外での集会は1年ぶりとなりました。
当日は、手指の消毒ののち、参加者各自でプログラムをとり、サーモグラフィー通過など、新型コロナウィルス感染症対策を講じました。

発言者と発言要旨は以下の通りです。
◆「オープニングライブ」西川郷子さん(もと上々颱風)と「星ノ飛ブ夜」のみなさん
◆「安倍政権はいかに無責任だったか。でもそれは終わっていない。責任をとらせなくてはいけない」落合恵子さん(さようなら原発1000万人アクション呼びかけ人)
◆「安倍政権に続く菅政権について」佐高信さん(ジャーナリスト)
◆「安倍政権はオリンピックで避難者を追いつめてきた」村田弘さん(福島原発かながわ訴訟原告団長)
◆「核燃料サイクルの危険性について」山田清彦さん(青森県反核実行委員会)
◆「日本の核廃棄物はほとんどヨーロッパで処理されている。その工場建設、輸送費用など、日本の消費者が払っている。」澤井正子さん(元原子力資料情報室)
◆「このコロナ禍でも日本原電は再稼働のための工事を続けている。しかしコロナを理由に住民説明会を行っていない。再稼働をしないのが一番安全だ!」設楽衛さん(茨城平和擁護県民会議事務局長)
◆「石炭火力発電をまだベースロード電源に据えている日本に、世界から批判が集まっています。」桃井貴子さん(気候ネットワーク東京事務局長)
◆「菅政権は、安倍政権は、同じ穴のムジナ内閣。原発政策は終わっているのです。早くやめるのが未来の子供たちのため。最終処分場も、再処理工場もできていない。もう終わったものにしがみついているのです」閉会の挨拶・鎌田慧さん(さようなら原発1000万人アクション呼びかけ人)

集会参加者は1300人、サイレントデモを基本に日比谷公園から東電前を通り、銀座を抜けデモを行いました。
会場の使用には人数制限もあり、これまで全国から集まっていた参加者に対しては、さようなら原発実行委員会のTwitterアカウントを使用したツイキャスで集会の様子を生配信する試みも行いました。
ツイキャス配信動画はこちら:https://twitcasting.tv/sayonara_n2011/movie/641272357
2020年10月05日
平和フォーラム・原水禁 SNS開設について
これまで、機関紙「ニュースペーパー」の発行、ホームページの更新、メルマガの発行などを通し、情報の発信と集中、共有化を行ってきました。
この度、インターネットの活用を強化すべく、下記の通り、平和フォーラム・原水禁でSNS(Facebook、Twitter)を開設いたしました。アカウント開設の情報共有・拡散をお願いするとともに、開設したSNSのフォローをお願い致します。
記
1.Facebook アカウントの開設
フォーラム平和・人権・環境(平和フォーラム)@peace.forum.jp
https://www.facebook.com/peace.forum.jp/
原水爆禁止日本国民会議 (原水禁)@gensuikin.jp
https://www.facebook.com/gensuikin.jp/

Twitterアカウントの開設
平和フォーラム・原水禁共通 @forum_gensuikin
https://twitter.com/forum_gensuikin
2.Facebook、Twitterでは、ホームページの更新内容が連動して表示されます。
更新したホームページは、表示されるURLからご覧いただけます。
3.Facebook、Twitterともに、コメントを書き込むことができます。また、更新した記事に対し、リツイート(Twitter)やシェア(Facebook)をしていただくことで、情報の共有が可能となります。
※この作業は、ログインが必要となります。
2020年10月05日
「トリチウム汚染水の海洋放出」に関する政府交渉

10月5日、原水禁を含む8団体は、「トリチウム汚染水の海洋放出」に関する政府交渉を参議院会館B107会議室で行い、地元の福島県在住者を中心に25名が参加しました。
冒頭、福島県平和フォーラムの角田政志共同代表から、「福島県民は『トリチウム汚染水の海洋放出』は、望んでいない。『海洋放出』以外の方法による早期解決を望む人々が多くいることを理解してもらいたい。」との、福島県民を代表した表明がありました。

今回は、前回・7月3日に行われた同交渉における残された課題・再質問等を、政府(経済産業省・外務省・原子力委員会・原子力規制庁)と行いました。政府側からは、「原発事故で多くの方にご迷惑をかけ、大変申し訳ない」との言葉はあったものの、「『トリチウム汚染水の海洋放出』は、ロンドン条約に規定する『海洋投棄』にはあたらないと考える。」「感情的な議論と科学的議論は違う。」等、これまで同様、福島県民・住民の立場に寄り添っているとは思えない発言・回答が多くあり、やりとりは平行線のまま終了しました。

政府交渉の時程は以下の通りです。
13:00~14:15 経済産業省
14:20~14:50 外務省
14:55~15:25 原子力委員会
15:30~16:00 原子力規制庁
主催8団体:
脱原発福島県民会議
双葉地方原発反対同盟
原水爆禁止日本国民会議
原子力資料情報室
全国被爆2世連絡協議会
原発はごめんだ!ヒロシマ市民の会
チェルノブイリ・ヒバクシャ救援関西
ヒバク反対キャンペーン
2020年10月05日
岩松繁俊元原水禁議長の訃報について
すでに新聞報道等でご存知の通り、原水爆禁止日本国民会議(原水禁)の議長を1997年から2007年の10年間に渡って務めいただいた長崎大学名誉教授の岩松繁俊さんが、9月23日午前8時20分、急性心不全のため、長崎市内の病院でお亡くなりになられました。92歳でした。
岩松さんは、学徒動員で三菱重工業長崎兵器製作所大橋工場での作業中に被爆しました。その後原水爆禁止運動に参加し、以後、核兵器の廃絶を訴え長年に渡り運動をけん引してきました。特に岩松さんは、被爆国日本が核兵器廃絶を訴える上でも、戦争での日本の加害責任に対する自己批判を必要とする「加害と被害の二重構造」論を主張しました。そのことを「反核と戦争責任」(三一書房)、「戦争責任と核廃絶」(三一書房)などの著書にまとめられました。またイギリスの哲学者であり平和運動家でもあったバートランド・ラッセルと1960年代から70年2月の病没まで交流を続け、親交を深めました。日本ではバートランド・ラッセル平和財団日本資料センターを立ち上げるなど、ラッセルの考えを広めました。
長年に渡る原水禁運動に対する功績を偲び、ここにお知らせいたします。
なお、葬儀につきましてはすでに近親者のみで執り行われました。原水禁として供花とおくやみの電報をお送りしました。経歴については以下をご覧ください。
岩松繁俊元原水禁議長の経歴はこちら(PDF)
以上
2020年10月05日
「福島原発集団訴訟仙台高裁判決に際しての見解」の発出について
9月30日、仙台高裁において、福島県民および隣接する3県の住民が集団で起こした、国および東電に対する損害賠償訴訟の判決がありました。高裁判決として、初めて国の責任を明確に判定した判決として、画期的であり、また当然ともいえるものです。本判決は、今後の原発裁判に大きな影響を与えるこのとして、重要であると考え別紙の通り事務局長見解を発出しましたので、ここに掲載いたします。
今後とも、原水禁は、被災者の側にたって、「一人ひとりの命に寄り添う政治と社会」を求めてとりくんでいきます。
2020年10月5日
福島原発集団訴訟仙台高裁判決に際しての見解
原水爆禁止日本国民会議
事務局長 北村智之
東京電力福島第一原発事故によって被災した福島県と隣接する3件の住民約3600人が、国および東京電力に対して損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が、9月30日に仙台高裁(上田哲裁判長)で言い渡された。判決は、国と東電の責任を同等と認め、原告3550人に対して総計で約10億1000万円の賠償を命じるもので、一審の約2900人、総計5億円を大きく上回り、より救済範囲を広げたものとなっている。国と東電は、判決の意味するところをしっかりと受け止めて、上告をせずにその責任を果たすべきである。
判決は、政府の地震調査研究推進本部が2002年に出した、福島県沖においても巨大な津波地震が起きうるとした「長期評価」を「客観的かつ合理的根拠を有する科学的知見であったことは動かしがたい」として、国と東電双方に津波の予見可能性を認め、国に対しては「不誠実な東電の報告を唯々諾々と受け入れ、規制当局に期待される役割を果たさなかった」と、その姿勢をきびしく弾劾している。国策として原発を推進してきた国の責任は免れはしない。国と東電双方の責任を認めた判決内容は、画期的であるとともに当然とも言える。
東電の責任は、すでに地裁判決の出た16件全てで認められてきた。しかし、国の責任を問う訴訟の判決は、地裁段階で14件を数えるが、うち6件で国の責任が認められず判断は分かれてきた。責任の有無の判断は、2002年の「長期評価」による津波の予見可能性をどのように捉えるかによって変わる。東電旧経営陣が業務上過失致死傷害罪で強制起訴された刑事裁判の東京地裁判決も、「長期評価は根拠が具体的ではなく、専門家の意見も分かれ、信頼性に限界があった」として、津波の予見可能性を認めなかった。今回の仙台高裁判決は、その意味で今後他の多くの原発訴訟に影響を与えることは必至であり、原水禁は、本判決をきわめて妥当なものとして受け止め、今後の判決に活かされることを求める。
判決は、2002年以降の国と電力会社とのやりとりを詳細に検討し、国と東電は対策の必要性を認識しながら東電の経済負担を恐れ、試算を避けその結果を隠ぺいしてきたものと判定している。これまでの原子力行政のあり方、原発運転のあり方に、猛省を促したい。また一方で判決は、賠償額・賠償の対象地域を拡大した。国は自らの過失を認めず、よって国が示してきた賠償額は低額に留まってきた。東電は、その水準を超える裁判外紛争解決手続(原発ADR)での和解案には応じてこなかった。国の言う安全を信じて、国策に協力してきた被害住民が、なぜ裁判に訴えなくては救済されないのか。国は被害住民の声を真摯に受け止め、本判決を境に、被害住民の損害賠償、生活再建にきちんとした結論を出すべきだ。
原水禁は、福島第一原発事故から10年を経過する中で、国と東電に対し、被災者への確実な保障と将来にわたる健康不安への真摯な対応を求める。そして、国民の総意として、原発の再稼働を止め、自然エネルギーを中心にした原発ゼロ社会の実現を求める。そのために「さようなら原発1000万人アクション」に結集する市民とともに、今後も懸命にとりくんでいく。
2020年10月01日
10/15 オンラインセミナー「衝撃の容量市場結果ー再エネ新電力は生き残れるか」

原水禁も参加する「eシフト」によるオンラインセミナーのご案内です。
気候危機のいま、再エネと省エネによるエネルギー転換(エネルギーシフト)が急務です。
ところが、過大な電力需要見積もりのもと、原発や石炭火力が温存される容量市場が、2020年度スタートしました。
容量市場では4年後(2024年度)の供給力(kW)が取引されます。
2020年7月に容量市場オークションが実施され、9月14日に結果が公表されました。
https://www.occto.or.jp/market-board/market/oshirase/2020/20200914_youryouyakujokekka_kouhyou.html
<2020年度メインオークション(対象実需給年度:2024年度)の結果>
・約定量 1億6,769万kW
・約定価格 14,137円/kW
・経過措置を踏まえた約定総額は1兆5,987億円
結果はほぼ上限価格と、電力業界や経済産業省さえも想定しなかった結果となりました。
新電力、とくに再エネ新電力への影響は大きく、経営の危機も懸念されます。
<問題点>
・古い原発や石炭火力が温存される
・再エネ新電力に大きな負担
・大手と新電力の格差拡大
eシフトでは、9月16日に経済産業大臣への要請を提出しました。http://e-shift.org/?p=3908
本セミナーでは、様々な視点から容量市場の問題点と今回の約定結果の影響を考えます。
◆ 10/15 オンラインセミナー「衝撃の容量市場結果ー再エネ新電力は生き残れるか」
日時: 2020年10月15日(木)13:30~15:30
場所: オンライン(zoomウェビナー)
主催:eシフト
共催:原子力市民委員会
■プログラム:
1.容量市場の概要、海外での状況と再エネへの影響
飯田哲也(環境エネルギー政策研究所 所長)
2.2020年度約定結果の分析
松久保肇(原子力資料情報室 事務局長)
3.再エネ新電力の負担と消費者への転嫁
竹村英明(グリーンピープルズパワー 代表取締役社長)
4.気候の安定化と石炭火力2030年全廃
桃井貴子(気候ネットワーク 東京事務所長)
5.常に過大となる電力需要想定
明日香壽川(東北大学東北アジア研究センター/環境科学研究科教授)
6.eシフトでの活動
吉田明子(国際環境NGO FoE Japan)
7.ゲストからのコメント(調整中)、質疑応答
■申込: 下記よりご登録ください。(セミナー直前まで登録できます)
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ghr-2i8YSI2Fb_KSZNSHhw
※オンライン会議システムのzoomを使います。
※マイク・スピーカー機能のついたPCもしくはスマホ、タブレットが必要です。
2020年09月25日
『増補 どうする?原発のゴミ 高レベル廃棄物の最終処分問題を考える』パンフレットのご紹介
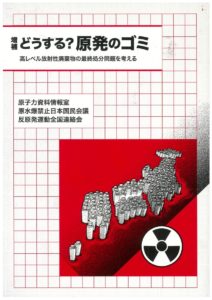
2017年8月20日発行
体裁:A5版40ページ+増補・科学的特性マップ8ページ
発行:原水爆禁止日本国民会議、原子力資料情報室、反原発運動全国連絡会
価格:300円(送料別)
寿都町の核のごみの最終処分地選定に向けた動きは、北海道への核のごみを持ち込むことを禁じた道条例(核抜き条例)を無視し、条例を死文化させるものであり、住民間の分断を招きかねないものです。さらに、今後、財政状況の厳しい自治体へ同様の動きが広がることが危惧されます。
高レベル廃棄物の最終処分問題をどのように考えるべきか、2017年に原水禁、原子力資料情報室、反原発運動全国連絡会が共著のパンフレット『増補 どうする?原発のゴミ 高レベル廃棄物の最終処分問題を考える』を、今、改めてご紹介させていただきます。
『増補 どうする?原発のゴミ 高レベル放射性廃棄物の最終処分問題を考える』もくじ
口 絵 高レベル放射性廃棄物処分場「適地マップ」 ………………1
第1章 高レベル処分場の危険性 ………………………………………2
第2章 どのように処分地を選ぼうとしているか ……………………18
第3章 誘致の動きを封じ、脱原発へ …………………………………25
第4章 地下研究施設の教訓
北海道幌延町 幌延深地層研究所 核廃棄物施設誘致に反対する道北連絡協議会共同代表 久世薫嗣 ………………30
岐阜県瑞浪市 瑞浪超深地層研究所 放射能のゴミはいらない!市民ネット・岐阜代表 兼松秀代 …………………34
表紙イラスト・高木 章次
13ページ写真・島田 恵
——————————————————————————–
ご注文を受け付けています(送料別)
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3-2-11 連合会館1F
TEL:03-5289-8224 FAX:03-5289-8223
申し込みはお名前、送り先、冊数明記の上、メール、またはFAXでお願いいたします。
メール:office▲peace-forum.top(▲を@に変えてください)
FAX:03-5289-8223
現在、新しいパンフレット作成の準備を進めています。
高レベル廃棄物最終処分について、これまでとは違った観点でまとめていきます。(11月発行予定)
2020年09月16日
eシフト、経済産業大臣に「容量市場の見直しに関する要請」を提出しました

9月14日、容量市場の初回メインオークションの約定結果が公表されました。
これを受け、原水禁も参加する「eシフト(脱原発・新しいエネルギー政策を実現する会)」は、9月16日、経済産業大臣に対し「容量市場の見直しに関する要請」を提出しました。
下記をご参照ください。
http://e-shift.org/?p=3908
容量市場の見直しに関する要請
気候危機のいま、再エネと省エネによるエネルギー転換(エネルギーシフト)が急務です。ところが、過大な電力需要見積もりのもと、私たちが支払う電力料金値上げによって原発と石炭火力が温存される電力市場が新たにつくられ、2020年度本格的に開始されます。
2020年7月に容量市場オークションが実施され、9月14日に結果が公表されました。
https://www.occto.or.jp/market-board/market/oshirase/2020/20200914_youryouyakujokekka_kouhyou.html
<2020年度メインオークション(対象実需給年度:2024年度)の結果>
・約定量 1億6,769万kW
・約定価格 14,137円/kW
・経過措置を踏まえた約定総額は1兆5,987億円
結果として、ほぼ上限価格で約定することとなりました。
2019年度の販売電力量8,361億kWhで割るとkWhあたり2円に近い金額とも言うことができ、消費者や新電力(特に再エネ新電力)にとって大きな負担です。
私たち環境団体は、大手電力の寡占化がますます進み、原発依存度の低下や再生可能エネルギー(再エネ)・省エネの導入が遅れ、電力自由化が逆戻りしてしまうことを強く懸念しています。
消費者の電力選択の権利、また将来にわたり安全で安心できる環境・くらしを守る観点から、再エネ新電力や再エネの普及に圧倒的に不利となり、省エネを考慮しない容量市場を見直すよう、要請します。
<要請の理由>
1.原発・石炭火力発電が温存され、エネルギーシフトを妨げる
容量市場は発電できる能力に価格を付ける市場です。新しい発電所も古い発電所もkWあたりでは同じ落札金額がもらえ、また、常に一定量を発電し続ける電源(例えば原発や石炭火力など)がより多くkWの価値を認められます。そのため、こうした電源が温存されることにつながります。また、これにより再エネや蓄電池などへの投資が控えられてしまうことが考えられます。
このため、エネルギーシフトはますます遅れ、持続可能な再エネを利用して暮らしたいという消費者の権利は損なわれます。原発の温存は安心して暮らせる市民の権利を奪い、石炭火力の温存は気候危機をさらに加速させ将来世代の生存する権利も奪うものです。
2.消費者にとって二重払いとなる
容量市場で回収することが想定されているのは初期投資などの固定費ですが、日本の大半の発電所の初期投資費用などは、電気代に算入されており消費者はすでに支払っています。また、2010年度以前に建設された電源に対する支払額(容量拠出契約金額)は、経過措置として2029年まで一定程度割り引かれることになっているものの、それ以降は満額の支払いとなります。消費者にとっては、すでに払っているのに再度徴収されることになります。また、容量市場によって、原発や石炭を温存するために電力料金が上がり、消費者の負担が不要に増えることも極めて問題です。
3.消費者の再エネ・省エネ選択・電力自由化も危機
大手電力の小売会社(みなし小売)は、古い大規模な発電所との直接契約を多く持っています。容量拠出金を支払いますが、その分の値引きも受け、実質負担は大幅に減ります。大手電力の発電会社側での収入もあります。一方、大規模電源を持たない再エネ新電力は容量拠出金で経営が圧迫され、格差がさらに拡大します。
再エネ新電力の消費者には特に不利な制度で、電力料金の一部が、大手電力の古い原発や石炭火力の維持費に流れてゆくことになります。再エネの導入が遅れ、再エネ新電力の経営も危機となれば、消費者の再エネ選択は大きく妨げられます。省エネの普及も阻害されます。
大手電力の寡占化が進み、消費者の選択や再エネ・省エネの導入拡大を意図した電力自由化も形骸化してしまいます。
4.消費者の知る権利を損ねる
容量市場は、市場規模が約1.6兆円にも上る巨大な官製市場です。そして、ここで徴収された費用は、事実上の補助金として、落札電源に配分されることになります。しかし、現状では、だれが保有するどの電源が入札し、落札したのかの詳細は公表されていません。電気に含まれる容量市場分のコストが示されるのかも分かりません。このような説明責任に欠ける制度設計は、原発や石炭火力に対する実質的な補助金制度を国民に気づかれないように導入しようとする意図の現れとしか考えられません。
・リーフレット「STOP!原発・石炭火力を温存する新たな電力市場」
http://e-shift.org/?p=3827
・消費者庁に容量市場の見直しを求める要請を提出
http://e-shift.org/?p=3881
・6/18 オンラインセミナー「原発・石炭火力を温存する新たな電力市場の問題点」
http://e-shift.org/?p=3815
<eシフト参加団体>
国際環境NGO FoE Japan 環境エネルギー政策研究所(ISEP) 原子力資料情報室(CNIC) 気候ネットワーク 市民電力連絡会 原子力市民委員会 原水爆禁止日本国民会議(原水禁) 福島老朽原発を考える会(フクロウの会) 大地を守る会 NPO法人日本針路研究所 日本環境法律家連盟(JELF) 「環境・持続社会」研究センター(JACSES) インドネシア民主化支援ネットワーク 環境市民 特定非営利活動法人APLA 原発廃炉で未来をひらこう会 高木仁三郎市民科学基金 水源開発問題全国連絡会(水源連) グリーン・アクション 自然エネルギー推進市民フォーラム 市民科学研究室 グリーンピース・ジャパン ノーニュークス・アジアフォーラム・ジャパン フリーター全般労働組合 ピープルズプラン研究所 ふぇみん婦人民主クラブ No Nukes More Hearts A SEED JAPAN ナマケモノ倶楽部 ピースボート WWFジャパン(公益財団法人 世界自然保護基金ジャパン) GAIAみみをすます書店 東京・生活者ネットワーク エコロ・ジャパン・インターナショナル メコン・ウォッチ R水素ネットワーク 東京平和映画祭 環境文明21 地球環境と大気汚染を考える全国市民会議(CASA) ワーカーズコープ エコテック 日本ソーラーエネルギー教育協会 THE ATOMIC CAFE 持続可能な地域交通を考える会 (SLTc) 環境まちづくりNPOエコメッセ 福島原発事故緊急会議 川崎フューチャー・ネットワーク 地球の子ども新聞 東アジア環境情報発伝所 Shut泊 足元から地球温暖化を考える市民ネットえどがわ 足元から地球温暖化を考える市民ネットたてばやし 東日本大震災被災者支援・千葉西部ネットワーク アジア太平洋資料センター(PARC) NNAA(No Nukes Asia Actions) Japan さよなら原発・神奈川 プルトニウムフリーコミニケーション神奈川 エコフェアネットワーク 350.org Japan 公害地球環境問題懇談会(JNEP) 大磯エネシフト 環境まちづくりNPO元気力発電所 地球救出アクション97
eシフト(脱原発・新しいエネルギー政策を実現する会)http://e-shift.org/
事務局(国際環境NGO FoE Japan) info@e-shift.org
容量市場申し入れ 関連ページ:http://gensuikin.peace-forum.com/2020/08/28/e-shift20200828yousei/
TOPに戻る