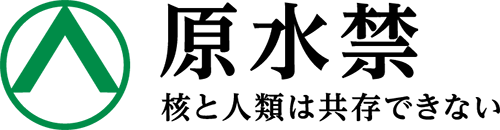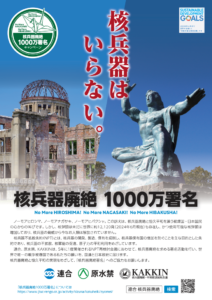4月, 2025 - 原水禁
2025年04月18日

4月16日、東京・連合会館において、「原水爆禁止日本国民会議第101回全国委員会」を開催し、2025年度の運動方針を討論・決定しました。その際、以下の全国委員会アピールを採択しましたので、ここに掲載します。
原水爆禁止日本国民会議 第101回全国委員会アピール
1945年の原爆被爆から今年で80年を迎えます。8月6日広島、8月9日長崎。原爆によって多くの命が一瞬にして奪われたばかりか、その後遺症や影響に苦しむ人がいまだ数多く存在する事実は、原爆は決して過去のものにはできないことを、私たちに突きつけています。
被爆直後からしばらくの間、被爆の実相はアメリカのプレスコードによって、報道することが禁じられ、検閲も行われました。被爆者に対する厳しい差別があり、被爆者は口を閉ざさざるを得ないという歴史的事実もありました。こういった現実に向き合いながら、原水禁運動はヒロシマ・ナガサキの被爆の実相を原点にし、1954年のビキニ環礁での被災を契機に高まった、原水爆禁止を願う市民の声を契機にその運動が始まり、今日まで継続されてきました。
国際社会では、ロシア・ウクライナ戦争の長期化、ガザ地区におけるイスラエルによる一方的な攻撃などによって、多くの命が奪われ続けています。加えて、核兵器使用リスクの高まりは危機的状況にあります。また、不安定さを増す国際情勢を理由に、「核抑止」が必要不可欠だと主張し核戦力を強化する国、そして日本のようにその「核の傘」のもとにある国があります。一方で、核兵器禁止条約を発効させてきた非核保有国は、核抑止論を乗り越えた先の核兵器廃絶をめざし、つながりを深めています。
そのような中で日本政府が果たすべき役割は、世界平和の実現、とりわけ核兵器廃絶に尽力することにあります。被爆者を二度と生み出さないための努力を、被爆国である日本が怠ることなどあってはなりません。核兵器禁止条約に対する態度を改め、日本の核兵器廃絶をめざす姿勢を国際社会に発信することで、そういった国々の先頭に立って行動すべきです。
原水禁はこれまでの運動の歴史において、「核の平和利用」を謳う原子力発電についても、すべての過程でヒバクシャが生み出される事実に目を向け、脱原発社会の実現をめざしてきました。日本政府は第7次エネルギー基本計画によって、再び原発の積極活用へと舵を切りました。福島第一原発事故から14年が経過した今でも、避難を強いられている県民は2万人を超えています。なぜ再び原発推進なのでしょう。30年以上たっても完成しない核燃料サイクルに依拠した原発推進政策は完全に破綻しています。誤りを認められない日本政府の政策によって、さらなる被害が生み出されることを決して看過することはできません。
原水禁はこれまで、すべての核に反対してきました。それは1955年の第1回原水禁世界大会で宣言されたように、「原水爆が禁止されてこそ、真に被害者を救済することができる」とした、被爆者との約束でもあります。核社会はいつも、犠牲を強いる側と強いられる側との差別的な構図の中にあります。そして犠牲を強いられるのは常に弱い立場にある市民です。この状況を打開していくためには、世界の核被害者と連帯して行動することが必要です。
原水禁は今後も「核と人類は共存できない」という揺るがない信念のもと、着実に歩みを進めていきます。被爆80年にあたる今年、改めて地域での原水禁運動の積み重ねの重要性を確認し、一人ひとりの命が大切にされる社会の実現に向けてとりくんでいきましょう。
2025年4月16日
原水爆禁止日本国民会議
第101回全国委員会
2025年04月30日
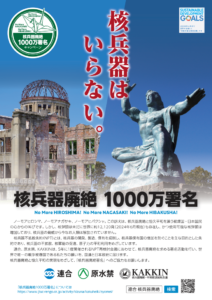
核兵器禁止条約(TPNW)が発効されて4年が経過しました。この間に3回開催されたTPNW締約国会議では、TPNWが核不拡散条約(NPT)を否定するものではなく、むしろ補完する条約であることが繰り返し確認されています。NPT第6条に「核兵器の軍縮を含め、軍縮を促進するために誠実に交渉すること」とあるように、NPTに参加する190か国がそのことを確実に進めていくことを前提としているからです。
いっぽう国際社会では、ロシア・ウクライナ戦争や、パレスチナ・ガザ地区でのイスラエルによる攻撃によって、多くの市民が戦争の犠牲となっています。なかなか停戦が実現しないなかで、核兵器使用も選択肢に入るなどといった発言が繰り返されてきました。日本国内においても核共有を議論すべきという声が政治家の一部から聞かれるなど、核兵器使用のハードルが下がっているのではないかという危機感を強めています。
広島・長崎以降、被爆者をはじめ世界の市民の声が、戦争における核兵器の使用を、辛くも今日まで阻んできました。これから先の未来にわたって、この歴史を正しく繋いでいかなくてはなりません。そのためには、一刻も早く核兵器廃絶を実現させる必要があります。核兵器が存在する限り、いつ使われるかわからないという危険がいつも存在するからです。
原水禁は「日本労働組合総連合会(連合)」と「核兵器廃絶・平和建設国民会議(KAKKIN)」と連携し、2026年春開催予定のNPT再検討会議にむけた「核兵器廃絶1000万署名」にとりくみます。前回の2020年に行った同様の署名の最終集約数は824万7714筆でした。被爆80年の節目にも当たる今回のとりくみは、目標である1000万人の署名を集められるように力を尽くしていきたいと考えます。
原水禁は、核兵器廃絶をめざすすべての皆さんに本署名へのご協力を、心から呼びかけます。
「核兵器廃絶1000万人署名」
呼びかけ団体:連合・原水禁・KAKKIN
とりくみ期間:2025年4月から2026年3月まで
要請先:日本政府・国際連合
要請内容:
私たちは、核兵器廃絶と世界の恒久平和をめざして国連と日本政府に対して次のことを要請します。
〇2026年NPT再検討会議で、核兵器廃絶への着実な道筋について合意すること。
〇「核兵器禁止条約」について、日本政府をはじめとした未批准国は一日でも早く批准し、世界中のあらゆる核兵器の根絶を実現すること。
〇各国政府は、次世代のため、世界の恒久平和に向けた役割を果たしていくこと。
※署名済の用紙は、原水禁にお送りください(〒101-0062東京都千代田区神田駿河台3-2-11連合会館1階)
2025年04月14日
日本教育会館一ツ橋ホールで4月12日に開催した、「核燃料サイクルを考えるシンポジウム」及び5月27日に行った要請行動・意見交換についてまとめた報告書は、以下よりご覧いただけます。
報告書データダウンロードはこちら
【4月12日開催「核燃料サイクルを考えるシンポジウム」報告】
「核燃料サイクルを考えるシンポジウム」が、4月12日に東京の日本教育会館一ツ橋ホールで開催され、約300人が集まりました(主催:核燃料サイクルを考えるシンポジウム実行委員会)。
核燃料サイクルをめぐる国内・国外状況はこの40年で一変し、再処理工場が竣工延期を繰り返す中でも、日本の核燃料サイクル政策は全く変化しません。青森の「4.9反核燃の日」に連帯しつつ、大電力消費地である首都圏から原発・核燃料サイクル政策の根本的転換を訴える機会にするべく、このシンポジウムは企画されました。
シンポジウムは「第一部 問題提起」と「第二部 パネルディスカッション」の二部構成で行われました。
第一部では、鈴木達治郎さん(長崎大学RECNA客員教授)と澤井正子さん(核燃サイクル阻止1万人訴訟原告団 運営委員)のお2人から問題提起をいただきました。鈴木さんは歴史的、経済的、政策的側面から、澤井さんは再処理工場の危険性などについて、お話をされました。
第一部に続いて、主催者代表として鎌田慧さん(さようなら原発1000万人アクション)から挨拶がありました。
休憩をはさんで第二部では、松久保肇さん(原子力資料情報室 事務局長)をモデレーターとして、パネルディスカッション「核燃料サイクル政策を多様な視点で考える」を行いました。パネリストとして鹿内博さん(青森県議会議員 原子力・エネルギー対策特別委員)、足立心愛さん(元Fridays For Futureオーガナイザー)、田中美穂さん(カクワカ広島 共同代表)がそれぞれ問題意識を語った後、第一部にご登壇の鈴木さんと澤井さんを交えて、主に「環境正義」と「核兵器」の2つの観点から、議論を行いました。
なお「核燃料サイクルを考えるシンポジウム実行委員会」では今後、核燃料サイクル政策の根本的転換などを求めて、経済産業省への要請行動を予定しています。
また本シンポジウムの討論は後日報告集(電子データのみ)としてまとめ、「核燃料サイクルを考えるシンポジウム実行委員会」参加団体・個人のホームページ等で掲載いたします。
(6月完成予定、完成後には原水禁ホームページにも掲載いたします)。
以下、シンポジウムでの発言概要
(more…)
2025年04月07日
3月15日福島県民大集会報告



事故から14年にあたる2025年3月15日、福島市パルセいいざかで「原発のない福島を!県民大集会」が開催され、全国各地から約1000人が参加しました。
浪江町の南津島郷土芸術保存会による「南津島の田植踊」から始まりました。
実行委員長のあいさつでは、福島の現状が語られるとともに、「原発事故当時の状況に立ち返り、福島原発事故の教訓とは何だったのか、改めて確認するとともに、福島原発の過酷事故の実情、人々の苦悩、原発事故から得た教訓を、若い世代にも継承していくことも、私達の使命だというふうに思います」と会場の参加者への訴えがありました。
続いて、さようなら原発1000万人アクションから、呼びかけ人で作家の佐高信さんが連帯挨拶をしました。農民文学者である草野比佐男「老いて蹌踉 (おいてそうろう)」の詩の一節を紹介し、福島原発事故や今の政治を作者はどう嘆いたであろうかと、話ました。
集会に寄せられたメッセージの紹介に続き、福島大学 食農学類教授の小山良太さんによる講演「原発事故の教訓をどう生かすか」が行われ、過去の教訓から学ぶことの大切さが指摘されました。
福島からの発信として、「生活再建の状況」、「再生可能エネルギー」をメインテーマに報告がなされ、若者からの訴えでは高校生平和大使から報告が行われました。
アピール採択ののち、「原発事故は終わっていない」「福島の悲劇を繰り返すな」と書かれたプラカードを掲げ、会場一体となってアピールをおこない、最後に閉会あいさつが行われました。
2025県民大集会アピール [PDF]
「2025 原発のない福島を!県民大集会」ホームページ
なお、集会後には、同会場内でフクシマ連帯キャラバンの閉校式が行われています。
原水禁主催「被災地フィールドワーク」報告




「原発のない福島を!県民大集会」の翌日3月16日に、原水禁主催でフィールドワークを行いました。
今回のフィールドワークは、飯舘村長泥地区の視察~浪江町大平山霊園~浪江町請戸港・震災遺構請戸小学校~東日本大震災・原子力災害伝承館視察を予定していましたが、寒の戻りの雪の影響で一部変更しての実施となりました。
飯舘村長泥地区は、福島原発から30㎞以上離れていたことで、極めて高い放射線量に汚染されていることがわかっても、ただちに避難することもできず、4月中旬になって、ようやっと国が全村避難の指示を出したという地域です。翌年2012年7月には帰還困難区域に指定されました。
現在、長泥地区では環境省が主体となって、飯舘村内の放射能汚染土壌を再生資源化するための実証試験を行う事業が進められています。今回のフィールドワークでは、「除去土壌の再生利用」について環境省の説明を聞きながら、試験が行われている田畑を見学しました。
環境省の説明では、除去土壌を基盤にしてその上に盛り土をしたうえで、野菜や米を栽培し、収穫した作物の放射性物質の濃度を検査するなどして、営農できる農地の回復をめざす事業とのことです。
参加者からは、そもそも汚染された土壌を再利用するということの問題、除染されていない山から流れてくる地下水の問題など質問が投げかけられました。
また、中間貯蔵施設にため置かれている福島県内で除染によって出た土壌をどうするのかという問題も非常に難しい課題であることも指摘されました。法律では2045年3月までに県外最終処分することが決まっていますが、「外に持って行ってほしい」という福島県民の願いと、福島県外の自治体や市民の思いに、簡単には結論を出せない難しさを感じます。なによりも事故を起こしてばら撒いてしまった放射性物質の所有者である東京電力の責任があまりにも希薄ではないでしょうか。
春の雪の影響で時間を押してしまい、浪江町の大平山や震災遺構は車窓からの視察となり、東日本大震災・原子力災害伝承館の見学も十分な時間がありませんでした。伝承館については、前日開催された「原発のない福島を!県民大集会」のなかで、東京電力の責任を問う展示がないことが指摘されていました。参加者からは、入館して視る映像が以前は白黒だったがカラーになって現実感があった、脱原発の世論が盛り上がりを見せたことも展示したほうが良いのでは、との感想が出されていました。
2025年04月07日

「3.11福島原発事故を忘れない」をメインテーマに、さようなら原発3.8全国集会が、3月8日東京の代々木公園で開かれ、約3000人が集まりました。
集会は、特設されたミニステージ、野外音楽堂でのメインステージが行われ、集会後にはパレードも行われました。
詳しくは、以下のさようなら原発1000万人アクションのウェブサイトをご覧ください。
3月8日開催「さようなら原発3.8全国集会」報告
TOPに戻る