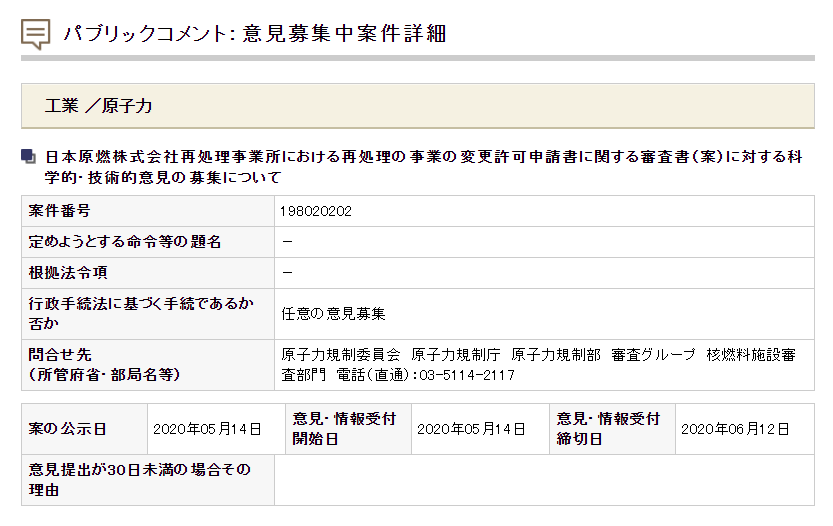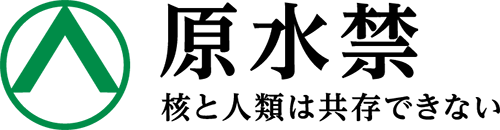再処理 - 原水禁 - Page 2
2020年06月04日
「六ヶ所核燃サイクル・再処理工場新規制基準に関するパブリック・コメントのとりくみ」参考意見について
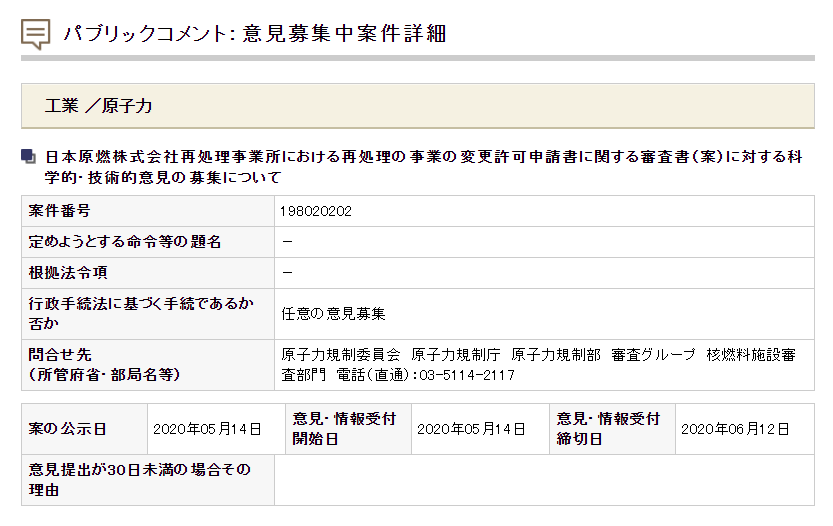
原子力規制庁が5月14日より開始したパブリック・コメントの締め切りが、6月12日と迫っています。
※原水禁ホームページでも、5月21日にご案内しています。
締め切り直前のご案内ではありますが、「核燃サイクル阻止1万人訴訟原告団」の山田清彦さんからパブリック・コメントを提出するための参考意見が提示されていますので、ご案内いたします。
◆「核燃サイクル阻止1万人訴訟原告団」HPはこちら
◆日本原燃(株)六ヶ所再処理事業の変更許可申請書に関する 審査書(案)についてのパブリックコメント文例集 PDFはこちら
◆ パブコメの箇所とそれに対する意見の例 その1
◆ パブコメの箇所とそれに対する意見の例 その2
◆ パブコメの箇所とそれに対する意見の例 その3
2020年05月21日
「六ヶ所核燃サイクル・再処理工場新規制基準に関するパブリック・コメントのとりくみ」について
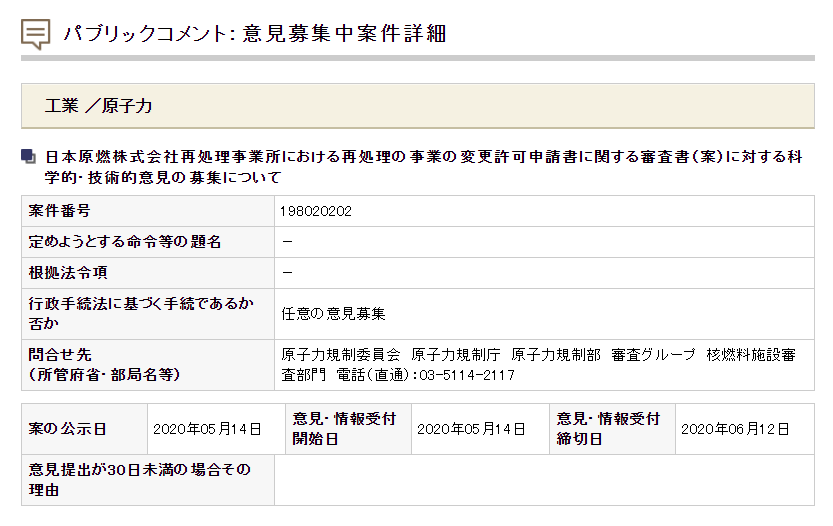
5月13日、原子力規制委員会は、青森県六ケ所村にある日本原燃の使用済み核燃料再処理工場(六ヶ所再処理工場)が、新規制基準に適合していると認める「審査書案」を了承しました。30日間の意見公募(パブリック・コメント)を行った後、「審査書」を正式決定するとしています。
これを受け、同月15日、原水禁は「核燃料サイクル政策の破綻を認め、六ヶ所再処理工場の建設中止を求める原水禁声明」を発出致しました。
現在、原子力規制委員会事務局である原子力規制庁が、意見公募(パブリック・コメント)を開始していますので、パブリック・コメントにおとりくみいただくようご協力をお願いいたします。
意見公募(パブリック・コメント)案件番号198020202
「日本原燃株式会社再処理事業所における再処理の事業の変更許可申請書に関する審査書(案)に対する科学的・技術的意見の募集について」
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=198020202&Mode=0
期間:6月12日まで
応募フォームに沿って、「直ちに核燃料サイクル政策を取り止めるべきである」という視点から意見をお願いいたします。
◆原水禁声明(2020年5月15日付)をご参照ください。
http://gensuikin.peace-forum.com/2020/05/15/kakunen0513/
◆意見公募要領
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000202106
◆原子力規制委員会・審査状況資料
https://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/tekigousei/nuclear_facilities/REP/index.html
◆関連講座のご案内
現在、原子力資料情報室では、再処理問題の論点整理として、連続WEB講座を開催しています。
https://cnic.jp/9104
2012年09月26日
再処理からの撤退は当然だ!
2030年代原発ゼロ?
9月14日、政府のエネルギー・環境会議は、「革新的エネルギー・環境戦略」を決定しました。原発の依存度を減らし、①40年廃炉を厳格に適用、②原子力規制委員会が安全確認を得た原発のみ再稼働認める、③原発の新増設は行わないとする三原則をあげた上で、「2030年代に原発稼働ゼロ」を目指すとし、そのため「あらゆる政策資源を投入する」としました。
9月19日、この方針を政府は、「今後のエネルギー・環境政策については、『革新的エネルギー・環境戦略』を踏まえて、関係自治体や国際社会と責任ある議論を行い、国民の理解を得つつ、柔軟性を持って不断の検証と見直しを行いながら遂行する」として、閣議決定をしました。しかし、方針としての閣議決定にとどめただけで、文書そのものを閣議決定とすることまではいきませんでした。政府の覚悟が疑われます。
「革新的エネルギー・環境戦略」では、使用済み核燃料の再処理問題は、見直されることなく、事業を引き続き進めるとし、高速増殖炉もんじゅは、年限を区切った研究を経て廃炉にするとされ、原発の廃炉や放射性廃棄物の最終処分について国が責任を持つことが示されただけで、具体的な施策は示されませんでした。核燃料サイクルそのものが破たんしているにもかかわらず、問題を先送りしたものとなっています。
さらに、この戦略発表後、島根原発3号機や大間原発、東通原発の計画続行を認めました。原発立地県への配慮が目立ち、「原発の新増設は行わない」との原則と大きく矛盾するものとなっています。「40年廃炉」となれば、それらの原発の廃炉は2050年代以降となるでしょう。「原発稼働ゼロ」に向け「あらゆる政策資源を投入する」とした政府の覚悟や具体的政策が見えません。選挙目当てと言われても仕方なく、政権が代われば、簡単に放棄されてしまうのではないでしょうか。
脱原発に向けた国民的な世論が高まる中で、このような中途半端な戦略では、結局2030年代に「原発稼働ゼロ」は絵に描いた餅でしかなく、いまこそ具体的な原発撤退戦略が求められています。
六ヶ所再処理工場はどうなる?
この「革新的エネルギー・環境戦略」に対して再処理工場の建設を進める日本原燃は、「2030年代に原子力稼動ゼロの方針となったことは極めて遺憾である。エネルギー政策は、5~10年経って失敗だったということは許されない。今後は、本戦略の中で示されたように、絶えず検証を行うとともに、不断の見直しが必要と考える。そして、わが国の将来の視点に立った冷静で現実的な判断をお願いしたい」と、自らの「失敗」を認めず、強引に核燃料サイクル路線を主張しています。
再処理工場そのものは、本来今年10月には竣工するはずでしたが、相次ぐトラブルでさらに1年延長され、来年10月と発表されました。前回の延期(2010年9月)に際し、日本原燃の川井吉彦社長は、「最後の延期。不退転の決意で臨む」と強調していましたが、今回、19回目の延期発表となりました。延期、延期を重ねていまだ完成していないのが六ヶ所再処理工場の実態です。1年先延ばしをしても、順調に事が進むとは限りません。新たに発足した原子力規制委員会がどのような完工前審査を行うのか、これまでトラブル続きだった
高レベルガラス固化施設が今後も順調に動き続けていくのか、これまでの事前確認試験の結果だけでは見えません。さらなる延期が待っているのではないでしょうか。
これまで何度も指摘しているように、作り出したプルトニウムの使い道がないのも問題です。現在、大飯原発が2基稼働しているだけで、残りの48基の原発は止まったままです。再稼働には新たに発足した原子力規制委員会が新基準で評価することになっています。その基準での評価は、来年夏以降となるようです。それ以降でしか再稼働はなく、新たに拡大した防災計画も自治体の対応がこれからという状況にあり、再稼働をめぐる状況は厳しいものがあります。その上プルトニウムを使うプルサーマル計画では、さらに周辺住民などの合意などハードルは高く、2015年までに16~18基の原発でプルサーマルを実施するという計画はすでに破たんしています。原発の再稼働さえ不透明な状況の中、六ヶ所再処理工場でプルトニウムをつくり出す意味はまったくありません。さらに2030年代に「原発稼働ゼロ」を目指すのであればなおさらです。再処理工場は40年間運転を前提にしていましたが、今回の「革新的エネルギー・環境戦略」議論ではその前提さえなくなるものです。
すでに2兆1000億円以上もの資金が六ヶ所再処理工場に投下されています。完成までさらに費用をかけ、その後何年稼働させるのか? 高くつく再処理工場は、本当に必要なのでしょうか。
六ヶ所再処理工場は「5~10年経って失敗だったということは許されない」ではなく、1984年の受け入れから28年経っても完成しないのにいまだ「失敗だった」と認めないことが問題です。プルトニウム利用政策の破たんを直視し、「冷静で現実的な判断」こそ、再処理事業に下されるべきです。
もんじゅは即刻廃炉しかない!
六ヶ所再処理工場とともに、核燃料サイクルの中核を担うとされている高速増殖炉は、もんじゅの開発段階で破たんを来しています。1995年にナトリウム漏洩火災事故を起こして以来17年間、まともに動いたことのない原子炉です。現在も2010年8月の炉内中継装置の落下事故で停止したままです。今後の再開の見通しさえ立っていません。
そして今回の「革新的エネルギー・環境戦略」の中では、もんじゅ開発は、「年限を区切って廃炉にする」となっています。その年限も5年と言われ、放射性廃棄物の減容に寄与する研究が無理矢理付けられて、なんとか研究開発は続行しようとしていますが、そこでの成果など期待できるものではありません。
すでにもんじゅ開発には、9600億円以上の資金が投入されてきました。それらは、すべて私たちの税金です。さらに東海再処理やMOX燃料加工、常陽などの高速増殖炉関連の開発では、さらに1兆7000億円もつぎ込んでいます。六ヶ所再処理工場の莫大な資金投下と合わせて、未完の核燃料サイクルに私たちの税金や電力料金が浪費されています。福島の事態の一刻も早い収束にむけた取り組みに、人やものや資金を全力で投入すべきであり、これ以上ムダな浪費を繰り返している場合ではありません。もんじゅを即刻廃炉にすることがまず先決です。
日本学術会議もNO!
これまでの核燃料サイクル路線は、原発から出てくる使用済み核燃料を全量再処理して出た、高レベル放射性廃棄物をガラス固化して数万年に渡って地中に廃棄処分する計画でした。現在その処分場の候補地さえ見つかっていません。この計画に対して、日本学術会議は見直しの「提言」を原子力委員会に提出しました。(9月11日)。その中で、日本では「万年単位で安定した地層を見つけるのは困難」と指摘しています。これまで「トイレなきマンション」と言われてきた原子力政策が、「トイレ」がないことがあらためて明らかにされました。六ヶ所再処理工場での高レベル放射性廃棄物の処分そのものがあらためて問われています。どこにも処分できるところがないまま、原発をさらに進めていくことは、大量の廃棄物をつくり出すだけで、後の世代に大量の負の遺産となるだけです。2030年代と言わず、一刻も早く脱原発に向けた政治選択と具体的取り組みを取るべきです。とりわけ再処理や高速増殖炉などの核燃料サイクル路線は即刻中止すべきです。
2011年11月30日
高速増殖炉「もんじゅ」廃炉検討
核燃料サイクル路線見直し必至!
ついに担当相が廃炉に言及
今月26日、細野豪志・原子力行政担当相は、高速増殖炉もんじゅについて「一つの曲がり角に来ている」、「(廃炉について)そういうことも含め検討していくべきだ」と発言しました。さらに「前回(2005年)改定のときは、従来の路線を継続したが、今度は問題の先延ばしは許されない」と述べ、現在進められている内閣府・原子力委員会の「新原子力政策大綱策定会議」の中でも廃炉を含めた抜本的な見直しが必要との意向を示しました。
もんじゅは、これまで国が進める核燃料サイクル政策の中核を担うものとして位置づけられてきました。2025年ごろには実証炉(もんじゅは「原型炉」)、2050年には実用炉を導入するとするロードマップを描いてきました。将来は高速増殖炉が原子力の主流を担うこととされていたのです。
しかし、1995年のナトリウム漏洩火災事故をはじめ近年では、炉内中継装置の脱落などの事故を繰り返し、長期に渡って運転が停止し、現在も停止したままです。その間にもんじゅには1兆円を超す資金が投入されてきました。運転停止中のもんじゅ維持のため年間200億円もの資金が浪費されています。事故続きで将来展望の見えないもんじゅに対して見直しの声が政府部内からも強く上がってきました。今月10日から始まった政府の行政刷新会議の「提言型政策仕分け」作業の中でももんじゅの予算やもんじゅの方向性を含め原子力研究開発の是非が問われ、「抜本的な見直しに踏み出すべき」との提言をまとめました。その中で、蓮舫・行政刷新担当相は「『もんじゅ』は1兆円かけて、まだ実験段階。信じられないぐらいの国民の税金とか、電気料が使われてきている」と述べていました。
もんじゅについては、原子力分野を担当した仕分け人7人全員が、抜本的な見直しが必要だと判定。12年度予算の概算要求に文部科学省が盛り込んだ試験費用22億円に対し、「計画そのものを見直すべきだ」として見送るよう提言しました。
そのことは、もんじゅを中心に描かれていた日本の核燃料サイクルの破たんを示すものです。すでに世界は高速増殖炉開発からの撤退をしています。アメリカ、フランス、イギリス、ドイツといった国々では技術的困難性や軽水炉(普通の原子炉)と同じような経済性を達成できない、核拡散の問題など多くの問題を抱える高速増殖炉開発から早々に撤退をしてきました。残された日本が高速増殖炉開発のトップランナーとして走ろうとしてきましたが、その夢も破れようとしています。
プルサーマル計画の破たん
もんじゅだけではありません。高速増殖炉開発の間をつなぐものとして登場した「プルサーマル計画」(普通の原子炉でプルトニウムとウランを混ぜたMOX燃料を燃やす計画)も、今回の原発震災によって計画そのもの実現がもはや不可能となっています。2015年までに16~18基の原発で実施する予定でしたが、来春には全ての原発が停止になることもあって、プルサーマルを実施するより、まず再稼働できるかどいうかという状況です。
さらに先行してプルサーマル発電を行っていた福島第一原発3号機は、爆発によってプルトニウムが飛散したこともあって、通常の原発よりもさらに危険性を高くしています。プルサーマル計画を今後歓迎する地元自治体はないのではないでしょうか。MOX燃料をフルに装荷する大間原発も工事が中断して再開の目途が立っていません。頼みのプルサーマル計画の実施は、もはや“夢物語”でしかありません。
福島原発事故の収束に全力を!
福島原発の放射性廃棄物処理も含め、放射性高レベル廃棄物の処理・処分の問題も残っています。最終的処分場や方法も決まらない中、六ヶ所村で再処理してもそこで生まれたプルトニウムの利用先がなければ、国際公約としての余剰プルトニウムを持たないことを打ち出している手前、これ以上プルトニウムを生産することは許されません。プルトニウムを生み出す六ヶ所再処理工場は、これまた事故と先の震災によっていまだ完成していません。
これ以上、完成に向けた資源と資金の浪費が必要なのか、もんじゅ・プルサーマルの動きを見れば、日本のプルトニウム政策を取り巻く環境は非常に厳しいものがあり、自ずと答えが出るはずです。もはやこれ以上のプルトニウム利用路線の追及に拘泥しているときではありません。福島原発事故の一刻も早い収束に向けた努力に全力を尽くすときです。
再処理推進の本音は核武装のため?
核燃料サイクル路線が行き詰まりを見せ、再処理そのものの存在理由が問われる中で、読売新聞は社説(9月7日)の中で「日本は原子力の平和利用を通じて核拡散防止条約(NPT)体制の強化に務め、核兵器の材料になり得るプルトニウムの利用が認められている。こうした現状が、外向的には、潜在的な核抑止力として機能していることも事実だ。」と主張しています。
自民党の石破茂政調会長(当時)も今年9月に「原発を維持するということは、核兵器を作ろうと思えば一定期間のうちに作れるという『核の潜在的抑止力』になっている」と同じような趣旨の発言をしています。原発も再処理も核武装のために必要とするマスコミと政治家の発言は、ヒロシマ・ナガサキそしてフクシマの惨事が起こった「被爆国」日本の中で、核の悲劇を再び起こすことの「力」をもつことは必要だと述べていることです。「力」は、見せかけでは「抑止」になりません。場合によっては「使うぞ!」ということがあってはじめて「力」となりえるものです。「潜在的核抑止力」だと言えばいうほど日本周辺の国々に対して警戒心を増幅させるだけです。
そもそもこのような考え方は古くからあり、1968年の外務省の内部文書「我が国の外交政策大綱」に「当面核兵器は保有しない政策をとるが、核兵器製造の経済的・技術的ポテンシャル=可能性」は常に保持するとともにこれに対する掣肘(せいちゅう=妨害)をうけないよう配慮する」としていました。しかし一方で、1973年のNPT加盟を論じた外務省の文書では「現段階では核武装する可能性がまったく無い」とし、「一個や二個の原爆と引き換えに失うものは、あまりにも大きい」として前記の主張を退けています。
それを再び、読売新聞も「自民党」もゾンビのごとく持ち出し、住民の安全・安心より国家の論理を押しつけようとしています。国策の名に依って押し進められた原発。またも国策として原発も再処理も押し進めようとする巨大マスコミと政治家。福島原発事故が何故起きたのかもう一度彼らは考えるべきである。地方をまたも犠牲にするのか!
2011年09月28日
さようなら原発集会に6万人
脱原発にむけて大きなうねりに
これまでの脱原発運動の中で最大規模
9月19日、東京・明治公園で開催された「さようなら原発5万人集会」に予想を超える6万人が集まり、これまでの脱原発運動の中では、最大規模となりました。この集会は、作家の大江健三郎さん、鎌田慧さんら9名の著名な方々の呼びかけて行われたもので、市民団体・NGO、労働組合、生協・共同購入会、市民など北は北海道から南は沖縄まで、全国各地から参加者が集まり、被災地・福島からも1,000名近い参加者がありました。
福島の「苦渋の思い」語られる
集会の中で、大江健三郎さんが、自分の先生であった仏文学者の渡辺一夫さんの文章を引いて、「狂気なしでは偉大な事業は決して成し遂げられない、と言う人々もいるが、それはうそだ。狂気によってなされた事業は、必ず荒廃と犠牲を伴う」。これはいま、「原発の電気エネルギーなしでは偉大な事業は成し遂げられない、と言う人々もいるが、それはうそだ。原子力によるエネルギーは、必ず荒廃と犠牲を伴う」と発言しました。
福島からは、「ハイロアクション福島原発40年実行委員会」の武藤類子さんが、「毎日、毎日、否応なく迫られる決断。逃げる、逃げない。子どもにマスクをさせる、させない。洗濯物を外に干す、干さない。何かもの申す、黙る」この間の苦渋の思いを語りました。その他にも呼びかけ人の落合恵子さん、内橋克人さん、澤地久枝さん、鎌田慧さんが発言し、ドイツから環境団体・FoEドイツ代表のフーベルト・ヴァイガーさんと俳優の山本太郎さんが、脱原発を訴えました。
時代の流れは脱原発へ
集会後、渋谷や原宿、新宿にむけてデモ行進を行い、沿道の市民からも応援の声や拍手、クラクションがあちらこちらで沸き上がりました。
今回の6万人の人々の後ろには、参加できなかった人たちが多くいます。その数は10倍や100倍にものぼるでしょう。いま多くの人々が、原発からの脱却を求めています。これまで原発を推進してきた政府や政治家、事業者、官僚、学者などは、この6万人をはじめとする多くの超えに真摯に耳を傾けることを強く訴えます。時代の流れを間違いなく読んで欲しいものです。
●詳しくはこちらから
「さようなら原発1000万人アクションホームページ」http://sayonara-nukes.org/
武藤類子さん(ハイロアクション福島原発40周年実行委員会)の発言要旨
皆さん、こんにちは。福島からまいりました。きょうは福島県内から、また避難先から、何台もバスを連ねて、たくさんの仲間と一緒に、やってまいりました。初めて集会やデモに参加する人も、たくさんいます。それでも福島原発で起きた悲しみを伝えよう、私たちこそが「原発いらない」の声をあげようと、誘いあってやってきました。
初めに申し上げたいことがあります。三・一一からの大変な毎日を、命を守るために、あらゆることに取り組んできた皆さん一人一人を、深く尊敬いたします。それから、福島県民に温かい手を差し伸べ、つながり、様ざまな支援をしてくださった方々にお礼を申し上げます。ありがとうございます。そして、この事故によって、大きな荷物を背負わせることになってしまった、子どもたち、若い人たちに、このような現実を作ってしまった世代として、心から謝りたいと思います。本当にごめんなさい。
さて、皆さん。福島はとても美しいところです。東に紺碧の太平洋を望む浜通り。モモ・梨・リンゴと果物の宝庫の中通り。猪苗代湖と磐梯山の周りに黄金色の稲穂が垂れる会津平野。その向こうを、深い山々が縁取っています。山は青く、水は清らかな、私たちの故郷です。
3.11原発事故を境に、その風景に、目には見えない放射能が降り注ぎ、私たちは被ばく者となりました。大混乱の中で、私たちには様々なことが起こりました。すばやく張り巡らされた安全キャンペーンと不安の狭間で、引き裂かれていく人とのつながり。地域、職場、学校で、家庭の中で、どれだけの人が悩み、悲しんだことでしょう。
毎日、毎日、否応なく迫られる決断。逃げる、逃げない。食べる、食べない。子どもにマスクをさせる、させない。洗濯物を外に干す、干さない。畑を耕す、耕さない。何かにもの申す、黙る。様々な苦渋の選択がありました。
そしていま、半年という月日の中で、次第に鮮明になってきたことは、事実は隠されるのだ、国は国民を守らないのだ、事故は未だに終わらないのだ、福島県民は核の実験材料にされるのだ、莫大な放射能のゴミは残るのだ、大きな犠牲の上になお原発を推進しようとする勢力があるのだ、私たちは捨てられたのだ――。私たちは疲れと、やりきれない悲しみに、深いため息をつきます。
でも口をついてくる言葉は、私たちを馬鹿にするな、私たちの命を奪うな、です。福島県民は今、怒りと悲しみの中から、静かに立ち上がっています。子どもたちを守ろうと、母親、父親、おじいちゃん、おばあちゃんが。自分たちの未来を奪われまいと若い世代が。大量の被爆に晒されながら事故処理に携わる原発従事者を助けようと、労働者たちが。土地を汚された絶望の中から、農民が。放射能による新たな差別と分断を生むまいと、障がいを持った人々が。市民が、国と東電の責任を問い続けています。そして、原発はもういらないと、声を上げています。
私たちは静かに怒りを燃やす、東北の鬼です。福島県民は、故郷を離れる者も、福島の土地に留まり生きる者も、苦悩と責任と希望を分かち合い、支え合って生きていこうと思っています。私たちとつながってください。私たちのアクションに、注目してください。政府交渉、疎開、裁判、避難、保養、除染、測定、原発と放射能についての学び。そしてどこにでも出かけて、福島を語ります。今日は、遠くニューヨークでスピーチをしている仲間もいます。思いつく限り、あらゆることに取り組んでいます。私たちを助けてください。福島を忘れないでください。
もう一つ、お話したいことがあります。それは、私たち自身の生き方、暮らし方です。私たちは何気なく差し込むコンセントの向こう側を想像しなければなりません。差別と犠牲の上に成り立っていることに、思いをはせなければなりません。原発は、その向こうにあるのです。
人類は、地球に生きる、ただ一種類の生き物にすぎません。自らの種族の未来を奪う生き物が、他にいるでしょうか。私は、この地球という美しい星と調和した、まっとうな生き物として生きたいです。ささやかでも、エネルギーを大事に使い、工夫に満ちた、豊かで創造的な暮らしを紡いでいきたいです。どうしたら原発と対極にある新しい世界を作っていけるのか。だれにも明確な答えは分かりません。でき得ることは、誰かが決めたことに従うのではなく、一人一人が、本当に、本当に、本気で、自分の頭で考え、確かに目を見開き、自分ができることを決断し、行動することだと思うのです。一人一人に、その力があることを思い出しましょう。
私たちは誰でも、変わる勇気を持っています。奪われてきた自信を取り戻しましょう。原発をなお進めようとする力が垂直にそびえる壁ならば、限りなく横に広がりつながり続けていくことが、私たちの力です。たったいま、隣にいる人と、そっと手をつないでみてください。見つめ合い、お互いの辛さを聞きあいましょう。涙と怒りを許しあいましょう。いまつないでいる、その手の温もりを、日本中に、世界中に広げていきましょう。
私たち一人一人の、背負っていかなければならない荷物が、途方もなく重く、道のりがどんなに過酷であっても、目をそらさずに支えあり、軽やかに、朗らかに、生き延びていきましょう。ありがとうございました。
TOPに戻る