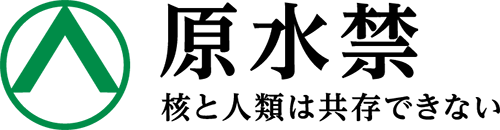2025年、ニュース
4月12日「核燃料サイクルを考えるシンポジウム」を開催【7/7報告集掲載】
2025年04月14日
日本教育会館一ツ橋ホールで4月12日に開催した、「核燃料サイクルを考えるシンポジウム」及び5月27日に行った要請行動・意見交換についてまとめた報告書は、以下よりご覧いただけます。
【4月12日開催「核燃料サイクルを考えるシンポジウム」報告】
「核燃料サイクルを考えるシンポジウム」が、4月12日に東京の日本教育会館一ツ橋ホールで開催され、約300人が集まりました(主催:核燃料サイクルを考えるシンポジウム実行委員会)。
核燃料サイクルをめぐる国内・国外状況はこの40年で一変し、再処理工場が竣工延期を繰り返す中でも、日本の核燃料サイクル政策は全く変化しません。青森の「4.9反核燃の日」に連帯しつつ、大電力消費地である首都圏から原発・核燃料サイクル政策の根本的転換を訴える機会にするべく、このシンポジウムは企画されました。
シンポジウムは「第一部 問題提起」と「第二部 パネルディスカッション」の二部構成で行われました。
第一部では、鈴木達治郎さん(長崎大学RECNA客員教授)と澤井正子さん(核燃サイクル阻止1万人訴訟原告団 運営委員)のお2人から問題提起をいただきました。鈴木さんは歴史的、経済的、政策的側面から、澤井さんは再処理工場の危険性などについて、お話をされました。
第一部に続いて、主催者代表として鎌田慧さん(さようなら原発1000万人アクション)から挨拶がありました。
休憩をはさんで第二部では、松久保肇さん(原子力資料情報室 事務局長)をモデレーターとして、パネルディスカッション「核燃料サイクル政策を多様な視点で考える」を行いました。パネリストとして鹿内博さん(青森県議会議員 原子力・エネルギー対策特別委員)、足立心愛さん(元Fridays For Futureオーガナイザー)、田中美穂さん(カクワカ広島 共同代表)がそれぞれ問題意識を語った後、第一部にご登壇の鈴木さんと澤井さんを交えて、主に「環境正義」と「核兵器」の2つの観点から、議論を行いました。
なお「核燃料サイクルを考えるシンポジウム実行委員会」では今後、核燃料サイクル政策の根本的転換などを求めて、経済産業省への要請行動を予定しています。
また本シンポジウムの討論は後日報告集(電子データのみ)としてまとめ、「核燃料サイクルを考えるシンポジウム実行委員会」参加団体・個人のホームページ等で掲載いたします。
(6月完成予定、完成後には原水禁ホームページにも掲載いたします)。
以下、シンポジウムでの発言概要
==================================
第一部 問題提起
鈴木達治郎さん「核燃料サイクル再考:原子力政策の負の遺産」
原子力推進している人たちの間でも、核燃料サイクルは合理性がないという合意がほぼできている。高速増殖炉がないと核燃料サイクルは成立しない。再処理は直接処分よりも費用が高く、廃棄物処分のリスクを低減しない。
それでも止められない理由は次の5つ。
1.巨大な債務とその負担問題(事業継続ができなくなると債務負担の責任が生じるので、政府も電力も自らの責任で変更を言い出せない)
2.柔軟性を排除する法・制度(再処理等拠出金法で再処理義務づけ、直接処分は法律上できない)
3.立地自治体との約束
4.巨大プロジェクトを運営する組織の惰性(障害があっても前進、仕組みの固定化、経済的に非合理でも政治的に合理的とする、約束の連鎖化、既に投資した額が大きいのでやめられない)
5.狭い意思決定プロセス(止めると損する人たちが意思決定プロセスに入っているので止められない)
結局犠牲者は国民と国際社会。
核燃料サイクル政策変更のため、具体的に次の5つを提言する。
1.使用済み燃料貯蔵量の確保
2.独立した第三者組織による再評価
3.全量再処理から移行するための法改正(福島事故の廃棄物も今の法律では処分できない、原子力基本法も要改正)
4.意思決定プロセスの改革(福島事故直後のような国民的議論)
5.立地自治体、債務負担への対応(移行期間を設けて軟着陸を目指す)
既に日本では国内石炭産業の撤退を実行した実績がある。やる気になればできる。
———————–
澤井正子さん「再処理工場の危険性について」
再処理工場は大量の放射能が集中(原発30基分)し、大量に放出する(原発1年分を1日で)。燃料棒を刻んで高温の濃硝酸に溶かし、有機溶媒(油)を接触させてウランとプルトニウムを取り出すので、原子力施設と化学工場の危険性を併せ持つ。高い放射能汚染のため、耐震補強工事、補修、点検、検査ができない設備、機器類が存在する(レッドセル問題)。
耐震性は450ガルが精一杯で、現行で対応が求められる700ガルの地震には「お手上げ」。直接検査できない機器類は記録による確認のみで国の検査が通ってしまう。
さらに活断層の問題がある。これまで日本原燃が施設に最も影響を与える断層としてきた出戸西方断層よりもはるかに大きな「六ヶ所撓曲」が、地質に関する日本最大のシンクタンクである産業総合研究所の地質図に掲載されたが、日本原燃も原子力規制委員会も無視している。海側の「大陸棚外縁断層」についても関連学会はみな活断層と認めているのに、原子力の関係者だけは認めていない。
「ふげん」の使用済み燃料の再処理をフランスに委託し、取り出したプルトニウムはフランスに譲渡して、ゴミだけを日本に戻すことにした。関西電力のMOX燃料もフランスで再処理するという。英国政府は民生用のプルトニウムがゴミであるとして地中への廃棄方針を決めたが、日本ではプルトニウム利用のためでなくゴミ対策としての「新しい再処理」になっている。核兵器の観点でも問題。こんなことを税金でやっていて良いのか。再処理を止めよう。
———————–
主催者代表 鎌田慧さん挨拶
今までは原発反対、再稼働反対という運動だった。残念ながら核燃料サイクル反対という運動はなされていなかった。青森では運動があり1989年4月9日に1万2千人の大集会が開かれたが、その後は大集会には結びつかなかった。そういう意味では、今日は東京で核燃料サイクルの運動が始まってきた。今まで核燃料サイクルの危険性は大衆運動的にほとんど指摘されてこなかった。それは一つには、青森県の核燃料サイクル施設がほとんど知られてなかった。
青森県が核燃料サイクル施設建設候補になったのは1969年の新全国総合開発計画、列島改造計画の中にあった。公害問題があったから遠距離に巨大な工業地帯を作るのが新全国総合開発計画だった。下北は原子力のメッカになると中曽根が言い始めた。ここを核燃料サイクルにすると電事連が発表したのが1984年。そのときの予算は低レベルの廃棄物の処分場、ウラン濃縮工場、再処理工場で1兆円。今、20~30兆円と言われている。とにかく膨大な予算が投入されている。
今でも再処理工場は稼働していなくても利益を計上し地元に税金を落としている。六ヶ所村、むつ市は政府の補助金が不要な黒字経営をしている。危険な施設があると国が補償するということで、原発の反対運動がない。原発は最初から金でやってきた。原発政策を維持するためだけの机上の空論の核燃料サイクルに対しどう反対運動をしていくか。最後には国会でどうやって中止するか。
「下北核半島」から「下北核処分半島」に今なっている。下北は核燃料サイクルと原発と中間貯蔵施設、それから軍事施設、三沢の米軍基地、自衛隊の陸海空がそろっている。日本の政策の犠牲的な地域となっている。それがようやく東京で集会ができるようになった。
日本全体の核政策に対しての反対運動、原発、最終処分場、再処理工場、膨大な運動が必要だが、どう構築していくか、議論していく第一歩の集会として位置づけられると思います。
———————–
第二部 パネルディスカッション「核燃料サイクル政策を多様な視点で考える」
鹿内博さん:
青森の実情を少しでも知ってもらえるとありがたい。
再処理を口実に青森県に核のゴミを集めている。国や事業者が40年前に約束したことはほとんど反故されている。残ったのは、40年前以上に色々な問題が出てきている。原発を止めないと核のゴミは解決できない。
今一番の問題は、高レベル放射性廃棄物の最終処分地にしないこと。「30年後に搬出」と言って、今月の4月25日がその「30年後」。再処理工場はできていない。これまで何十年もかかってできなかったことが、今後20年間でできないだろう。結局、何十年、何百年とかかり、最終処分場になる可能性がある。そのため、国に対して引き取るよう伝えたい。5月13日に国を相手にしたヒアリングをする。ぜひ参加してください。
「原発」と違って、「核燃料サイクル」という名前の施設はない。
むつ中間貯蔵施設があるからという話があるが、地元では受け入れるつもりはない。
原発解体後の処分場はない。が、六ヶ所低レベル放射性廃棄物埋設センターと1984年の電事連の資料に書いてある。
土地、借金を使う形で、下北半島に核燃料サイクルが集中した。使用済み核燃料など、名前と形を変えて青森に集まってくる。
トイレなきマンション問題。70年前からそういわれているにもかかわらず現状をみると、今後も変わらない状況だろう。
国、事業者は約束を守らない。福島にも立地自治体の苦悩がある。
国は計画は実現できないし、約束は守らない。青森県はその犠牲になるわけにはいかない。
足立心愛さん:
きっかけは気候変動対策について同世代の活動家の言葉に衝撃を受けたこと。政治に何かしてもらえるわけではなく、個人的にできることをしていても変わらないと気づいたので、政府への働きかけなどを行うようになった。
温暖化で花粉症や火災など、すでに多くの影響が出ている。
カーボンニュートラルと言われているが、2050年、私は44歳。自分ごととして真剣に考えざるを得ない問題。
裕福な10%の人たちが、温暖化となる50%の影響を出している。グローバルノースとサウスの格差もある。「他の誰かに押し付ける構造」は気候変動以外にも原発、核燃料サイクルにも共通している。
核燃料サイクルと将来世代について言えば、建てるときには金額は考慮されるが、その後のことは考慮されていない。廃棄物によるマイナス影響を抜きに原発を語るのはおかしい。
高レベル放射性廃棄物は10万年の問題。地震多発国、MOXなど安全性に問題があるのになぜ続けるのか。将来世代は自分たちが決めてないのに安全でない世界で生きていく。
意思決定プロセスに若者がいない。これから生まれる世代は参加できない。政府の意向のみで決まるプロセスを変えないと。
地域のためになる、市民のためになる、国民のためになるエネルギー政策を考えていく必要がある。将来世代に大きな負担を強いないエネルギーのあり方を将来世代と一緒に考えていく。
田中美穂さん:
核兵器禁止条約について国会議員に面会して見解を聞き、カクワカのウェブサイトに掲載している。
願っているだけでは変わらない、政治が変わらないと、と実感し、活動している。
核兵器禁止条約は、人道的視点から核被害者にフォーカスした初めての条約。核を使われる側の視点が大切。ほぼ世界の半分が入っているが、核兵器保有国、同盟国の日本などは入っていない。
ニューヨークで開催された第3回締結国会議に参加した。議長は核実験被害国カザフスタンの方。グローバルヒバクシャといって世界中に被爆者がいる。マーシャルの人とも交流した。
原発と核廃絶は一緒に考えていかなければならない。全ての工程に犠牲が伴うサイクル。これは植民地主義の問題だと考える。一部の利益を持つ人たちの影響で、被害を受ける人々、そしてその他の多くの人が無関心でいられるマジョリティー。そこを解体することが私たちに課せられたことだと考えている。
気候正義同様に、ニュークリアジャスティスという事も言われている。人間の尊厳の問題。新たな被害を生まないために日本でも広めたい。
鈴木さんコメント:
鹿内さんへ:核燃料サイクルの問題は核のゴミの問題である。まさにその通り。国は約束を守らないと言われた。第三者機関、国民が信頼できる人が守ると言わなければならない。
足立さんへ:今決めることが何十年後の人々へ影響するという点。同様に1960年代に決めたことが今響いてきている。弱い立場の人が影響を受ける。科学に基づく政策決定ができていない。
田中さんへ:国会議員に核燃料サイクルについても意見を聞いて公開しては。条約に入らないのは、核抑止を信じているから。実体のないものを信じているのは核燃料サイクルと同じ。「プルトニウム生産過程」など、名前を変えては。
澤井さんコメント:
サイクルという言い方がイカサマ。入口も出口もゴミの問題。最初に鹿内さんがおっしゃったように、六ヶ所に低レベル、高レベルと、実体のあるものは全部青森に置いてある。政策を止めてもそのゴミが残る。それをどうするのか、どこから議論を始めればいいのか。
昔、三重県の芦浜原発計画を知事が止めたとき、市民は18歳からの意見を反映させるような自主県民投票を行った。
今まではゴミを捨てたい人たちがその人たちだけで集まって決めてきた。
再処理の費用を電気料金に乗せることにしたとき、当時の東電の荒木社長は「こんなにかかるとは思わなかった。受益者負担にしてくれ」と言った。国民は原発から益を受けているんだという論理。まだ生まれていない子どもたちからもお金をとると。ゴミを発生した責任は? 根本的に立ち止まらないと。3人の話を聞いてそう思った。
———————–
議論 テーマ1:環境正義の観点から
松久保さん:
正義という概念、公平、公正に決定されているのか、とても重要。どうすればいいのか?
鹿内さん:
田中さんが植民地主義的な状況からの脱却という点を言った。
すべての国民はどの地域にいようが、平等、公平であるべき。それが正義。
なぜゴミはすべて青森なのか?
大都市でダメなものは、地方でもダメ。
松久保さん:
廃炉廃棄物、次の世代に重荷を押し付けていく形になっている。どのように若い世代を含め、議論していけるのか。
足立さん:
審議の場に若者の委員を入れる。
パブコメが機能していない。書いても反映されない。
政策を決める前に市民の意見を聞いて、その意見がきちんと反映される仕組みづくりが重要。
松久保さん:
核兵器禁止条約は市民の力で作ってきたと思う。どのように市民が民主主義を守っていけばいいか。
田中さん:
会議に日本政府はオブザーバーとしても参加していないが、7名の議員が来て海外との議員と意見交換した。自分たちの味方を着実に増やしていくことが必要。
核廃絶というと議員は乗りやすいが、そこに原発、核燃料サイクルを入れていくと、嫌悪感が出てくるような雰囲気がある。この問題についても議員とかかわりを作っていく必要がある。
松久保さん:
ずっと関わっている鈴木さんから見て?
鈴木さん:
原子力は男性、年長者、技術者が主流派。正義や公平は後回し。
核兵器禁止条約では被爆者の方々の声が大きかった。同じことが環境や原子力でできるのかが問われている。
今回の締約国会議では「科学に基づく意思決定」が前面に出された。
核燃料サイクルも、科学的根拠に基づいた政策ができていない。
ただし、科学的には1か所に置いてしまうのが合理的。それは公平ではない。
意思決定で科学的根拠と社会的な倫理を組み合わせなければならない。
それが信頼されていない状態なのではないか。
松久保さん:
どうやって都会の人間も考えるようになるのか。
澤井さん:
原発を東京に建てろと言いたい。福島で放射性物質をかぶった人たちのことを東京の人たちは考えず、停電が怖いなどの声。都会の問題が地方の問題にされている。
反対派は経産省などで、人間として扱ってもらえないような蛇蝎のように嫌われていた存在という感じだった。
原子力で環境と言ったら、廃棄物の問題。廃棄物を覆い隠すことをやってきた。
大規模開発で困った青森のために核燃料サイクルを持っていったという感じなのでは。さらに、金を持っていけばいいというような感覚。安全対策ではなく住民対策でお金を出している。
廃棄物については、科学的根拠も社会的合理性も考えられていない。歪んだ政治の極みが原子力。
みんなで世直しをまたすべきだろうと思う。
———————–
議論 テーマ2:核兵器の観点から
松久保さん:
最近韓国で、核兵器を持ちたいが実際難しいだろうから、日本のように核燃料サイクルなど技術的なものを持てればという議論が出ている。
それは日本が潜在的な核兵器保有国として見られているという背景がある。日本は二つの顔を持っていると思う。どのように見るか?
田中さん:
核廃絶のことを言っているとメディアにも取り上げられやすいが、原発や植民地主義の構造の話をしても全く取り上げられない。
メディアの取り上げ方も大きな問題があると思っている。
そこで何とか組み込んでいこうといつも思っているが、なかなかできていない。
松久保さん:
核兵器に関するグループにも入っているが、核燃料サイクルの話をしてもピンとこないよう。核兵器禁止条約は最後のステップ。その前の段階で核物質を作るのを止めないと核廃絶に向かわない。どのようなステップを踏んでいくべきなのか。
田中さん:
組み合わせることが運動の中でもできてこなかった。今仰った条約自体が最後のものと言われていた。
岸田首相は条約は日本が目指す最後の出口だと言った。踏み込んだという捉え方もあったが、「最後」という事で取り組みも最後にされるという、先手を取られたという捉え方もあった。私たち市民運動としてはこれは最初の入口で、まず入って世界をリードすべき。核保有国が入るのが最後の過程。
松久保さん:
日本で核兵器廃絶と核燃料サイクルが関連して考えられていないのはなぜか。
鈴木さん:
原子力と核兵器が全く異なるものだというイメージを植え付けられてきた。
核抑止が必要だと言っている段階では核廃絶は無理。どこかの時点で早めに舵を切らないといけないと私たちは言い続けている。
核不拡散条約は原子力平和利用の権利を認めているので、原子力そのものの否定は国際条約上難しい。ただし兵器に使われるウラン濃縮技術と再処理はコントロールしようという動きは以前からある。
「核燃料サイクル」イコール「核物質生産装置」。これを持っている国はわずかしかない。
プルトニウムは全くいらない。原発を動かすうえでも不要。
まずはこれから始めるのがいいのでは。
松久保さん:
日本がステップを踏むべきではというのならば、日本が核燃料サイクルを止めると宣言したらいいのではと思うが、何故やらないのか。
鈴木さん:
止めたくても止められない。止めたら損をする人たちがハンドルを握っているので難しい。核抑止も似ている。もし政権交代があれば変わるかもしれない。
松久保さん:
審議会で何を言っても聞いてくれない。市民活動は何をしていけば良いか。
足立さん:
求める内容としては、第三者機関が必要だと思った。科学的な視点のあとに、国民の意見を反映する。
市民活動のやり方は、議員との話し合い、メディアとの関係、道でアクションなど。いろいろな方向から自分の得意な分野を使いながら、連帯してやっていくことが重要だと思う。
鈴木さん:
3.11後の脱原発デモは大きく、政府の中にいても聞こえてきた。そのとき政府は15%でやろうとした原発を一度はゼロにした。核兵器問題も同じだと思う。諦めたら終わり、声を出し続けることが重要。
澤井さん:
原子力のゴミはこの国ではタブーだった。日本では低レベルの六ヶ所村が早い時期に決まったので、大変な問題が後送りにされてきたことが現状だと思う。原子力のパンドラの箱は青森で、政府も電力会社も触りたくない。黙っておけば国民がお金を払ってくれるとして、無責任。普通の企業なら最後の廃棄物までのプランがあって当たりまえ。
27回目の竣工延期をやっていて、30回目の延期を行わないとは思えない。原子力は場当たり。こういうことを許してしまう民意の問題もある。
そこに対して鹿内さんは穴をあけたいと思っているのでは。
鹿内さん:
核兵器も核のゴミも人間の手に負えない。責任を負える人がいない。受け入れる人も地域もいない。即やめるべき。
安全に責任を持つという人を見たこともない。処分場について国民的議論というが、うちの役所が企業が責任を持つという人はいない。
私は43歳で核燃料サイクルを止めさせたいと思い県議になったがまだできていない。今年の約束は今月だが、次の約束の2045年4月25日まで生きていたい。核のゴミが青森から持ち出される前には死ぬわけにはいかないという人たちがいたが、何人かは鬼籍に入った。国の政策としてこれほど約束を守れない政策は見たことはない。できないことはやるべきではない。
当時は北村知事。野球場を作ろうとしたところの開発をやめ三内丸山遺跡にしたのは北村知事の決断。ブナの森を切り開く計画を進めてきた当時の北村知事が結局止めた結果、世界遺産になった。だから止めさせることはできる、やめさせるまでは死なないと言いたい。
———————–
最後に一言
田中さん:
核廃絶と交差する問題がたくさんあり、運動も交わって行かなければと思った。普段の話の中でも原発、核燃料サイクルの話を入れていきたい。止めていけることができるリーダーを私たちが選ぶことも重要。今の運動が何十年後を変えていくことを学ばせていただいたので頑張りたい。
足立さん:
正義の話、公平、公正の話はどの問題でもつながるものだと思った。ぜひそこで手を取り合って活動していければ。希望は捨ててはならないなと思う。世論を盛り上げ、今度も活動していきたい。
鹿内さん:
5月13日に衆議院議員会館で集会を行うので、ぜひご参加ください。
澤井さん:
鹿内さんの話の続きで、六ヶ所でも三内丸山に負けない遺跡が出ていた。六ヶ所はつぶしていいという政治的な判断が県庁にあった。恐ろしいほどのお金や人間が注ぎ込まれた。知らない人に、1人でもいいので伝えてほしい。こういう問題を残していたら、日本はまともな国にならない。
鈴木さん:
民主主義が問われているという事だと思う。自分の問題だとして考えてもらう。青森だけの問題ではない。メディアはぜひ記事に書いて。
==================================
以上、「核燃料サイクルを考える実行委員会」として作成した文章となります。