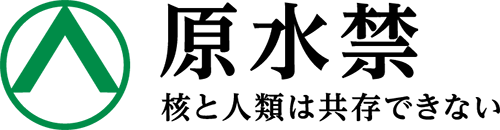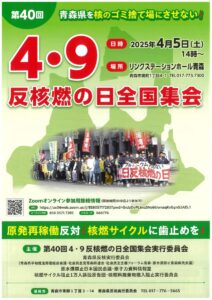2月, 2025 - 原水禁
2025年02月25日
中国電力が上関町に中間貯蔵施設の建設計画を明らかにし、立地可能性調査を始めたのは2023年8月のことでした。多くの町民には「寝耳に水」でしたが、町はすぐに計画を受け入れ、住民や周辺市町からは困惑の声が上がりました。その後、中国電力は2024年4月から、建設予定地でボーリング調査を実施し、同年11月に現地の掘削作業が終わりました。今後、中国電力が採取した試料を分析して活断層の有無などを調査し、適地かどうかを判断する見通しとなっています。
しかし、これまでの流れの中で取り残されているのは、周辺自治体を含めた住民たちです。上関町は原発の新設を巡って40年以上も住民が翻弄されてきました。中国電力が40年余り前から祝島の対岸にある上関町の予定地に原子力発電所の建設を計画する一方、上関町内の別の場所で、使用済み核燃料の中間貯蔵施設の建設に向けた調査を進めたのです。そして、適正な環境影響評価さえも行わないまま、中間貯蔵施設建設に向けた動きが進んでいます。
一方的に押し進められようとする中間貯蔵施設建設について、その撤回を求めて原水爆禁止山口県民会議などが呼びかける署名に、ご協力をお願いいたします。
「上関中間貯蔵計画の白紙撤回を!環境影響評価なしに適地判断を 行わないよう求める署名」
1.要請内容
①上関における中間貯蔵施設建設計画を撤回すること。
②中国電力が7学会の要望書に真摯に対応すること。
③適正な環境影響評価なしに中間貯蔵施設の適地判断を行わないこと。
2.集約締め切り 2025年4月30日(水)
3.集約先 原水爆禁止山口県民会議
〒753-0063 山口県山口市元町3‐49 自治労会館内
℡ 083‐922-1841 FAX 083‐924-8145
4.署名用紙 「署名用紙」をダウンロードしてご利用ください。
******************************
中国電力(株)社長 中川賢剛 様
上関中間貯蔵計画の撤回を!
環境影響評価なしに適地判断を行わないよう求める署名
中国電力は 2023年8月2日、山口県上関町において使用済み核燃料の中間貯蔵施設の建設を検討していることを明らかにしました。私たちは大規模な自然破壊をともなうこの計画に対して反対の立場を明確にし、申し入れや署名活動を展開してきました。
しかし、昨年4月から 11 月にかけて中国電力によるボーリング調査が行われ、今後適地かどうかの判断が行われようとしています。このような動きに対して、さる 12 月 12 日、7学
会にわたる研究者組織から「適正な環境影響評価を求める要望書」*が提出されました。
同要望書は適正な環境影響評価がまったく行われないまま中間貯蔵施設建設に向けた動きが進行していることは、改正「環境影響評価法」をはじめとする複数の法の理念や県の生物多様性戦略にも反するものであると厳しく批判し、直ちに最新の知見に基づく総合的な環境影響評価を実施すべきであると要望しています。
私たちは改めて中間貯蔵施設建設に反対するとともに、7学会による要望を支持し、以下のことを要求します。
【 要 請 事 項 】
1.上関における中間貯蔵施設建設計画を撤回すること。
2.中国電力が7学会の要望書に真摯に対応すること。
3.適正な環境影響評価なしに中間貯蔵施設の適地判断を行わないこと。
2025年02月25日
1985年4月9日、北村正哉・青森県知事(当時)が核燃料サイクル施設の受け入れを決定したことから、この日を「反核燃の日」と制定しました。
そして、原水禁は、現地実行委員会とともに、核燃料サイクル政策に反対し、原子力政策そのものに反対する抗議集会を青森現地で重ねてきました。
今年も核燃料サイクル政策撤回を求め、脱原発を訴える集会を行います。
全国からのご参加、お待ちしております。
チラシはこちら
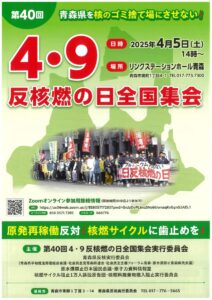
なお、下部に原水禁主催の「全国交流集会」、6日に実施するフィールドワークのご紹介も記載しておりますので、ご覧ください。
4.9反核燃の日全国集会
日 時 2025年4月5日(土) 14時~15時集会・15時20分~デモ行進
会 場 青森市文化会館(リンクステーションホール青森)5階会議室
主 催 「第40回4・9反核燃の日全国集会」実行委員会
原水爆禁止日本国民会議/原子力資料情報室/青森県反核実行委員会(青森県平和労組会議、自治労青森県本部、社民党青森県連合、フォーラム青森、原水禁青森県民会議、核燃サイクル阻止1万人訴訟原告団、核燃料廃棄物搬入阻止実行委員会)
連 絡 先 「第40回4・9反核然の日全国集会」実行委員会(青森県反核実行委員会)
青森市青柳1丁目3-14青森県社会文化センター内
電話017-776-5665/FAX 017-777-3238
(more…)
2025年02月19日
日本政府が核兵器禁止条約(TPNW)第3回締約国会議への不参加を表明したことに対し、原水禁は以下の声明を発表しました。
日本政府の核兵器禁止条約第3回締約国会議への不参加決定に抗議する
2月18日、岩屋外務大臣は3月3日から7日にかけてニューヨークで開催される核兵器禁止条約(TPNW)第3回締約国会議(3MSP)に、日本政府としてオブザーバー参加を見送る方針を表明し、「大変難しい、厳しい判断をせざるを得なかった」と述べた。
TPNWが発効して4年。これまで日本政府はTPNWに対して、「核兵器のない世界の世界への重要な条約」としながらも、核保有国が参加していないことを理由に、批准に否定的な姿勢を崩そうとはしていない。一方で、核保有国と非核保有国の「橋渡し役」を担うとしているが、非核保有国を中心に発効されたTPNWに消極的な態度を示しながら「橋渡し役」など務まるはずがない。
原水禁はTPNW発効につながった国際社会における「核の非人道性」の確立において、被爆者が果たしてきた役割は非常に大きなものであったことを認識し、被爆の実相を証言してきた被爆者のみなさんに心からの敬意を表する。
2024年にはそれまでの成果が認められ、日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)がノーベル平和賞を受賞した。こうしたなかで、日本政府が被爆80年にあたって核兵器廃絶に向けとりくむことに国内外の期待が集まっていたところだった。
いま国際社会では、ロシアやイスラエルなど、軍事力で問題を解決しようとする国々の姿勢によって、核兵器使用リスクが高まりつつある。同時に、そうした姿勢を許さず、核兵器廃絶を求める声も高まり続けている。
そのような状況にあって、日本政府がTPNWに前向きな姿勢を示さないばかりか、オブザーバー参加さえも見送るということは、日本政府が核兵器廃絶そのものに否定的だと国際社会に受け止められるだろう。それは戦争被爆国である日本政府のとるべき態度ではない。
今回の参加検討においては、日本政府は過去の締約国会議にオブザーバー参加した国の事例を検証するとしてきた。ドイツやノルウェー、オーストラリアなどの事例をどのように具体的に検証したのか、その実態が説明されることはなかった。そもそも検証を行うにあたり、当然あるべき「オブザーバー参加する」という方向性が確認されていたのかも疑わしい。
すでに日本からも多くの市民団体やNGO団体、個人が第3回締約国会議に参加するため準備を進めている。原水禁も核兵器廃絶を願う国際社会において、これまで積み重ねてきた市民の連帯を深めることが重要だと考え、「すべてのヒバクシャ救済」と「核廃絶」を両輪として進めてきた原水禁運動の具体化をはかるため、第3回締約国会議に向け代表団を派遣する予定だ。
これまでの締約国会議のなかで私たちに寄せられてきたのは、「なぜ原爆被害の凄惨さを一番経験している日本がTPNWに参加しないのか」という、至極当たり前の疑問の声だ。原水禁はこれまでも、日本政府に一刻も早いTPNWへの署名・批准を求めて運動を展開してきた。今回の参加見送りに、被爆者を中心に落胆の声が大きく拡がっているが、ここで運動の歩みを止めるわけにはいかない。
日本政府がTPNW第3回締約国会議への参加を見送ったことは、核兵器廃絶に向けた国際社会の流れに逆行している。日本政府が示す方針はアメリカの「核の傘」に守られることに拘泥し続けており、核兵器の存在を支えている核抑止論を自らのりこえようとする姿勢は見られない。被爆から80年経とうとする今日において、一日も早い核兵器廃絶の実現を願う被爆者のおもいに応えることとは程遠いと言えるだろう。
私たちは今後も粘り強く、日本政府にTPNWへの署名・批准を求めていく。それが被爆80年を迎えてもなお、苦しみ続ける被爆者のおもいを受け止めることにつながると考える。そして核も戦争もない社会の構築に向けて、今後も原水禁運動を積極的に展開していくことを改めて決意する。
2025年2月19日
原水爆禁止日本国民会議
共同議長 川野浩一
金子哲夫
染 裕之
TOPに戻る