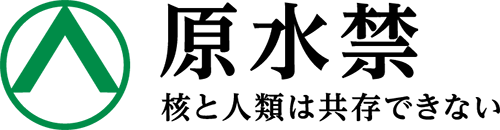2020年、ニュース、分科会報告、原水禁大会、原水禁大会 2020年、注目記事、被爆75周年原水禁世界大会
被爆75周年原水爆禁止世界大会 基調(全文)
2020年07月26日
被爆75周年原水爆禁止世界大会 基調(全文)
2020年7月26日公開
(1)核兵器をめぐる世界の現状と運動の課題
■核兵器をめぐる現状
2017年7月7日、国連加盟国193カ国中122カ国の賛成で「核兵器禁止条約」が採択されました。人類史上初の核爆弾投下から75年、核兵器を「国際人道・人権法」に反する「非人道兵器」として、核兵器の開発、実験、製造、等から使用、そして使用の威嚇も含めて国際法で「禁止」する、被爆者や核実験被害者、原水禁運動、世界の反核運動が、長年にわたって求め続けている「核兵器廃絶」への歴史的一歩としてきわめて重要な条約です。2020年7月7日の太平洋島嶼国のフィジーの批准により、現在世界で条約を批准した国は39カ国、条約発効に必要な批准国数50まで残り11カ国となりました。早期の条約発効が待たれています。
日本政府は、核兵器禁止条約は、核兵器保有国と非保有国の対立を生み、核兵器廃絶への建設的協力を阻むことにつながるとして、交渉に参加せず条約そのものに反対してきました。また、「核兵器禁止条約が目指す核兵器廃絶という目標を共有している」としながらも、北朝鮮の核・ミサイル開発は、日本及び国際社会の平和と安定に対するこれまでにない、重大かつ差し迫った脅威であり、そのことに対応するためには、日米同盟の下で核兵器を有する米国の抑止力を維持することが必要だとして、条約に賛成することは、米国による核抑止の正当性を損なうと主張しています。日本政府の、「核兵器禁止条約では、安全保障の観点が踏まえられていない」という主張は、条約自体を否定するもので、これまでの被爆者の思いと行動とは相容れないものです。私たちは、「核抑止力」という欺瞞を許さず、日本政府に「核の傘」からの離脱を求めるとともに、核兵器禁止条約の署名・批准を、強く迫らなければなりません。
米科学雑誌「原子力科学者会報(BAS)」が発表する「世界終末時計」は、2018年1月以降、米ソ(当時)が水爆実験に成功した1953年以来最小の数値である2分前を示していました。しかし、2020年1月23日、BASは「世界終末時計」の針が20秒進んで残り100秒となり、1947年の開始以降、最も「終末」に近づいたと発表しました。発表に当たって、BASの委員は口々に、「世界が複雑な脅威に対抗するための手段を軽視するか放棄している」「我々が指摘したことは改善されず、不穏な現実となっている」として、残り時間は秒単位で警戒レベルは深刻だとしています。「終末時計を巻き戻せ(#RewindtheDoomsdayClock)」をメッセージとしたBASの勧告は、「包括的共同行動計画」(イラン核合意)からの米国の離脱、中距離核戦力全廃(INF)条約からの米国の離脱による失効、先行きの不透明な新戦略兵器削減条約(新START)、米中露による対立の激化に加えて、リーダーたちによるサイバー空間を利用した情報戦が事実と政治的キャンペーンの境を曖昧にし、民主主義が核兵器や気候変動及び他の実在する危険に立ち向かう力を削いでしまっていることへの憂慮を表明しています。
人類史上初の原爆投下から75年が経過してもなお、私たちは原子爆弾の脅威から逃れることができないでいます。「ストックホルム国際平和研究所」は、6月15日、2020年1月時点での世界の核兵器数を発表しています。
核兵器保有国の保有数(2020年1月現在)
| 国 名 | 配備核弾頭数 | その他弾頭数 | 核兵器数(2020年) | 同(2019年) |
| 米 国 | 1,750 | 4,050 | 5,800 | 6,185 |
| ロシア | 1,570 | 4,850 | 6,375 | 6,500 |
| 英 国 | 120 | 95 | 215 | 200 |
| フランス | 280 | 10 | 290 | 300 |
| 中 国 | - | 320 | 320 | 290 |
| インド | - | 150 | 150 | 130-140 |
| パキスタン | - | 160 | 160 | 150-160 |
| イスラエル | - | 90 | 90 | 80-90 |
| 朝 鮮 | - | [30-40] | [30-40] | [20-30] |
| 合 計 | 3,720 | 9,680 | 13,400 | 13,865 |
※ -は0を意味します。[]は不明確のため、合計数には含まれない。
(SIPRI YEARBOOK 2020およびHiroshima for Global Peace参照)
発表によれば、核兵器保有国の核兵器保有数は、2020年は2019年から465減少しています。この数は、米国とロシアの減少数(米△385、ロシア△125)510が大きく寄与していますが、しかし、米国・ロシアともに老朽化による廃棄数であり、両国が核兵器の近代化に取り組んでいることを考えると核兵器廃絶へのアプローチによるものとは考えられません。中国も核関連設備の近代化に取り組み、核保有数を30ほど増加させています。インドや朝鮮の推計値の増加など、核を取り巻く状況は深刻です。
世界は、核の近代化の進展、米中露の対立と核軍拡競争、特に米トランプ政権の自国第一主義をあらわに世界との協調性を欠いた外交政策、「核態勢の見直し」などによって、核軍拡へと世界は大きく転換させられています。
■連合・KAKKINと連携し、核禁条約の発効と核軍拡の中止・核軍縮を
原水禁は、連合・KAKKINと協力し、日本政府に核兵器禁止条約の批准を求める「核兵器廃絶1000万署名」を展開し、800万筆をこえる署名を集約しました。しかし、今年4月末に開催予定だった核拡散防止条約(NPT)再検討会議は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い延期されました。同時に、原水禁・連合・KAKKINのNPTへの代表派遣も困難となり、現在国連・日本政府への署名提出も先送りされています。
核不拡散条約(NPT)再検討会議は、インド、パキスタン、イスラエル、南スーダン、朝鮮の5国を除く世界191カ国・地域の国連加盟国で構成された、核問題を議論する最大の組織であり、その存在はきわめて重要です。しかし、核保有国と非核保有国との意見の相違などから、2015年の再検討会議では最終文書を合意するに至りませんでした。2020NPT再検討会議の準備会合においても、2020NPT再検討会議の方向性を決定づける勧告案を議論しましたが、核保有国及び、その「核の傘」の下にいる同盟国と、核軍縮を求める非核保有国との核兵器廃絶をめぐる溝は埋まらず、採択に至りませんでした。前回の2015NPT再検討会議と同様に、2020年も最終文書の合意に至らなければ、NPTそのものの存在意義が問われることになります。NPT条約第6条には、「核軍備競争の早期の停止及び核軍備の縮小に関する効果的な措置につき、…全面的かつ完全な軍備縮小に関する条約について、誠実に交渉を行うことを約束する」と明記されています。NPT体制の強化は、核軍縮・核不拡散を推し進め核兵器廃絶に進むために重要であり、日本を含め、核抑止に拘泥し核兵器禁止条約に背を向ける外交姿勢は、核軍縮と全面完全軍縮への努力を定めたNPT条約第6条に反するものです。今こそ、非同盟諸国や世界の多くの反核平和NGOを中心とした「核兵器禁止条約」発効への努力を重く受けとめ、非核保有国全ての意思統一が図られなくてはなりません。唯一の戦争被爆国を名乗る日本政府が、米国の核抑止力に頼る安全保障政策を改め、核兵器禁止条約を先ず署名・批准し、核兵器保有国に対して他の非核保有国とともに、核兵器廃絶への共通したとりくみ(CTBTの批准・発効、カットオフ条約の締結、中東の非核・非大量破壊兵器地帯化、等)の強化を求め、その成立をめざさねばなりません。
NPT再検討会議は、2021年1月に開催すると伝えられていますが、新型コロナウイルスの感染症の状況如何にかかっています。NPT再検討会議の重要性を考えると、十分な日程を以て十分な議論が保障されなくてはなりません。新型コロナウイルス感染が終息した静謐な中での真摯な議論を望みます。原水禁は、核兵器廃絶を求める国内外の運動と連帯しながら、NPT再検討会議へのとりくみを検討していきます。
■米国トランプ政権の極めて危険な外交・核政策に反対を
米トランプ政権の「核態勢の見直し」(2018NPR)では、①核兵器を「核攻撃に対する抑止と反撃に限定せず、通常兵器への反撃にも使用する事を否定しない、②前記①のために新しい核兵器の開発を行う、③オバマ政権での「核なき世界」をめざす路線を転換し、核兵器の役割を拡大しその使用を可能とするとして、これまでのNPT再検討会議や様々な国際的な核廃絶へのとりくみを否定するものです。現実的に核兵器の使用を可能とする「小型核兵器の開発」と戦略原潜への配備、F‐35ステルス戦闘機等への精密誘導小型核爆弾の配備、原子力潜水艦や水上艦へ搭載可能な巡航核ミサイルの開発など核軍縮に逆行し、核兵器の使用条件も緩和し、核兵器以外の兵器での攻撃やサイバー攻撃をも核兵器使用の対象としています。さらに今年5月には、1992年以来行っていなかった爆発を伴う核実験の再開が、米政権内で議論されていることが報じられ、「かつてない核軍拡競争につながりかねない」と米国をはじめ世界の反核・平和団体から抗議の声が上がっています。
「力による平和の維持」「米国の影響力強化」を基本にした、米トランプ政権の外交政策は、オバマ政権の「核なき世界」への構想を放棄し、核兵器が「平和と安定を守るための基本」と、「核態勢の見直し」に位置づけられるように、極めて危険なものとなっています。
■米国にイラン核合意への復帰を求め危機的な状況を転換させ、中東和平へ
2018年5月、米トランプ政権は、「米国史上最悪のディール」と批判を繰り返しながら「イラン核合意」(イランの核開発制限と制裁の緩和:英米仏中露とイランで締結)から、一方的に離脱を宣言しました。英仏独は、米国の離脱に「遺憾と懸念」を表明しつつ、イランに対しては核合意の遵守を要請してきましたが、イランは段階的にウラン濃縮拡大をすすめてきました。国際原子力機関(IAEA)は、2020年3月3日、イランが所有する低濃縮ウランは約1トン、核合意で定めた上限の約5倍となったと報告しています。イランへの最大限の制裁をかけ続けてきた米トランプ政権は、今年10月18日に期限を迎える国連安保理によるイランへの武器禁輸の制裁延長を実現しようとしています。米国は、核合意に含まれる「紛争解決メカニズム(DRM)」を利用して、話し合いのステージを安保理に移し、最終的に「制裁解除」に拒否権を発動しようともくろんでいます。トランプ政権は、10月18日の制裁期限が大統領選挙と重なることで、世論へのアピールを狙っているとも考えられます。中国やロシアは、合意を離脱した米国にはDRM発動の権限はないとし、英仏独も、合意に反してウラン濃縮をすすめるイランに武器取引を認めることの懸念を抱きつつも制裁解除は予定されるとの見方も示しています。今秋までに、水面下における様々なやりとりが予想されます。イランは、協議が安保理の場に移れば、核拡散防止条約(NPT)からの離脱も辞さないとしており、朝鮮によるNPT脱退の再現も予想され、イランによる核兵器保有の可能性が生まれることとなります。一方で、イランへの接近を図る中国・ロシアは、国際的孤立の中で武器が老朽化しているイランへ、武器輸出の制裁解除後には新型武器の輸出をもくろんでいるとも考えられます。イランと米国との関係性の強い核保有国イスラエルや宗教問題をはらむサウジアラビアとの対立を考えるならば、中東情勢を一層複雑にしていくことが予想されます。そこには、米と中露の対立による「代理戦争」のような状況を引き起こすことも懸念されます。
2020年1月2日。米国はイラン領内において無人機を利用しイラン革命防衛隊の実力者ソレイマニ司令官を殺害しました。イランは、イラクの米軍基地に対してロケット攻撃を再三にわたって行い、2019年12月27日にはイラク北部のキルクーク近郊で、米国の民間人1人が死亡し、米軍兵士4人が負傷しました。このことへの報復がソレイマニ司令官の殺害であったと伝えられています。ロウハニ政権の報道官は、「米国は越えてはならない一線を越えた。イランは近い将来断固とした返答をする」と述べています。その後の、新型コロナウイルスのパンデミックによって、大きな動きは封じられていますが、今後の情勢は予断を許しません。複雑な中東情勢にあって、米国は「イラン核合意」に復帰するとともに、自国中心主義から離れて中東和平に尽力しなくてはなりません。
■米のINF全廃条約からの離脱に抗議し、欧州・東北アジアの非核化の実現へ
米露2国間での具体的な核戦力の全廃条約であったINF条約は、米国の離脱宣言によって2019年8月2日に失効しました。米国の離脱表明を受けたロシアは、「2年以内に地上発射型の新たなミサイルを開発する」ことを表明しています。米国は、INF条約失効直後の2019年8月18日、カルフォルニア州サンニコラス島において、地上発射型の中距離巡航ミサイルの発射実験を行いました。条約に反して中距離核を配備したとするロシアやアジアでの配備をすすめる中国を牽制する狙いを持つものであることは確実です。2020年2月4日、米国防総省は、爆発力を抑えた新型の小型核弾頭(W76-2)を搭載した潜水艦発射弾道ミサイル(SLBM)を実践配備したと発表しました。小型核は敵国の軍事基地などに対象を絞り限定攻撃する能力に優れ、従来型の核兵器よりも使用のハードルが低いとされています。しかも、攻撃される側から見れば小型核と従来型の区別はつかず、核攻撃と判断され、報復攻撃=熱核戦争を招きかねません。米国は、「潜在敵国」を念頭に置いた配備としていますが、搭載する潜水艦や配備地域に関しては言及していません。このような状況は、核軍拡をさらに進め、核戦争に現実に繋がる危険性を高める由々しき事態です。
ロシア・プーチン大統領は、2014年のクリミア併合時に核兵器使用の準備をしたと述べていますが、米国のNPRに通常兵器による攻撃に対する核使用の容認が盛り込まれたことなどを受けて、2020年6月2日、「核抑止力の国家政策指針」に署名し、通常兵器を使った侵略でも国家の存立が脅かされる場合には核使用の可能性があるとしました。5月22日に開幕した中国全国人民代表大会で公表された2020年度の国防予算は、前年比6.6%増の日本円にして約19兆円で、軍拡路線支持の状況が顕著となっています。米中露の軍拡競争路線が明確化する中で、いかに核軍縮をすすめていくかが問われています。
■米露は、「新START」を更新せよ
今年は核軍縮を核保有国に求めるNPT条約の発行から50年を迎えましたが、NPTをめぐる現状はきわめて重大な局面にあります。米露両国は、核軍拡の進展やキューバ危機などの情勢の中で話し合いをすすめ1972年には「戦略核兵器制限条約(SALT)」を締結し、両国の核戦力の制限を始めました。1979年の「SALT2」、1987年の「INF全廃条約」、1991年の「戦略核兵器削減条約(START)」と2国間での核兵器削減への歩みをすすめてきました。2010年には「新START」を締結して両国の核兵器を1550発に制限することと年間18回の相互査察を認め合っています。「INF全廃条約」が失効した中にあっては、2021年2月に更新期限を迎える「新START」が、米露間唯一の核兵器削減の条約となっています。米国は、これまでの米露2国間の枠組みを見直して、軍事力の強化が著しいとする中国を加えて3カ国による新たな条約制定が必要と訴えていますが、中国は全世界の核兵器の9割以上を占める米露の削減が優先されるとして、「いかなる3カ国間の軍縮交渉にも参加しない」としています。米国の主張の真意は不明ですが、場合によっては、NPT発効50年目にして米露間の核兵器削減への条約は消滅する状況になりかねません。2021年2月までには、米露両国は「新START」の更新を行い、更なる核兵器削減を行いつつNPT再検討会議における非核保有国の意見に耳を傾け、核なき世界へのアプローチに対する真摯な議論に参加すべきです。そのことが二大核保有国の責務と言えます。
■米朝首脳会談と朝鮮半島
2018年6月12日、シンガポールにおいて米国トランプ大統領と朝鮮民主主義人民共和国(以下朝鮮)金正恩国務委員会委員長との戦後初の両国首脳会談が開催され、朝鮮が朝鮮半島の完全な非核化に取り組むことなどを盛り込んだ共同声明に署名しました。その後、段階的な非核化へのプロセスによる制裁措置解除を求める朝鮮と米国の間では、2019年にベトナム・ハノイと板門店での2回の首脳会談が開催されましたが、両国関係に大きな進展はありませんでした。
本年5月24日、朝鮮中央通信は、朝鮮労働党中央軍事委員会で金正恩国家武力最高司令官(国務委員会委員長)が「核戦争抑止力の一層の強化」の方針を示したことを報じました。米国を念頭に、敵対勢力の持続する軍事的脅威を牽制できるよう、軍事的対策と政治的対策が話し合われ、「核戦争の抑止力を強化し、戦略兵器を運用するための新たな方針が示された」としています。米国のシンクタンク、「戦略国際問題研究所」(CSIS)は、5月29日、朝鮮の平山(ピョンサン)のウラン精製所が核実験停止後も稼働しているとの衛星写真の分析結果を発表しました。また、朝鮮東部の造船所において潜水艦発射型ミサイル(SLBM)搭載可能な新型潜水艦に関連する情報を確認したと、韓国の情報機関が明らかにしています。
非核化への米朝交渉が膠着状態にある中で、5月28日、米国司法省は朝鮮貿易銀行元幹部、海外支店関係者33人を、制裁措置を逃れた違法送金などで訴追したことを明らかにしています。
このような情勢の中で、米朝初の首脳会談から2年を経た2020年6月12日、朝鮮の李善権(リ・ソンゴン)外相談話を朝鮮中央通信が報じました。談話の中で李外相は「世界が注目する中で、2年前に膨れ上がった関係改善に対する希望は絶望に変わった」と述べました。加えて、「見返りもなく成果をあげるために利用されるような提案は2度としない」と発言し、さらに、アメリカの軍事的脅威に対処するために「より確実な力を育てる」としています。前述の「核戦争抑止力の一層の強化」の方針は、これらの状況を反映したものに違いありません。これまでの、実質的進展を伴うことのない自国第一主義の米国の外交姿勢が、米朝会談以前より大きな亀裂をつくったとすれば、米国の姿勢はアジアの平和に大きな脅威を残すものと言わざるを得ません。
一方で、南北朝鮮の両首脳、金正恩朝鮮国務委員会委員長と文在寅韓国大統領は、2018年4月27日、板門店において、歴史上3回目となる南北首脳会談に臨み、「南と北は、完全な非核化を通して、核のない朝鮮半島を実現するという共通の目標を確認した」と明記した、板門店宣言を発表しました。2018年9月には、開城工業地区内に双方の当局者が常駐する南北共同連絡事務所が開設されました。その後も18年中は、相互信頼の醸成のために南北対話、共同行事などが次々と実施され、南北鉄道連結に向けた現地調査も行われるなど、南北融和の方向性が示されていました。
しかし、米国からの圧力もあって南北関係も実質的進展が見られないまま、平壌での3回目の首脳会談(2018年9月)以降は膠着した状況が続いてきました。朝鮮中央通信が、2020年6月9日に、韓国の脱北者団体による朝鮮批判のビラ散布を理由に、南北当局間の全通信手段を同日正午(日本時間同)に完全に遮断することが決まったと報じると、6月16日には、朝鮮中央テレビが、同日14時50分ごろ、南北融和の象徴でもある開城の南北共同連絡事務所を「完全に破壊した」と伝えました。朝鮮は、韓国および米国との対話政策を転換する方向にあります。
今回の一連の報道は、2020年1月に就任した金与正党中央委員会第1副部長名によって行われました。金与正党第1副部長は、3月に朝鮮が行った火力演習に対する韓国の反応に「おじけづいた犬はさらに騒々しくほえる」という比喩を使ってきびしい非難を展開していました。これ以上の南北対立の激化は絶対に避けなくてはなりません。
■日本は朝鮮と関係改善し、東北アジアでの緊張緩和に役割を果たせ
日本政府は2006年から輸入や入港禁止などの制裁を発動し、制裁対象を広げながら措置を延長し、2019年4月には、朝鮮との輸出入の全面禁止や、朝鮮に寄港歴がある船舶を含むすべての船舶の入港禁止等を柱に、制裁措置の2年延長を決定しています。日本政府は、朝鮮の完全な非核化や日本人拉致問題の解決に向けた行動を引き出すために制裁を維持するとしていますが、そのことが解決に向かう手段であるとは考えられません。
2002年に小泉純一郎首相と金正日国防委員会委員長の間で「日朝平壌宣言」が取り交わされました。日朝国交正常化に向けた交渉開始、植民地支配の日本の謝罪と経済協力の実施などが明記され、日朝国交正常化に向けて動き出すかに見えました。しかし、小泉政権を継いだ安倍晋三首相の拉致三原則(拉致問題は日本の最重要課題、拉致問題の解決が国交正常化の前提、拉致被害者の全員帰国)を掲げる拉致問題解決に拘泥する姿勢によって、両国間の交渉は行き詰まりました。また一方で、国内においては、「高等学校等就学支援金制度」からの朝鮮高校排除、今回の幼保無償化からの朝鮮幼稚園排除、また新型コロナウイルス感染症対策の支援金などから朝鮮学園、大学校を排除するなど、在日コリアン社会への差別を行っています。日朝両国間の懸案事項は山積しており、その解決のためにも信頼関係の醸成と早期の国交正常化は急務と言えます。
■日本はプルトニウムの放棄と東北アジアの非核化へ進め
「日本が保有するプルトニウムは核弾頭1000発以上に相当し、安全保障と核拡散の観点から深刻なリスクを生んでいる」「日本の使用済み核燃料再処理工場(六ヶ所再処理工場)計画は、世界を安心させるのではなく事態を悪化させる行動だ」「核兵器を保有すべきだと日本の一部の政治勢力が主張し、核兵器開発を要求している。世界は日本を注意すべきだ」。これは、2015年10月に開催された国連第一委員会(軍縮委員会)での、中国の傅聡軍縮大使の発言です。中国による日本の原子力政策(核燃料サイクル計画)への批判は、福島原発事故ではなく、プルトニウム利用政策に向けられています。2016年6月、米国バイデン副大統領(当時)が、習近平中国国家主席に対して「日本は一夜で核兵器製造が可能」と発言したと伝えられました。自民党など保守勢力の中には、「原発推進とプルトニウム利用計画が、『核の潜在的抑止力』」であり「安全保障の面から、プルトニウム利用を継続し『潜在的核保有国』」であり続ける」との考え方が存在します。46トンと言われる日本のプルトニウム保有量は、長崎型原爆に換算して約5800発と考えられます。日本政府自らが、核兵器保有への途を確保しつつ、他国の核兵器開発を非難しても、核兵器廃絶の主張に説得力はありません。
プルトニウムを利用する「核燃料サイクル計画」は、六ヶ所再処理工場の24回にもわたる完工延期や高速増殖炉「もんじゅ」の廃炉、プルサーマル可能な原発の再稼働が福島原発事故以降進まず、MOX燃料価格が高く、英保管プルトニウムをMOX加工できない等で、プルサーマル自体も進まないことなどから将来の見通しが全く立っていません。多くの関係者が再処理の見直しを主張しています。国際的な非難を受けながら、「核燃料サイクル計画」をすすめる意味は全くありません。
原水禁は、この間核兵器廃絶のアプローチのひとつとして、米国と中国・ロシアの核兵器保有国に囲まれた日本と朝鮮半島の非核化を求める「東北アジア非核地帯構想」を掲げてきました。核兵器禁止条約が国連で採択され発効に向けた努力がなされる中、朝鮮半島の非核化を求めていくためには、日本の核保有への懸念材料であるプルトニウム政策(核燃料サイクル計画)を廃止し、「非核三原則」を法制化し、日朝および日朝韓における信頼醸成と平和への話し合いをすすめなくてはなりません。すでに中国は先制不使用宣言を行っており、米国・ロシアの不使用宣言とともに朝鮮半島の非核化をもって、被爆国日本の具体的政策として「東北アジアの非核地帯」に向けた努力が求められます。日朝国交正常化も、そのための一歩であると言えます。
■深化する日米同盟の下、日本の軍拡と中距離核配備を許すな
INF全廃条約失効後において、中国・ロシアを意識した中距離核配備について、米国から同盟国日本への協力を求める声もあがっています。中国やロシアの中距離核開発を理由にした日本への公然たる核配備の要求も、在日米海軍の戦略原子力潜水艦への小型核配備が現実化する中で、在日米海軍基地などへの半ば公然の核持ち込みも現実化する可能性があります。日本政府は、自国の安全保障の基本姿勢に米国の核抑止力を据えています。このような姿勢は、米トランプ政権の核態勢の見直しなどから見て、被爆国の国是である非核三原則を揺るがしかねない情勢を呼び込むものできわめて問題と考えます。日本政府に非核三原則の法制化を行なわせなければなりません。
日本政府はこの間、朝鮮の核実験やミサイル発射実験などを理由に、米国とともにミサイルディフェンス(MD)による防衛システムの構築をめざしてきました。青森県車力と京都府経ヶ岬に設置された米軍のXバンドレーダー基地、韓国慶尚北道星州(ソンジュ)に配備された終末高高度ミサイル防衛ミサイル(THAAD)とともに、米軍による一体的運用が行われつつあります。5兆円を上回る防衛予算は、安倍内閣の下で毎年過去最大を更新し、米国からの要求を丸呑みする対外有償援助(FMS)によって、様々な防衛装備を購入してきました。F-35Aステルス戦闘機の購入、ヘリコプター搭載護衛艦(DDH)のいずも・かがの空母化とF-35B(ストーブル機)の配備、MV-22オスプレイ、無人偵察機(RQ-1 プレデター)、F-35A搭載用の長距離巡航ミサイル、地上配備型イージスシステム(イージス・アショア)導入など、これまでの専守防衛をこえて安全保障関連法に基づいての、米軍と一体になった世界展開がもくろまれてきました。日本の自衛隊が、米軍の指揮下で軍事展開する「日米統合軍」構想が現実化しています。
地政学的な日本の立場を考え、米国との軍事的・政治的協力ではなく、日本を含む東北アジアの平和と安定をめざす外交政策を追求していくことが、この地域の国々との協調に基づく繁栄につながるものであり、米軍との軍事一体化の現状は、そのような外交を阻害する要因にしかなりません。日米を中心とした「自由で開かれたインド太平洋構想」は、中国が推し進める巨大経済圏構想である「一帯一路構想」と対立するものであり、これら日米のあり方、言い換えれば米国追従の日本のあり方は、アジアの平和と安定を阻害する要因のひとつとなっています。
2020年6月15日、防衛省は、イージス・アショアの秋田、山口両県への配備計画を、システム改修にコストと期間がかかるとして停止すると発表しました。19日には、政府が配備計画を撤回する方針を固め、国家安全保障会議(NSC)の議論を経て、イージス・アショアに代わるミサイル防衛(MD)などについて議論したうえで、今年末を目途に防衛計画の大綱(防衛大綱)、中期防衛力整備計画(中期防)を見直して正式決定するとしています。原水禁は、秋田・山口両県の平和センターや市民の方々と、イージス・アショア配備阻止にとりくんできました。配備撤回の決定を運動の成果として歓迎します。一方で、MDの見直しが先制攻撃を容認する「敵基地攻撃能力」の保有と充実に繋げることは絶対に許してはならないと考えます。米国は、防衛政策の基本に「統合防空ミサイル防衛(IAMD)」構想を据えています。これは単に迎撃ミサイルによる「防衛」に頼るのではなく、早期警戒機や戦闘機(巡航ミサイル搭載可能なF-35A)など全ての兵器を連携させ、敵基地攻撃も含む「防衛構想」であり、平和憲法の下での「専守防衛」というこれまでの日本の「防衛構想」の基本を覆すものであり、イージス・アショア配備より一層問題の大きなものです。「日米同盟の深化」を基本に、朝鮮半島や中国・ロシアとの対立をはらむ日本政府の外交・軍事政策は、日本の国民を危険にさらすだけでなく、東北アジア及び世界の平和を脅かすものです。私たちはこのような日本政府の国家安全保障戦略を許してはなりません。
■辺野古基地建設の撤回を
沖縄防衛局は、6月12日から辺野古新基地建設工事再開しました。それに伴い、沖縄平和運動センターが参加する「オール沖縄会議」は、コロナ感染防止に配慮しながら、ゲート前の座り込み行動を再開しました。原水禁は、沖縄の仲間とともに、辺野古基地建設の撤回を求めて闘います。復帰48年を迎えた今年の5月15日、沖縄平和センターは「平和センターが参加をしている広島、長崎を原点とした原水禁国民会議は、かねてより東北アジアの非核化地帯構想及び非核法の制定を提唱しています。かつて核の島とも言われたこの沖縄からその運動を大きくつくっていくことを誓います」と「平和アピール」を発しています。「私たちが復帰にめざしたものは、平和憲法下への復帰でした。そこには、基本的人権、国民主権、地方自治、なによりも軍備と戦争放棄が謳われています。今その憲法は、集団的自衛権の行使容認、安保法制、共謀罪など切り裂かれてきました。それでもまだ憲法は生きています。『政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないよう』に、沖縄から為政者に守らせなければなりません」沖縄本島の15%を占め全国の70%を超える在日米軍基地を抱える沖縄の言葉をしっかりと受け止めなくてはなりません。
河野太郎防衛大臣は、6月15日、防衛省内で記者会見し、陸上配備型迎撃ミサイルシステム(イージス・アショア)を秋田県と山口県へ配備する計画を停止すると発表しました。停止の理由は「安全性を確保するためのハードウエア改修に2,200億円前後のコストと12年前後の時間がかかる」というものです。沖縄の辺野古新基地建設では、日本政府は、「米軍普天間飛行場のリスク軽減」の唯一の選択肢としていますが、軟弱地盤補強のため「辺野古移設の実現には9,300億円の工費と12年の工期が必要」との見通しを明らかにしています。県の試算では、工費2兆5,500億円工期は13年とされています。玉城沖縄県知事が主張している通り、「陸上イージスと同様に相当なコストと期間を要する辺野古移設は断念すべき」です。
中国の中距離ミサイル配備と米軍のアジア・ローテーション配備計画の下では、米軍にとっての沖縄米軍基地の位置づけは従来とは大きく異なってきており、中国のミサイル射程範囲に入る第一列島線に位置する沖縄に恒常的な米軍基地が常駐する意義はむしろ薄れてきていると考えられます。
■自国第一主義を許さず、人々の命と平和を守るグローバルな連帯を進めよう
新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大は、世界に深刻な影響を与えています。国と国の行き来は断絶され、ウイルスの発生源やWHOの対応をめぐっての国家間の対立、特に米国と中国の対立が深刻化しています。2020年3月24日、グテーレス国連事務総長は、「私たちの世界はCOVID-19という、共通の敵と対峙しています。このウイルスには、国籍も民族性も、党派も宗派も関係ありません。すべての人を容赦なく攻撃します。その一方で、全世界では激しい紛争が続いています。女性と子ども、障害をもつ人々、社会から隔絶された人々、避難民など、最も脆弱な立場に置かれた人々が、最も大きな犠牲を払っています」と述べて、ウイルスに対応するために「グローバルな即時停戦」を呼びかけました。また、中満泉国連軍縮担当上級代表も、2020NPT再検討会議をはじめ様々な軍縮に関する会議や議論が延期を余儀なくされる状況の中でも、国連は核兵器(CTBTのプロセスから、中東の非核兵器・非大量破壊兵器地帯の設立のための会議もふくめて)のみならず、化学、生物、毒物兵器、通常兵器、等々の軍縮の課題に取り組み続けるという決意を述べ、COVID19による危機に「ともに連帯して立ち向かうことで、最高の共通目標を達成するために、私たちは分断を乗り越えられることが理解されるよう心から願っている。共通目標は、健康な生活を保障すること、地球上のすべての人々の幸福を増進し、全ての人々の平和で安全な世界を確立するよう努力すること」呼びかけています。
2020NPT再検討会議参加を予定していた世界のNGOは5月11日、NPT無期限延長25年を期に「共同声明」を発し、「敵意に満ちた政治論議を越えて、核兵器の終焉をもたらすために努力を集中する、かつてない好機」「軍縮のさらなる発展のために、責任ある国々が力を合わせ、そして核戦争の悪から人類を救うために、新たな、より広範なリーダーシップを発揮することが求められている。」と呼びかけました(この声明には原水禁も賛同しています)。そして、世界の多くの反核平和、人権擁護団体が、COVID19パンデミックによって、世界中で多くの人々、特に貧困にあえぎ、医療等の保証のない人々の命が脅かされている中で、核兵器をはじめとする軍備に投入されている巨額の軍事費を、人々の命と健康、生活を守るための資金に費やすように強く求めています。
原水禁は、グローバルな視点で、人々の命、それを保証する平和を守る世界の多くの人々との連帯と団結が、核廃絶を導き出すための基本にあると考えます。「コロナ禍後の社会」は、決してこれまでの社会ではあり得ません。また、私たちはコロナ禍への対応の中で、新たな社会のための様々な課題を受け止めることとなりました。コロナ禍も、原水爆も、ひとり一人の「命」の存在に係わる課題として捉えながら、その尊厳を守るとりくみを強めながら、ポストコロナ社会を提起していかなくてはなりません。
(2)核の商業利用(原子力エネルギー)の現状と運動の課題
■福島第一原発事故の現状と課題
東日本大震災・福島第一原発事故から9年5ヵ月が過ぎ、来年3月には10年を経過しようとしています。しかし廃炉作業は、圧力容器周辺では毎時12~42シーベルト、2号機5階の床面でも最大毎時630ミリシーベルト、原子炉建屋から100メートル離れた地点でさえ空間放射線量が毎時120マイクロシーベルト(8時間程度で一般公衆の年間追加被曝線量の限度を超える)をこえるような高い放射線量に阻まれ、遅々として進んでいません。溶融した核燃料(燃料デブリ)は、その全容をいまだ確認することができず、当初2031年から2036年とされていた燃料デブリの取り出し完了時期は、廃炉作業の行程表が改訂される中で記載が消えてしまいました。燃料デブリの取り出し開始を2021年、廃炉完了時期を2041年から2051年とする記載は当初から変更されていませんが、1から3号機の使用済み燃料プールからの燃料取り出しが、1573体中91体(3号機分)に止まり、完了予定を10年延長しています。建屋上部に大量の瓦礫が散乱しその撤去もままならず、1号機は建屋上部の覆いも完成せず、がれきの撤去も手つかずの状況です。プールからの燃料取り出しが予定通り完了するとしても、それだけで廃炉完了予定までの半分を使い切ることになり、廃炉が予定通り進むとは考えられません。
困難極まる燃料デブリの取り出しも含めて、福島第一原発の廃炉作業に従事する労働者の被曝は放射線防護の法令を遵守し、できるだけ低く抑えなければなりませんし、汚染された福島県やその他の地域を再び汚染することは絶対に許されません。東京電力と国は、福島事故を起こした自身の責任を認め、集団ADR拒否など不誠実な損害賠償対応と凍土遮水壁など廃炉・汚染水対策の破綻を深く反省し、損害賠償・廃炉対策費約22兆円の電力消費者への転嫁を撤回し、東京電力自らの破産処理を含めて、その責任をとるべきです。これらを前提として初めて廃炉・汚染水対策の抜本的転換が可能になるのであり、その上で、超長期的に安全を確保する途を福島県・県民、地元自治体、そして国民とともに模索すべきです。
■膨大な事故収束費用と場当たり的な政府対応
福島第一原子力発電所の廃炉費用は、東京電力の廃炉計画から試算したもので現在約8兆円と予想されています。それに賠償費約8兆円、除染費および除染で生じた土壌などの中間貯蔵費約6兆円(予想)を加えると、現段階においても22兆円という莫大な費用が見積もられます。しかし、これはあくまで「試算」であり、原水禁は、今後の廃炉作業の推移次第では、莫大な費用負担が私たちに求められると考えてきました。公益社団法人日本経済研究センターは、2019年3月の報告で廃炉費用の総計を81兆円と試算する一方、今後の増加分も含めた汚染水200万トンを薄めて海洋投棄すれば40兆円削減できるとしました。これは、検討されてきたタンク貯蔵の拡充やコンクリート固化などの安価な貯蔵方法を無視し、非現実的で高額な方法だけを取り出して、海洋投棄すれば40兆円もの削減につながるとする作為的で悪質な論考です。そのような作為を以て「40兆円の国民負担か、汚染水の海洋投棄か」の二者択一を福島県民と国民に迫ることは許されません。
今、何よりも大切なことは、福島事故を直視して、事故の原因究明と責任の所在を明らかにするとともに、福島県民への放射線被曝防護の徹底と、無料の健診や医療を保障する「健康手帳」交付によって将来的な健康保障をはかり、これ以上の放射能災害を防ぐための徹底した事故処理対策を講じることです。加えて、安易な放射性物質の環境への故意の放出は絶対に許してはなりません。
2020年度より、原発依存度の低減というエネルギー政策の基本方針の下、原子力事業者が相互扶助で負担すべき損害賠償費の一般負担金「過去分」2.4兆円や原子力発電所を円滑に廃炉するための費用として、原子力事業者が経済産業大臣の承認を受けた額を電気料金(託送料金)の一部として、原子力事業者以外の新電力契約者を含めた全電力消費者から徴収すること(改訂法令施行)となっています。国や電力会社が責任を明確にせず、その責任をとらないまま、このような方法で一般電力消費者に責任転嫁するのは大問題であり、撤回させなくてはなりません。
また、2020年の通常国会において、政府は「復興庁設置法改正案」など計5本の「束ね法案」のひとつとして、「エネルギー対策特別会計の改正案」を提出しました。これは、特別会計内の使途の異なる勘定間の資金のやりくりを一時的に可能として、再生可能エネルギーの普及などに使途を限定する「エネルギー需給勘定」の資金から、「原子力災害からの福島の復興に関する施策」について、原発振興や福島原発事故処理を目的とする「電源開発促進勘定」(電促勘定)に繰り入れられるようにするもので、東京電力福島第一原発の汚染土中間貯蔵施設費の一部または全部を再生可能エネルギー普及に使う財布からまかなうことを意味するものです。この中間貯蔵費1.6兆円は電促勘定から東電へ一旦交付されるものの、30年の中間貯蔵事業終了後に東電へ全額求償する(返済させる)ことになっています。しかし、閣議決定(2016年12月20日)だけで、法的に制度化されておらず、完全に返済できる保証はありません。同法案は、5月22日衆議院本会議、6月5日に参議院本会議で可決成立しています。このような法案提出の手法は、問題となった「検察庁法改正案」が「国家公務員法等の一部を改正する法律案」と束ねられていたことと同様に、通しやすい法案と束ねることで追及を避ける「禁じ手」にほかならずきわめて問題です。
損害賠償費一般負担金「過去分」の託送料金による徴収、除染費の交付国債による代替交付、中間貯蔵費のエネルギー特別会計による代替交付、廃炉費積立金の東電管内託送料金高止まりによる確保などは、東電を破産させないための無理な施策であり、結局は電力消費者や国民の転嫁されるのです。破産処理を含め、東電に責任をとらせて、抜本的見直しを含めて国の責任で廃炉・汚染水対策をすすめる必要があるのではないでしょうか。
■貯まる汚染水、海洋放出を許すな
オリンピック誘致に際して、安倍首相は、「汚染水の影響は港湾内で完全にブロックされ、アンダーコントロールの下にある」と発言しました。現在、3基の溶融燃料デブリの冷却に約200トンが注入され、これに「建屋への地下水・雨水流入量」と「高濃度地下水ドレン等の建屋への移送量」の50~250トンが雨量に依存して加わり、計250~450トンの高濃度汚染水が毎日発生しています。これをセシウム・ストロンチウム除去して「淡水」と「濃縮塩水」の半々に分離し、「淡水」は冷却用に再利用され、「濃縮塩水」は多核種除去装置(ALPS)で処理され、貯蔵タンクにためられます。その量は120万トンを超えて、サイト内のタンクに貯蔵されています。タンクは現在1000基を超えています。当初ALPSによってトリチウム以外の放射性物質は除去できるとされていましたが、サイト内のタンクで保管されている汚染水120万トンには、ALPSでは除去できないトリチウム860兆ベクレルはもちろんのこと、満水になったタンクの75万トンに国の基準(告示濃度限度)を超える高濃度で放射性物質が含まれていることが明らかになっています。うち、6.5万トンには基準の100~2万倍のストロンチウム90、ヨウ素129、ルテニウム106などが含まれています。国や東電は「ALPSでトリチウム以外の放射性物質は除去できる」「トリチウムは生物への影響が小さく、国内外の原発でも海洋放出している」として、海洋か大気中への放出と提案しています。しかし、海洋や大気中への放出は明らかな環境汚染であり「風評被害」や「健康被害」を拡大するなどの懸念があります。トリチウム以外の核種を二次処理で除去したとしても、トリチウム汚染水120万トン、860兆ベクレルを(平均500倍に薄めて1,500ベクレル/リットルとして)海洋放出するのは、何よりも、東電・政府が福島県民や国民に約束したことに違反しています。
第1に、汚染水を減らすために地下水バイパスやサブドレンの排水を福島県民、とりわけ漁民が苦渋の選択で容認した際、東電と政府は、その運用方針で「運用基準を超えれば排水せず、希釈放出もしない」、「ALPS処理水は海洋放出しない」と約束しています。トリチウム汚染水(ALPS処理水)の希釈・海洋放出は、この約束に違反します。
第2に、福島県民等には事故時に甚大な放射能被爆を強要され、今なお年1ミリシーベルトを超える地域での生活を余儀なくされている人々がたくさんいます。さらに、トリチウム汚染水の海洋放出で、新たな被曝を強要することは許されません。国内法には「年間1~20ミリシーベルトの現存被曝状況」を認める法律など存在せず、法令で担保された年1ミリシーベルトを超える被曝を強要することは法令違反です。
第3に、1993年のロシアの放射性廃液の日本海投棄に際して、原子力委員会が「我が国としては,今後,低レベル放射性廃棄物の処分の方針として、海洋投棄は選択肢としないものとする」とした決定に違反します。
第4に、日本の加盟するロンドン条約及びIAEA(国際原子力機関)の基準(セーフティ・シリーズ NO.78)によれば、高レベル放射性廃棄物の海洋投棄は全面禁止、低レベル放射性廃棄物についても、液体状の容器に封入されていない海洋投棄は禁止されています。実行可能なあらゆる措置で海洋汚染防止を図ると誓約している日本はこれに従う義務があります。
外務省や原子力委員会は、トリチウム汚染水120万トン、860兆ベクレルを海洋投棄することはロンドン条約で禁止されていると認めています。現に、実例のある陸上での固化埋設やタンク貯蔵など実用的な選択肢をまじめに検討すべきです。
「原発のない福島を!県民大集会」実行委員会が、福島県民の総意を結集して4月15日から始めた反対署名は、現在10万筆を超えています。トリチウム汚染水の海洋放出への意見書の採択が福島県内19市町村議会で相次いでいます。13決議は海洋放出に反対し長期陸上保管を求め、2決議は長期陸上保管の検討も含める、もしくは、合意が得られるまで陸上保管継続を求める内容で、いずれも海洋放出に懸念を表明しています。6月23日には全国漁業協同組合連合会が「海洋放出に断固反対する」との特別決議を全会一致で採択しています。福島県漁連も6月26日、「海洋放出に断固反対する」特別決議を全会一致で採択し、福島県の森林組合連合会や農業協同組合中央会等も海洋放出に強く反対しています。福島県外でも、茨城県知事が今年1月末以降、「海洋放出を安易に結論とする報告は容認できない」との立場を鮮明にし、茨城沿海地区漁業協同組合連合会も2月13日に「海洋放出、絶対反対」の要請書を茨城県知事へ提出、茨城県知事は政府に反対を働きかけると表明しています。宮城県漁協も6月15日、村井宮城県知事に海洋放出しないよう国へ求めることを促す要望書を提出し、同知事は「県民の代表として、こうした声を伝えていくことは重要だ」と応じています。
このような状況を考えると、被害の拡大を防ぎ、放射能量の自然減少にもつなげるため、用地を確保してのタンクでの保管継続が望まれます。トリチウム汚染水の海洋放出ありきの議論を認めるわけにはいきません。トリチウムの健康への影響も懸念されるなかで、汚染水の海洋投棄でさらに被曝を強要することなど断じて許せません。トリチウム汚染水の海洋放出反対の署名を拡大し、何としても海洋放出を断念させなくてはなりません。
■廃炉・除染に伴って、さらなる汚染拡大・拡散を許すな
汚染水以外にも、汚染水処理による廃吸着塔や沈殿した放射性物質を含む泥状の「スラッジ」「スラリー」と呼ばれるものなど様々な高レベル放射性物質が発生します。これらはHICと呼ばれる高性能容器に保管されますが、確保された保管場所の8割以上が埋まっています。放射性物質に汚染された瓦礫、使用済み防護服、伐採木などもあり、焼却・減容すれば高濃度の焼却灰が発生します。これらの処理問題も大きな課題となっています。
汚染地域の除染によって出た汚染土は、環境省によれば、福島県では約1,400万立方メートルで、政府は2020年度までに全てを事故原発周辺の中間貯蔵施設に運び出すとしていましたが、搬入開始から5年目を迎えた2020年2月現在で搬入済みは615万立方メートルで、全体の約44%に留まっています。生活環境にまだ残されている除染廃棄物は、容器(フレコンバック)の劣化が進み、環境の再汚染も懸念されています。
2019年10月に福島県を襲った台風19号によって、福島第一原発事故の放射性物質によって高濃度に汚染された山林の土砂が崩壊して道路に流れ出ていることが確認されています。1㎏あたり最大1万1000㏃で放射性廃棄物の基準(8000㏃)を超えていると報告されています。また、フレコンバックに入れて福島県内の仮置き場に山積みされている除染土(1袋1立方メートル)が田村市、二本松市、川内村、飯舘村で合わせて50袋以上が付近の川に流出したことも確認されています。
2016年6月30日に、環境省は「再生資材化した除去土壌の安全な利用に係る考え方について」を決定し、汚染土の放射能濃度が8,000Bq/kg未満なら道路や鉄道の路盤材や防潮堤、海岸防災林、土壌造成・水面埋立などの盛土材として、汚染土を私たちの生活環境へ戻しています。このような汚染土再利用は、現行法のクリアランスレベル(セシウム137で100Bq/kg)にも違反します。事故によって汚染と被ばくを強いられた上に、さらに放射能汚染を拡散する「除染土再利用」に対しては、住民からも反対の声が上がっています。福島県二本松市では、除染土を農道の路底材に使用する実証実験の計画が、地域住民の反対で、2018年6月に白紙撤回されました。その後、環境省は飯舘村長泥地区などで行った実証実験では「これまでのところ安全性に問題はない」として、「放射性物質汚染対処特別措置法」を改定し、2020年4月から本格的に除染土の再利用に踏み出そうとしましたが、1月~2月に行われた同法改定のパブリックコメントでは、1ヶ月で2854件の意見が寄せられ、そのほとんどが反対意見だったことを受けて、今回の改定を見送らざるをえませんでした。
原発核燃料サイクルは、たとえ事故を起こさなくても放射性廃棄物を排出し続けます。そして、一度、原発重大事故が起これば、大量に放出された放射性物質が長期にわたって、人々の住環境を放射能で脅かし続けることを福島の現実が示しています。事故被災地で、これ以上の汚染の拡大と人々への被ばくの強要を許してはなりません。
■続く避難生活、事故によって奪われた命
原発事故から、9年半が経過しようとしている今なお、福島県では県内7602人、県外に3万211人、避難先不明者も含めて合計3万7826人(2020年4月9日復興庁調査に基づく、6月5日現在の被害状況即報[福島県災害対策本部発表])が、長期の避難生活を余儀なくされています。政府は2017年3月末で「自主避難者」への避難先住宅無償提供が終了すると、避難者数から自主避難者を除外しました。また、公表されている統計には、避難指示が出されている地域の住民でも、避難先で自宅を購入した人や、県などの住宅支援を受けずに東京電力から家賃の賠償を受けて賃貸住宅で暮らす人などは含まれていません。福島県・復興庁の調査には十分に避難の実態が反映されていません。
2020年6月5日の被害状況即報では、福島県内の震災関連死と認定された人の数は2307人で前年度より35人増えています。約9割が66歳以上の高齢者で、福島県の震災関連死は東日本大震災全体の関連死の約6割を占めています。この数字は、福島県では自然災害である東日本大震災に加えて、人災である東電福島第一原発事故の影響が大きく、放射能汚染によってふるさとや生業を剥奪され長期にわたる避難生活を強いられる中で、健康の悪化や将来への不安など精神的にも追い詰められる被害者の状況を反映しています。原発事故によって多くの命が奪われてきたのです。
■無理な避難指示解除と進まない帰還
一方、政府は、除染が進んだとして帰還困難区域を除いて避難指示を相次いで解除しました。避難指示解除の条件としては「①年間積算空間線量が20mSv以下②日常生活に必要なインフラや医療・介護などの生活関連サービスの復興、子どもの生活環境の除染の進捗③県、市町村、住民との十分な協議」(2015年6月、原子力対策本部決定・閣議決定)としてきました。この「年20mSv」の被ばくは、国の被ばく防護の法令で担保されている「一般公衆の年間被ばく限度1mSv」の20倍にも相当する被ばく量です。政府は、フクシマ事故直後から国際放射線防護委員会(ICRP)が勧告した重大事故時の「被ばく基準」(参考レベル)に従って、事故後の対策を行ってきました。このICRP勧告(2007年勧告)は、重大事故が起こっても人々に被ばくを押しつけながら原発を推進し続けられるように、チェルノブイリ事故後に出された「二重基準」(重大事故による被ばくに対しては、大幅に緩和した被ばく基準「参考レベル」を適用するというダブル・スタンダード)です。日本政府は、フクシマ事故後なし崩し的にこの「二重基準」を政策に取り入れ、事故直後の学校の校庭除染や避難の基準に「年20mSv」を適用しました。そして2015年以降は「避難解除の基準」としても「国際基準だ」と強弁して用いているのです。このように重大事故が起こっても原発推進を続け、人々に被ばくを押しつける政策を許してはなりません。法令で担保されている「一般公衆の年間被ばく限度1mSv」を超える被ばくを、事故によって人々に強いてきたことは「法令違反」であり、人々を被ばくの健康リスクに曝す人権侵害です。
2020年3月4日と5日には、事故を起こした福島第一原発が立地する双葉町と大熊町の一部地域で避難指示が解除されました。全線再開するJR.常磐線の開通(3月14日)に合わせたもので、帰還困難区域ではあるが、除染によって「人が住める」ようにしようとしている「特定復興再生拠点区域」の一部とされます。政府は、限定的な除染をすすめ2022年には双葉町に「特定復興再生拠点区域」として住民の帰還を実現させようとしています。しかし、復興庁の行った住民意向調査では、「帰還したい」が1割で、「帰還しない」は6割を占めています。
一方で、政府は「地元(飯舘村)の強い意向」を口実に、将来的に人が住まないことなど一定の条件を持つ地域を除染せずに避難指示解除し、人々の立入り制限をなくす方向で検討に入っています。「放射性物質汚染対処特措法」は、除染を国の責務としていますが、避難指示解除要件を見直し除染しなくても良いという例外を設けるものできわめて問題です。高汚染地域への住民等の自由な立ち入りは、人々の被ばくの機会を増やします。このような動きに対して、帰還困難区域を抱える大熊、浪江、双葉など周辺自治体の首長からは「国は約束通り除染を」と、反発の声が上がっています。
■国と東電は責任を取れ~それぞれの選択へ、様々な支援を国の責任で行え
避難指示解除に合わせて、帰還を強要するかのように住宅支援、精神的賠償などの支援策が次々に打ち切られています。避難指示解除区域では、医療や介護、日常生活に必要な各種インフラやサービスは全く不十分なままです。これまでに一部または全域で避難指示が解除された10の市町村(3月4日に解除された双葉町を除く)では、避難指示が解除された地域に住民票を登録している4万6529人(2020年2月1日現在)のうち、実際に住んでいる人は最大で1万3248人で、帰還率は28.5%に留まっています。2014年4月先んじて解除された田村市では84%の帰還率ですが、2016年までに解除された川内村、楢葉町、南相馬市などにおいては50%前後に留まっています。朝日新聞と地方自治総合研究所(今井照:主任研究員)が福島県の避難者を対象に行った共同調査で、自らの気持ちを「頑張ろうと思う」と答えた人が35%、「気力を失っている」23%、「仕方ないと思う」20%、「怒りが収まらない」15%となっています。きびしい現実と向き合う福島県民の心情を象徴しています。
避難の長期化は、生活基盤の移転をもたらし、若い世代ほど帰還を断念する割合が高いと言えます。帰還先での生業の確保が困難な上に、何よりも子どもたちの被ばくへの不安により帰還を断念し、避難先での生活を選択する人々が多いのが現実です。帰還しても事故前と同じようなコミュニティの再建は事実上不可能な現状で、事故によって、多くの人々の人生が変貌してしまいました。
原水禁は、事故の当初から、一般公衆の被ばく限度年1ミリシーベルトの遵守を基本に避難者支援と除染の実施を求め、被害者それぞれの選択に対応する支援の確立を要求してきました。子どもたちを避難させる、家族で避難する、県外での生活を選択する、県内の生活に戻る、それぞれ様々な選択が在り、様々な選択が成立するよう支援するのが、国の役割であることは明らかです。国の施策として原発の建設・運転が進められ、そこで取り返しのつかない事故を起こした責任を、国がはっきり認め、責任ある施策をとるべきです。健康と生活を守るための放射線防護や健康管理、生活支援を、国の責任の下でしっかりと行うことが基本です。「福島原発子ども被災者支援法」の第2条2項には「被災者一人一人が第八条第一項の支援対象地域における居住、他の地域への移動及び移動前の地域への帰還についての選択を自らの意思によって行うことができるよう、被災者がそのいずれを選択した場合であっても適切に支援するものでなければならない」と記載されています。安倍政権が進めている原発事故被害者への帰還の押しつけと支援策の切り捨ては、この考え方を根底から否定するものです。
一般公衆の被ばく限度の20倍もの「年20mSv」基準で、政府が線引きした避難指示区域外からの自主避難者は、2017年3月の住宅無償提供の終了以降、国や福島県からは全く支援されず、住宅を追い立てられた多くの家庭が生活困難に陥っています。このような状況で、山形県などでは、提供住宅に住み続けたいと願う自主避難者に、住宅の明け渡しを求めて住宅を管理する独立行政法人が裁判に訴えるということも起こりました。国や県のこのような姿勢は、避難者に対して「勝手に逃げた」「風評被害を広める」などの誹謗中傷をもたらすこととなっています。避難するかしないかなどの、それぞれの選択を認めない姿勢が、被害者の間に分断と差別をつくり出しています。国は、原発事故を起こした上に、このような被害者の苦況をつくり出してきたことの責任を取るべきです。
このように安倍政権は、東京オリンピックに向けて「復興」をアピールし、福島原発事故の早期幕引きと被害の矮小化を図り、被害者を切り捨てようとする「棄民」政策をすすめています。多くの人々が、物言えず苦しんでいる状況があります。私たちは、国と東電の責任をきびしく問い、事故被害者の健康と命、生活を守るための施策を求めて運動を強めなければなりません。
■子どもをはじめ、事故被害者の健康と命、生活を守れ
福島県は「県民健康調査」において、福島原発事故当時、概ね18歳以下であった子どもたちに甲状腺(超音波)検査を実施してきました。県民健康調査における甲状腺検査状況は、2020年 3月末現在、2019年3月末より23人 増えて241人が甲状腺がんまたはがんの疑いとされ、196人が手術を受け(うち一人は、術後良性腫瘍と診断)ています。原発事故によって放射性ヨウ素が放出され、福島県をはじめ広範囲の住民が放射性プルームの正確な情報も知らされずに甲状腺被ばくし、甲状腺がんを始めとする健康リスクに曝されました。事故がなければ約30万人もの福島県の子どもたちがこのような甲状腺検査を受ける必要はありませんでした。このような状況をふまえ、国は事故を起こし人々を被ばくさせた責任を認め、少なくとも「県民健康調査」で甲状腺がん・疑いと診断された全ての人々について、「事故による健康被害者」として認め、生涯にわたる医療支援、精神的ケア、生活・経済支援等を行うべきです。
2019年6月3日、専門家で構成する「福島県県民健康調査検討委員会甲状腺検査評価部会」は、「先行検査における甲状腺がん発見率は、わが国の地域がん登録で把握されている甲状腺がんの罹患統計などから推計される有病率に比べて、数十倍高かった。本格検査(検査 2回目)における甲状腺がん発見率は、先行検査よりもやや低いものの、依然として数十倍高かった」としながら、その原因に言及することなく、個人の甲状腺被曝量調査・推計も行わず、国連科学委員会(UNSCEAR)で公表された推計甲状腺吸収線量を用いて、線量と甲状腺がん発見率に明らかな関連はみられなかったとし、「現時点において、甲状腺検査本格検査(検査2回目)で発見された甲状腺がんと放射線被ばくの間の関連は認められない」と結論づけています。専門家による安易な評価は、マスメディアを通じてあたかも断定的な結論であるかのように喧伝されています。甲状腺検査評価部会は、他方で「今後の評価の視点について」のなかで「将来的には、より詳細な推定甲状腺被ばく線量を用いて、交絡因子等を調整した症例対照研究や前向き研究として、線量と甲状腺罹患率との関連を検討する必要がある」としています。ならば、現時点では、「甲状腺がんと放射線被ばくの間の関連は認められない」と結論づけることには、大きな問題があると言わざるを得ません。
2015年7月から福島県で「19歳以上の甲状腺医療費支援」(甲状腺調査サポート事業)が始まりました。2020年5月25日に開催された「県民健康調査検討委員会」の第38回会合における報告によると、2015年の事業開始から2020年3月末までの5年間に医療費の交付を受けたのは実人数314人のべ499件で、昨年公表時(2019年4月8日)より実人数は57人増えています。また、手術費用の交付を受けた人も25人増加。5年間では118人となり、うち4人が再手術費用の交付を受けています。甲状腺調査サポート事業は福島県と全国の運動が繋がって実現させた、事故後初めての国による被害者への「医療支援」です。さらに「診療情報提供」を支援の条件としないこと(「診療情報提供」を条件としているにもかかわらず、今のところ、県は収集した「情報」の集計や解析すら行っていません)、手続きの簡素化、償還払いでなく現物給付にすること(窓口での支払を不要にする)、生涯にわたる支援の継続、甲状腺検査に関する「健康手帳」の交付など、施策の改善を国と県に対して求める取り組みが続けられています。人々の要望を受けて、福島県は昨年末にサポート事業の対象となる医療機関の拡大を決めました。しかし、その他の改善要望ついては未だに「関係機関と調整中」として実現を怠っています。私たちは、これまでの運動の成果と力を、さらに充実した支援の早期実現につないでいかなければなりません。
■事故10年を前に~支援打ち切りを許さず、事故被害者の人権守り、国の責任での生涯にわたる健康・生活の保障を求めよう
東日本大震災・福島原発事故から来年で10年を迎えます。政府は「復興・創生期間」は10年を以て終了するとし、2019年12月20日に「『復興・創生期間』後における東日本大震災からの復興の基本方針」(「基本方針」)を閣議決定し、施策を進めるため「復興庁設置等の一部を改正する法律」が2020年6月に成立しました。「基本方針」は、震災・事故後の「復興」政策を総括し、10年以降の施策の方向性を示したものです。しかし本来なら総括の大前提となるべき、国策で進めた原発の重大事故によって多大な被害を招いたことへの責任と反省は、一切述べられていません。そして、事故収束、環境再生、帰還、産業の再建、等が、事故後「国が前面に立って」「着実に進んでいる」かのように記され、被害者の現実の生活や苦悩とはかけ離れた内容です。今後の方針については、避難指示が出された区域のみを施策の対象とし、事故収束、帰還促進とそのための生活再建、帰還困難区域の「復興・再生」、ロボット産業などの誘致による「イノベーション・コースト構想」、事業や一次産業の再建、等を、「リスク・コミュニケーション」(放射能や被ばくのリスクの過小評価の押しつけ)を重ねながら進めるというもので、被害者の切実な生活再建の要望や不安、元の故郷の生活を取り戻したいという願いに応えるものではありません。それどころか、避難指示区域等の人々に対して行われてきた、医療保険、介護保険の保険料と医療費窓口負担の減免措置については、「住民税減免等の見直しが行われてきている」「被保険者間の不公平性等の観点から、適切な見直しを行う。」と、打ち切りの方向を示しています。また、ALPS処理水の海洋等への放出、除染土の再利用推進、モニタリングポストの撤去につながるような内容も含まれています。「自立」「復興」の名の下に、「復興・創生期間」終了の10年をメドに、医療費支援等、被害者の生活再建に必要な支援の切り捨てを許してはなりません。
事故後1~2年に、浪江町などは、自治体として住民に「健康手帳」を配布しました。そして、浪江・双葉町は、2012 年6月、無料の健診・医療、長期的な健康確保のための諸手当の支給、「放射線健康管理手帳」の交付など、「原爆被爆者手帳と同等の法整備」の要請を国に求めました。
福島原発事故被災地では、健康不安や生活不安、原発への不安などについて、公に語ることが憚れるような雰囲気が広がっています。国やマスコミの「復興宣伝」の中で不安を口にすることが、あたかも「風評被害を広げる」かのような雰囲気がつくり出されています。政府の一方的な避難指示区域の線引きによる分断などの理由から、不安を被ばくの影響は生涯にわたり健康被害は何時起こるか分かりません。またたとえ低線量被曝でも線量に応じた健康リスクがあります。福島原発事故では福島と周辺県の約400万人の人々が、はじめの1年間だけでも法令でも守られるべき「一般公衆の年間被ばく限度1mSv」を超える追加被ばくを強いられ、20mSv/年の基準で避難指示が解除された後も1mSv/年を遙かに超える被ばくを強いられています。自らの瑕疵なくして被ばくを強いられ、人権を侵害された人々が、健康を守るための施策を国に求めることは当然の権利です。国の責任で「健康手帳」(無料の健診と医療、生活保障などの権利を伴う「手帳」)の交付など、より包括的な国の医療・生活支援策を求める声を結集し、具体的な運動へと発展させていくことが重要です。
■原発事故を省みることなく放射線を語るな
政府の福島原発事故の基本姿勢は、現在も過去にも、放射線による健康被害はなく、「風評やいわれのない偏見・差別が今なお残っている主な要因は、放射線に関する正しい知識や福島県における食品中の放射性物質に関する検査結果、福島の復興の現状等の周知不足と考えられ」るとするものです。「風評払拭・リスクコミュニケーション強化戦略」の中で、健康影響への評価については、①放射線はその有無ではなく、量的に考える必要があること、②現在、福島県では放射線の安全性が確保されていること、③世界で最も厳しい水準の放射性物質に関する基準の設定や検査の徹底により、福島県産食品及び飲料水の安全は確保されていること等を発信し、個々人の安心感の醸成にしっかりとつなげていくことに留意する必要があるとしています。その主張を基本に、復興庁はパンフレット「放射線のホント」を配布しネット上でも公開しました。また、文科省も2018年10月より「放射線副読本」を全国の小学校、中学校、高等学校の全生徒分を各校に配布しています。このパンフレットは、福島原発事故の被害の重大性を隠し、放射線被曝の影響を過小に評価し、決して福島原発事故の真実をしっかりと捉えるものになっていません。国民の間にも、専門家の間にもきびしい意見対立のあるこのような問題を学校教育に押し付けることは、教育の中立性、子どもの人権の観点からも許されません。「放射線のホント」、「放射線副読本」の撤回を求める運動が各地で取り組まれています。運動をさらなる強化が求められます。
原発事故はいまだ収束しておらず、溶融した燃料は手つかず、汚染水はたまり続けています。山野においては除染も手つかずの状態で放置され、生活の場の近辺にも除染土や除染ゴミが仮置きされています。事故や天災などにより再び放射性物質が飛散する可能性は否定できません。
出荷規制のかかっていない場所で採取したとされ、直売所やネット上で販売されていた山菜から、食品基準(1kgあたり100Bq以下)を超える放射性セシウムが検出されるという事態が起こっています。しかし、国会の議論では、1kgあたり100Bq以下という食品基準は科学的・合理的かとの疑問を投げかけ、厳しい規制は一次産業に大きな打撃を与えているとして、基準の見直しを迫るものもありますが、このような規制緩和は許されません。むしろ、乳幼児への影響を優先的に考慮して食品基準を強化し、汚染食品の流通を阻止することが一次産業への打撃を和らげることになるのです。福島原発事故から10年を迎えようとする今なお、山野に降った放射性物質はいまだ環境を汚染し続けており、それが山菜の放射能汚染として現れているのです。20mSv/年の基準で避難指示を解除し、住民に被曝を強いる政策をとっているから、汚染された山菜を採取し流通させるような事態が起きているのです。政府は、法令で担保されている「一般公衆の被ばく線量限度1mSv/年」を可能な限り遵守させる政策を中心におき、「20mSv/年の基準による除染なき帰還困難区域の指定解除」方針を撤回し、住民に被曝を強要する政策を転換すべきです。
■東電はADRの和解案を尊重しろ
東電は、当初原発事故被害者に対して早急な補償の実現のために、「裁判外紛争解決手続(ADR)の和解案は尊重する」としていました。しかし、浪江町の集団ADR申立、飯舘村村民のADR申立など、に対して、東電は「20mSv程度の被爆の危険性は証明されていない」「精神的賠償は既存の金額で十分」などと主張し、和解案を拒否する姿勢に終始しています。2019年12月19日には、相馬市玉野地区の139世帯419人が慰謝料増額を求めたADRを、東電は和解案を複数回拒否し国の原子力損害賠償紛争解決センターは和解手続を打ち切りました。東電のADR和解拒否が続いている問題を重く見た所管官庁の文科省は、2020年3月26日、東電に対して和解仲介案の尊重を求めました。しかし2020年4月にも東電は、福島市大波地区と伊達市霊山町雪内、谷津地区の409世帯1241人が損害賠償を求めたADRにおいて2回に渡って和解案を拒否し、国のセンターは仲介手続を打ち切りました。
被害者は、十分な補償を受けられないことから、満足できる補償と支援を求める訴訟を全国各地で起こしています。多くの場合、原告側が勝訴し、東京電力に賠償を命じる判決が出ています。事故の責任を明確にせず放射能被害を認めない国と東電の姿勢が、全国各地での訴訟につながっていると考えられます。事実上国有化されている東電がこのような姿勢をとり続けられるのは、政府がそれを容認し、東電の破産処理を回避して東電を救済し続け、放射線被ばくを住民に強要する政策をとっているからであり、政府の責任でもあります。東電にADRを尊重させるためにも、東京電力と政府の事故責任を徹底追及することが重要です。
■事故の責任はどこに
検察庁が2度にわたって不起訴にし、検察審査会が強制起訴に踏み切った「福島原発刑事訴訟」は、17年6月30日の初公判でスタートし、東電元幹部3人の刑事責任を追及してきました。元幹部3人は、事故の原因は予想を超えた津波による自然災害にあるとして、一貫して責任を否定しています。しかし、裁判では建設の基準である想定を上回る津波予想を無視した経営者の姿が浮かび上がっています。事故被害者への不誠実な国や東電の態度は、原発の安全性に対して監督責任や運転責任を免れていることに起因しています。国や東電は加害者であることを認め事故の責任を全うすべきであり、原発事故被害をなかったことにしようとする姿勢は、被害者をさらに追い詰めるもので許すことはできません。2019年9月19日の判決は、「三陸から房総沖のどこでも巨大地震が起こりうる」とした長期評価を「取り入れるべき知見との評価を一般に受け入れていたわけではない」として、その信頼性や具体性を否定し、当時の原子炉等規制法が求めていたレベルは、「合理的に予測される自然災害を想定した安全性」だとして、東電旧経営陣に運転を止める義務はなかったと結論づけました。裁判において、旧経営陣は会議での津波対策の議論を、「関心を持たなかった」「記憶にない」などと繰り返し、権限を他に転嫁して自らの責任回避に終始しました。危険性が高く、一旦事故になれば取り返しの付かない事態が想定される原発の運転が、このよう無責任な組織・人間に委ねられている事実を、私たちはしっかりと受け止めていかなくてはなりません。地震・津波対策は元より、火山噴火やテロ対策、避難計画の策定などにおいて、電力会社は常に重大事故のリスクを過小評価し、経済性喪失と運転停止につながる対策を拒否し、あるいは先延ばししてきたのです。「世界最高水準の規制基準」の下で、地震の基準地震動は過小評価され、2020年4月から国の定期検査は廃止されて電気事業者の一義的責任に任され、維持基準による「ひび割れ放置」運転が常態化し、連続運転期間が13ヶ月から24ヶ月へ伸ばされようとしています。福島事故の教訓を踏まえるのであれば、第201通常国会(2020年6月17日閉会)で継続審議とされた「原発ゼロ」法案の閉会中審議などを進め、2021年度に見直し予定のエネルギー基本計画を再エネ優先・脱原発・脱石炭へ転換させるべきです。
■原発の再稼働を許すな
安倍政権は、原発推進政策を強引に進め、原発の再稼働を強行してきました。2020年6月24日現在、実際に稼働している原発は、九電玄海原発3・4号機、関電大飯原発3・4号機と高浜原発4号機の5基となっています。関電高浜3号機、四電伊方3号機は定期検査で停止しており、九電川内原発1・2号機は、テロ対策で原発に義務付けられた「特定重大事故等対処施設」の建設遅れで停止しています。福島事故以降、廃炉になった軽水炉原発は、21基となっています。2020年6月末現在新規制基準に適合とされた原発は16基(内稼働したのは9基)、その内4基は60年運転認可となっています。審査中は11基で泊、東通(東北)、志賀、敦賀原発では敷地内の活断層の評価をめぐって議論が続いています。今年2月の時点で、「稼働中」の原発は9基、規制基準審査中11基(建設中の島根3号と大間を含む)、未申請8基(柏崎刈羽1~5号、女川3号、浜岡5号、志賀1号)、審査合格後の対策工事中など7基で「停止中」の合計が26基(建設中の東電東通は含まず)となっています。福島事故発生直前に56基あった「稼働中」の軽水炉原発は9基へ激減し、21基が廃炉になり、7基が適合審査に合格したものの再稼働反対の声が高まっています。2019年9月30日福島第2原発全4基の廃炉が決定され、福島県民が求めて来た「原発のない福島」が現実のものとなりつつあります。原発の時代は、福島第一原発事故から10年を迎えようとする今、原発の時代は終焉に向かって進んでいるといってよい状況です。それを確実なものにするため、再稼働を阻止する闘いがかつてなく重要になっています。
福島第一原発の事故が示すように、原発の過酷事故は、地元はもとより非常に広範囲にわたって多大な被害を及ぼします。原発が集中する地域では、地震や津波などによって同時にまたは連鎖的に複数の原発で事故が起きることも予想されます。「新基準に適合したからといっても、安全とは言えない」と、田中俊一前原子力規制委員長は繰り返し表明していました。原発の安全性を監督する官庁の責任者が安全を保証できないのであれば、運転を認めるべきではありません。2019年11月の時点で、電力各社の合計した原発への安全対策費は、前年7月より約1兆円増の5兆3844億円と報じられています。これは、原発コストに大きく跳ね返っており、原発の生む電力が、市場経済での競争力を失いつつあることは明確です。そのほかにも住民避難の課題、住民合意の課題、使用済核燃料の処分や原発の廃炉、破綻した核燃料サイクル計画など課題は山積しています。
40年を超えて老朽化している日本原子力発電(原電)の東海第二原発(茨城県)は、原子力規制委員会の審査が終了し運転延長が許可されました。しかし、地元東海村を含めた6市町村の事前了解は得られておらず30キロ圏内の住民94万人の避難計画も策定されず、再稼働には至っていません。原電は、原発専業の企業であり福島原発事故以降発電事業はゼロにも係わらず、電力各社から「基本料金」として約1兆円を受け取ってきました。しかし、老朽原発東海第二の安全対策などで深刻な資金不足に陥っており、東京電力は2200億円という原電への資金援助を決定しています。福島第一原発事故の収束費用もままならず、国や電力消費者からの援助を受けている東電が、原発存続のために他社の費用負担を行うことは、市民の理解を超えており、許されるものではありません。原発立地点と都市部の連係した闘いで原発の再稼働を阻止しなければなりません。
■変わる司法、変わらない司法、そして変わらない政府
山口県の住民が起こした、四電伊方原発3号機の運転差し止め仮処分の即時抗告審で、2020年1月17日、広島高裁(森一岳裁判長)は、四電の地震や火山リスクに対する評価は不十分で安全性に問題が無いとする原子力規制委員会の判断は合理性を欠くとして、運転差し止めの決定をしました。決定は、2017年の決定を覆した2018年9月の広島高裁決定同様に、阿蘇山の破局的噴火の可能性は低いとした。しかし一方で、破局的噴火に至らない最大規模の噴火の想定が過小であるとして、四電の想定認めた規制委員会の判断を批判しました。森裁判長は、原発の危険性の検証には、福島原発事故のような事故を絶対に起こさないという理念を基本にした解釈が必要として、専門家の判断が分かれる場合は、きびしくない方を安易に採用してはならないとの立場を明確にしています。
大飯原発の運転を差し止めた福井地裁判決(2015年4月)、高浜原発を差し止めた大津地裁の仮処分決定(2016年3月)、広島高裁の仮処分決定(2017年12月と2020年1月の2回)など、福島原発事故以降、裁判所の考え方は明らかに変化しています。しかし、これらの判決や決定は、高裁段階(高裁での仮処分決定の異議審での取消決定を含む)で取り消されてきました。絶対的安全を求めることは合理的ではなく、社会通念上ある程度のリスクは認められるとする判断も依然として続いています。広島高裁の決定に対して、四電は決定を不服として争うとし、規制委員会も「新規制基準は最新の科学的・技術的知見に基づく。審査は適切」として反発しています。とくに、運転差止めの判決・仮処分決定が相次ぐ中、規制委員会は2016年6月に「実用発電用原子炉に係る新規制基準の考え方について」を策定し、これが判決・決定を覆す判決・決定の理由説明文の中でそのまま引用されています。原発推進の立場に立たないはずの規制委員会のこのような姿勢には、再稼働阻止の裁判闘争や運動の中で徹底した批判を強めていかねばなりません。
判決直前の1月12日、定期点検中の伊方原発3号機で制御棒を誤って引き抜くトラブルがあったと発表されました。同月20日には、手動でクレーンを操作し燃料棒を移動させていた際に点検装置の枠に乗り上げ、落下を示す信号が発信されるというトラブル、同月25日には、発電所内が停電しほぼ全ての電源が一時的に喪失するトラブルもありました。制御棒を引き抜くトラブルは、規制委員会が「知る限り前例がない」「事業者の深刻度や捉え方が少し軽すぎるのではないか」と指摘しています。危険な原発をいい加減に運転しトラブルを重ねながら、裁判所の指摘には反発する姿勢は、福島原発事故以前と同様に傲慢で許されないものです。
■改ざんや隠ぺい、虚偽で固める原発政策
2020年2月7日、原電敦賀原発2号機の審査会合が開催されましたが、原電がこれまで提出した資料において、それも活断層かどうかに係わる審査の根幹部分で、元データの改ざんが発覚しました。書き換えや削除は、80箇所に上ります。原電は、これまでも敦賀原発2号機の稼働に関して、規制庁職員から報告書の原案を事前に入手し反論準備を行う、専門家チームに厳重抗議なる文書を持って圧力をかける、冷却水漏れを隠ぺいする、使用済み核燃料のキャスク関連の試験データを改ざんする、原子炉格納容器の機密性試験で空気漏れを不正に塞いで合格させる、原発サイト内を走る活断層を否定するなど、様々違法な行為を繰り返してきました。原発に絡んでの電力会社のデータ改ざんなどは、原電に限らず様々行われてきました。廃炉となった高速増殖炉実験炉「もんじゅ」のナトリウム漏れ事故の際の「ビデオ隠し」では、内部調査担当者の自殺にまで発展しました。また、原子力規制委員会の更田豊志委員長が、関電への火山灰想定のやり直しを命じる命令文を作成する事前会議を開いていたことを隠ぺいする虚偽の説明をしていたことも判明しています。
関西電力において、長期にわたって会社幹部の不正な金品受領が発覚した問題で、2020年3月14日、この「関西電力役職員らの金品受領問題」という、重大なガバナンス問題を追及する第三者委員会(但木敬一委員長)の調査報告書が公表されました。この金品の受領が工事発注などの見返りであれば収賄や背任という事件に発展するため、第三者委員会の調査は重要であり、衆目の一致するところでした。しかし、第三者委員会は報告で本件取引先に対する発注金額を水増ししていた等の事実は見られず、本件取引先に対する発注金額が不合理であると認めるまでには至らなかった」としています。しかし、何もないところにこのような不正な金品の流れができるわけはなく、第三者委員会の調査は不十分と言わざるを得ません。
原発反対福井県民会議の宮下正一事務局長(福井県平和運動センター前事務局長)や中嶌哲演共同代表委員らが発起人となり、「関電の原発マネー不正還流を告発する会」が発足し、関電役員を告発する運動が展開されています。「原発関連工事として支出した金が役員に還流していたことは明らかで、不当に工事費がつり上げられ会社に損害を与えた」などとして、2019年12月13日には、関電役員12人に特別背任罪(会社法960条1項)、背任罪(刑法247条)、贈収賄罪(会社法967条1項)、所得税法違反(238条1項、120条1項)の疑いがあるとして、3,272人(その後3,371人)が告発状を大阪地検に提出しました。告発人には、原水禁役員も参加しています。2020年6月9日には第三者委員会報告で明らかになった「退任役員への報酬減額分や国税局への追加納税分の補填」を業務上横領と特別背任で、大阪地検へ追加告発されました。追加告発人は2,172名で、一次告発に参加していなかった新規告発人は171名ですので、告発人総数は3,542名に上ります。
また、関西電力は、株主からの提訴請求(2019.11.28、2020.4.18)を受け、旧役員の善管注意義務違反を認定した取締役責任調査委員会6月報告に基づき、6月16日に元役員5名に対する19億3,600万円の損害賠償請求訴訟を大阪地裁へ提起しました。しかし、これでは不十分であり、責任追及が曖昧になる可能性もあることから、提訴請求した株主5人が原告となり、44人の株主が訴訟参加する形で、49名の原告団が6月23日、現旧役員22名に対し92億円の損害賠償を求める株主代表訴訟を提訴しています。
今後、原発の闇を解明し、原発推進の利権構造を解体すべく、とりくみを強化していかなくてはなりません。
■世界の懸念、46トンもの日本のプルトニウム
核不拡散防止条約(NPT)に加盟する日本は、核兵器を保有しない国で唯一「核燃料サイクル計画」をエネルギー政策の基本に据えて、使用済み核燃料からプルトニウムを抽出する再処理を実施しています。核兵器に転用可能なプルトニウムに関しては、その利用計画を国際原子力機関(IAEA)に報告・公表することになっています。原子力委員会は「『利用目的のないプルトニウムは持たない』との原則を示すとともに、プルトニウム管理状況の公表やプルトニウム利用計画の策定・公表など積極的な情報発信を進めている」としています。2018年7月、日米原子力協定改定に際して、米国は日本政府に対し、①プルトニウム保有上限量の策定、②削減策の公表などを求めてきました。原子力委員会は 同月31日に「我が国のプルトニウム利用について」を策定し、「プルトニウム保有量を減少させる。プルトニウム保有量は、以下の措置の実現に基づき、現在の水準を超えることはない」として、①必要以上生産しない、②プルトニウムの需給バランスを確保する、③海外保有分(英:約21トン、仏:約15トン)の着実な削減に取り組むことなどをあげています。
しかし、国内外に46トン(2018年末分離プルトニウム45.7トン、国内保管9.0トン、英仏保管36.7トン:原子力委員会2019.7.30)ものプルトニウムを保有する日本は、2018年3月には「高速増殖炉もんじゅ」の廃炉が認可されることでプルトニウム利用の将来が閉ざされています。また、2011年の福島原発事故以降、原発の再稼働もままならず(2020年6月現在9基、プルサーマル可は4基のみ)、輸入MOX燃料価格はウラン燃料の10倍で、英保管プルトニウムは加工工場がないためMOX加工できず、伊方3号と玄海3号の仏保管プルトニウムは残り少なくて新規発注できず、新MOX燃料はプール保管中のそれぞれ5体と4体に留まります。高浜3・4号は最大40体装荷のところ数年おきに16体ずつ発注し、経済性に影響しない程度に実施しています。このような欺瞞的「プルサーマル実施」をやめ、経済性がなく、原発重大事故の危険を高めるプルサーマルを即刻中止し、六ヶ所再処理工場を閉鎖すべきです。
■行き詰まるプルトニウム利用
「もんじゅ」の廃炉決定によって、再処理したプルトニウム利用を基本に据える「核燃料サイクル計画」は行き詰まっています。高速炉計画の断念は、再処理工場の意義が一挙に失われ、「核燃料サイクル計画」の失敗を意味します。日本政府は、高速炉計画を継続させるために、世界で唯一とも言える高速炉計画である仏の「アストリッド(ASTRID)」計画に参画することを表明しました。しかし、仏マクロン政権は、2018年11月27日、電力量に占める原子力比率の75%から50%への引き下げ時期を2035年へ10年遅らせる一方、再エネ投資を1.5倍へ増やし2030年までに陸上風力5倍化・海上風力開発促進で原子力の再エネへの転換を加速させる方針を打ち出し、「2020年代半ばまでにASTRID実機建設の可否を判断する」予定を撤回しました。2019年10月、仏原子力・代替エネルギー庁(CEA)のフランソワ・ジャック長官は、「アストリッド建設断念」を表明しました。ウランが低価格で推移し、高速炉の実用化は経済性が見いだせないということが理由だと考えます。日本政府は、この現実を真摯に受け止め、再処理・プルトニウム利用政策からの撤退を決定すべきです。
MOX燃料も、仏からの輸入MOX燃料費は通常のウラン燃料費の10倍近く、国内調達(六ヶ所再処理工場やMOX燃料工場:2022年上期完工予定)ではその数倍にもなることが予想され、原発の発電コスト、売電価格に影響するのは必至です。プルトニウム利用が、市場経済の中で破綻していることは明らかになっています。原発再稼働阻止・プルサーマル阻止の闘いを再処理工場閉鎖の闘いと結びつけ、脱原発・脱プルトニウムに向けて前進しましょう。
■六ヶ所再処理工場の閉鎖を
2020年5月13日、原子力規制委員会は、日本原燃の使用済み核燃料再処理工場(青森県六ケ所村)が新規制基準に適合していると認める「審査書案」を全会一致で了承しました。国内初の商業用工場として本格稼働の前提となる審査に事実上「合格」した。今後、一般からの意見公募や経済産業相への意見照会などを経て正式合格となります。
審査書案は、基準値振動を600ガルから700ガルに引き上げていますが、他の原発の基準値振動や過去の地震の規模などを考えると、全く不十分と言えます。規制委員会は、審査書案の議論を前に、「六ヶ所再処理工場がリスクを上回る有益性があるのか、そのことがエネルギー基本計画で確認されているのか」と経産相に問うています。更田委員長は、問いの理由を「得られる便益より与える害の方が大きい施設は許容されないので」と述べています。ならば、まさしく今、六ヶ所再処理工場建設が、核燃料サイクル計画が、改めて問われなければならないのです。
六ヶ所再処理工場は1993年に工事に着工しましたが、ガラス固化体の加工工程でのトラブルが相次ぐなど、1997年の完工予定は24回の延期を経て現在2021年上期とされています。建設費は当初の7600億円から約3兆円と4倍近くに膨れあがり、総事業費も約14兆円に上ると予想されています。抽出したプルトニウムを利用するMOX加工工場の完工も2022年度上期に延期され、その建設費も当初の2倍、2.3兆円に上っています。これらの費用は、電力各社の持ち寄りとなっており、元を正せば、消費者が支払う電力料金です。
規制委員会の更田委員長は、原燃が目指す完工時期について「アンビシャス(野心的)だと思う。今後の審査の対象となる設備や機器の量は膨大であり、原燃がどれだけ念入りな計画を立てられるかにかかっている」としました。2021年上期などと言う完工予定は、実現不可能なものと言わざるを得ません。高速炉計画の破綻、経済的に利用価値のない高額なMOX燃料、原発以上の危険性と技術的困難性、今後も予想される建設費用の増大など、再処理を取り巻く状況はきびしく、将来の見通しは全く立っていません。MOX燃料加工工場と共に六ヶ所再処理工場の早期の計画断念・閉鎖を求めていきましょう。
■破綻した核燃料サイクル計画-放棄への決断を迫る全国的な闘いを
夢のエネルギーと言われた、使用済み核燃料から抽出したプルトニウムを利用する「核燃料サイクル計画」の中核を占める高速増殖炉原型炉「もんじゅ」(福井県)の廃炉の決定、その後日本政府が参加するとした仏高速炉計画「アストリッド」の中止決定、「核燃料サイクル計画」の破綻は明らかです。国策ありきですすめてきた計画は、止めるものがないままに暴走してきました。しかし、日本政府はこの計画を推進するとしています。現在六ヶ所に保管する大量の使用済み燃料は、六ヶ所の計画断念が決定すれば、青森県との協定では、全国の原発に戻すこととなっています。現在でも、サイト内の使用済み燃料は満杯に近く、六ヶ所で保管される使用済み燃料が戻るとすれば、原発の稼働は困難になります。また、日米原子力協定によって認められる「再処理」の特権も失い、廃止決定後は使用済燃料が大きな負債となって電力会社にのしかかるでしょう。このような理由から、六ヶ所再処理工場、核燃料サイクル計画は「推進」され、無駄な資金がつぎ込まれてきました。
2017年12月の「もんじゅ」廃炉決定など、既存の政策を変更するような政治決定には、様々な困難があると思いますが、政治が決断しなければ、新しい未来は開けません。再エネ推進と脱原発が国際的な流れとなっている今、その決断にとって猶予ない最後の場面を迎えているのだと考えます。それを政府に迫るには、「原発ゼロ」法案を実現させるほどの大きな全国的な運動が必要不可欠です。
■原発に拘泥するな
2011年の福島原発での重大事故の後も、安倍政権はアベノミクスの重要な柱に原発輸出政策を位置づけ、自ら世界に「日本の原発は世界一安全」としてセールスしました。しかし、ウェスティングハウス社を買収し、インドや米国での原発建設に打って出た東芝、フラマトム(旧アレバ)との共同出資で、トルコのシノップに原発4基建設するとした三菱重工、英ホライズン社を買収し、英国中部アングルシー島ウィルファ原発の新設計画の受注を目指した日立製作所、これらの計画は全て頓挫しました。風力・太陽光など再エネ拡大の方向が顕著となって、安全対策に莫大な費用がかかる原発は、市場から閉め出される状況となっています。
経団連は、このような世界情勢の中で、原発の再稼働促進、運転期間の最長60年を超える延長、福島原発事故以降の停止期間の運転期間からの除外、規制の合理化・審査の迅速化、原発のリプレース・新増設・新型炉開発、原発優遇のベースロード電源市場や非化石価値取引市場などの電力システム改革を求めるなど、原発推進の電力政策を提言しました。脱原発を求める市民社会の動向や再生可能エネルギーを中心とした世界の情勢からは無謀とも言える提言は、原発推進の側の追い詰められた状況を明らかに反映しています。
政府は、エネルギーの「ベストミックス」などという原発温存の政策や非現実的な原発輸出策、破綻している六ヶ所再処理工場などの核燃料サイクル計画などを早期に廃止し、再生可能エネルギーを中心としたエネルギー体制を構築すべく、早期に「脱原発」の姿勢を明確にすべきです。2021年度予定のエネルギー基本計画改定で再エネ優先、脱原発・脱石炭路線へ転換し、太陽光・熱発電、地熱・風力・潮力などの発電技術の新規開発・向上への支援を進め、企業の動きを活性化すべきです
■すすむ自然エネルギー、政策の転換を
脱原発、自然エネルギーへの方向転換は世界各国で顕著となっています。自然エネルギー財団の示す2019年の統計では、法律で原発を禁止しているデンマークでは、発電量に占める自然エネルギーの割合が79%となっています。カナダ66%、スウェーデン59%、ポルトガル55%、2022年までの脱原発を決定したドイツは、42%を達成しています。日本はいまだ20%に止まっていますが、火力発電が65%を占める中国も27%にまで高まっています。原子力が69%を占める原子力大国フランスでは、前政権の2025年までに原子力発電比率を50%まで削減するとした目標を、マクロン政権は10年先送りしました。しかし、2022年までに石炭火力発電を全て廃止し、2030年までに発電量に占める再生可能エネルギー割合を現在の約18%から40%に引き上げることを決定し、再生可能エネルギーと環境保全分野に150億ユーロ(約1.8兆円)を投資するとしています。様々な国においてエネルギー革命とも呼べる動きが強まっており、世界の電源比率は、原子力は10.4%、自然エネルギーは26%となっています。この動きは変わることはないでしょう。自然エネルギー(太陽光発電)の発電コストは、2010年に36¢/kWhでしたが、2017年には10¢/kWhと、73%減となりました。風力発電や太陽光・熱発電、バイオマスなど再生可能エネルギーが急速に普及することで発電コストも大きく下がっています。
国際再生可能エネルギー機関(IRENA)は、2018年1月のレポートで、「すでに商用段階にある自然エネルギーの発電コストは方法の違いにかかわらず、2020年までには化石燃料による火力発電と同等になる」として、陸上風力は5¢/kWhに、太陽光は6¢/kWhになると予測しました。しかし、2018年11月のLazard(世界規模の財務アドバイザリー及び資産運用会社)の統計に依れば、助成金無しの均等発電原価で、陸上風力発電コストは4.2¢/kWh、太陽光発電が4.3¢/kWhとなっています。ガスコンバインド発電は5.8¢/kWh、石炭火力が10.2¢/kWh 、原子力は15.1¢/kWhとなっています。世界のエネルギーは、原発ゼロ・再生可能エネルギー推進へと向かい、温暖化防止のパリ協定がこの流れを促進しています。日本でも、福島原発事故以降、原発が稼働しなくても電力は不足しませんでした。脱原発、脱炭素、再生可能エネルギーへの転換は、机上の論理ではなく現実的なものとなっています。
ところが、日本では、再エネ普及に三大制約を課して自然エネルギーの普及を阻害しています。第一の制約は、廃炉になっていない原発が震災前の設備利用率で動くと仮定した上で電力需給面からの「接続可能量」が設定され、これを超える再エネ接続には無制限・無補償の出力制御(運転停止)が課されています。第二は、停止中・建設中を含めた原発・石炭火力など大型電源が容量を先取りした上で送電線の容量面から再エネの接続が拒否されています。これは「日本版コネクト&マネージ」で少し緩和されましたが、送電事故時や潮流過多時に再エネの接続が遮断される状況は変りません。第三は、送電網へ接続するための一次変電所への接続工事費が全額負担とされ、不当に遠い変電所への接続が求められたり、高価な工事費を請求されたりして、断念するケースが後を断たないことです。また、一次変電所から基幹系統へのローカル系統送電網の増強工事費については、「発電側基本料金」の導入(2023年度予定)で再エネ事業者の特定負担金のうち初期負担分の減額と減額分の分割払い化が図られようとしていますが、新規に接続する再エネ事業者だけでなく、すでに接続している再エネ事業者へも発電側基本料金が課されようとしており、これが、再エネ普及妨害の新たな制約になろうとしています。国内で再エネを抜本的に普及させるためには、「日本に固有の原発・石炭火力のベースロード電源優遇」から「欧米では当たり前の再エネ優先接続・優先給電」へ転換させることが不可欠です。
■気候危機とエネルギー政策
2019年11月29日、世界中の若者らが地球温暖化対策の強化を求めてデモをする「グローバル気候マーチ」が、世界150カ国以上であり、日本国内でも25都府県で行われました。「気候危機の影響を受けるのは若者」と訴え、スウェーデン国会議事堂前にひとりで座り込んだグレタ・トゥンベリさんの訴えは、世界の若者に広がりました。12月11日、スペイン・マドリードで開催された「第25回国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP25)で演説したグレタはさんは「一番危険なのは行動しないことではない。危険なのは、政治家や企業家たちが、ほとんど何もしていないのに、ずるがしこい説明と想像力豊かなPRで、本当の行動をしていると見せかけることだ」と訴えました。
2019年9月9日、10月12日、日本は首都圏を中心に史上最強とも言える大型台風の直撃を受けました。台風19号(10/12)の経済損失は、その年の世界最高額を記録し、台風15号(9/9)の経済損失とあわせて2兆7500億円に達しました。世界的に見ても、ここ30年で、気象関連自然災害による経済損失額は約3倍に増加しています。日本の平均気温は、徐々に上昇し、特に1990年代以降真夏日は10年で0.6日増加し、猛暑日も1990年代後半から特に増加しています。文科省、気象庁、環境省のまとめを見ると、このまま気温上昇が続くなら今世紀末には日本で真夏日が最大で2.1倍、熱帯夜は3.3倍になると予測されています。
2020年に入って、世界は新型コロナウイルス感染症の拡大によって、多くの国々でロックダウン(都市封鎖)が行われ、各国間の交流も中断されました。経済活動が停滞する中にあって、国際エネルギー機関は、今年の二酸化炭素排出量は前年を8%下回ると発表しました。温暖化は人類共通の危機であり、世界が一体となって対応しなくてはならない課題です。経済活動の活性化と二酸化炭素排出の縮減という課題を、どのように両立させるかは、ポストコロナ社会の大きな課題になっていくと考えます。
2020年6月、イギリスのLGA(Local Government Association:地方自治体協会)は経済回復に向けた報告書を発表し、その手段として「グリーン・ジョブ」と呼ばれる環境関連の雇用を促進していくべきだと主張しています。英政府が主張する「カーボンニュートラル」実現のための「UK net zero target」への動きを政府と地方自治体連携で加速していけば、今後10年で70万人、2050年までに100万人以上に上るグリーン・ジョブが生まれるとしています。
米国オバマ政権が2008年から推し進める「グリーン・ニューディール政策」では、総額でおよそ7800億ドル(72.8兆円)もの資金を投じて、環境・エネルギー分野の技術開発や新サービスの普及に取り組んできました。2019年2月7日、米民主党は環境政策で米経済を成長させる「グリーン・ニューディール(Green New Deal)」下院決議案を発表しました。発表された「グリーン・ニューディール」決議案は、今後10年以内に国内電源を風力発電や太陽光発電のような二酸化炭素排出量ゼロの再生可能エネルギーに100%切り替えることや、交通手段の近代化、製造業及び農業での二酸化炭素排出量削減、住宅及び建物のグリーンビルディング化、土地保全の拡大等を通じた気候変動政策を大きく掲げています。
EU議会では、フランスのマクロン大統領が、EU加盟国は2050年までに温暖化ガスの域内排出量を実質ゼロにすることを提案し、ドイツのメルケル大統領も、2021年から28年のEU共通予算の4分の1を気候変動やエネルギー効率関連に向けること支持しています。
COP25において、小泉進次郞環境大臣は、日本の石炭火力政策に変更がないことを表明しました。石炭火力発電の廃止など脱炭素に向けた具体策には踏み込めず、現状の温暖化ガス削減目標の上積みも見送りました。世界からの批判が強まることは必至です。石炭火力は二酸化炭素排出量が多く、気候危機に敏感となっている欧州各国は石炭火力の全廃計画をそれぞれ発表しています。(仏:2021、英:2025、伊:2025、蘭:2030、独2038)
COP25開催中の2019年12月3日、日本はCOP25開催中初の「化石賞」(Fossil Award)を受賞しました。化石賞は地球温暖化問題に取り組む世界のNGOのネットーワークである「CANインターナショナル」が、温暖化対策に消極的な国に与える不名誉な賞です。日本は、12月11日にも開催中2度目の化石賞を受賞しました。石炭火力の継続を表明する日本は、世界から強く批判されています。
■日本の「石炭火力廃止」の偽り
2020年7月3日、日本政府は、国内に140基ほど存在する、特に二酸化炭素の排出量の多い従来型の石炭火力発電所の約9割、およそ100基を廃休止する方向で調整に入るとしました。気候危機対策に後ろ向きとの世界からの批判をかわす狙いがあるものと思われます。しかし、一方で効率の良い新型の石炭火力は認めるとしています。石炭ガス化複合発電(IGCC)や石炭ガス化燃料電池複合発電(IGFC)のCO2排出係数は、従来型石炭発電のCO2排出係数0.80~0.867kg-CO2/kWhと比べてIGCCで0.73kg-CO2/kWhで、IGFCでも0.590.73kg-CO2/kWhと最大でも約3割の削減にしかなりません(LNGガスタービン複合発電は0.32~0.36kg-CO2/kWh)。このことを考えると、今回の政府方針は、二酸化炭素排出量の大きな引き下げにはつながらず、新規石炭火力の建設を認めることで、二酸化炭素排出量を固定化することにつながります。また、政府は再生可能エネルギーの比率を高め(実際には再エネ普及抑制策を講じようとしている)、原子力発電の稼働率も高めたいとしており、原発再稼働や40年超運転促進に向けた原子力規制委員会や立地・周辺自治体への圧力強化につながる可能性もあります。
2019年12月17日、英スタンダード・チャータード銀行が、シンガポールのOCBC銀行についで、ベトナムにおけるブンアン第2石炭火力発電所への融資の段階的取りやめを決定しました。シンガポールのDBS銀行や事業出資者のCLPホールディングス(香港)も脱石炭方針を発表し撤退を表明しています。同石炭火力発電所建設の事業出資者である三菱商事と融資を予定する日本の官民5銀行の姿勢は、温暖化対策が重要な課題となっている中にあってきわめて問題です。オランダのNGOの調査では、2017年1月から2019年9月までの、石炭火力開発企業への融資額の1位から3位までを日本のみずほ・三菱UFJ・三井住友の各行が独占しており、世界からの批判を浴びています。みずほ、三菱UFJ、三井住友の各行は、石炭火力の新設事業への融資停止を発表していますが、しかし、進行中の計画など例外が存在すること、石炭火力に係わる企業への資金提供が制限されないなどの問題点が指摘されており、不十分なものとなっています。日本の環境政策、エネルギー政策は、世界の動きに遅れていることは明らかであり、日本政府の明確な姿勢を確立させることが重要です。
■原発は温暖化対策の切り札ではない
気候危機が進む中で、「原発は発電中に二酸化炭素を出さない」と言うことから、エネルギー政策において二酸化炭素排出削減の切り札のように喧伝されています。しかし、二酸化炭素の排出は、巨大な原発の建設、ウラン資源の採取から、燃料棒の製造・使用、使用済み燃料の廃棄に至るすべてのプロセスを踏まえて考えなくてはなりません。ベースロード電源と位置づけられる原発は、急激な需要の変化に応じることができず、事故等で不意に長期間止まる可能性もあって、火力との併用が必須であり、二酸化炭素排出削減にはつながりません。一基で100万kWを超える大規模発電は、小規模分散型の再生可能エネルギーの普及を妨げるもので、地球温暖化へ逆行する施設となります。
また、気候危機が進む中で、熱波などによる渇水には、冷却に大量の水を必要とする火力や原子力は、きわめて脆弱なものであることが分かります。気候危機を利用しての原発推進策は決して許されません。運転を停止した原発の廃炉は、10%にも満たず一向に進んでいません。高レベル放射性廃棄物の最終処分にいたっては、世界で一ヶ所も動いていません。原子力産業には、多くの課題が山積しており、今後その役割はきわめて限定的であることが確実です。今後、自然エネルギーが益々優位になっていくことは明白です。
2015年には、電力広域的運営推進機関を設け、地域間の需給調整や地域間連系線の増強など全国規模での系統運用をすすめることとしました。2016年からは、一般家庭においても電気を選ぶことができる、電力の「小売り自由化」が始まりました。新規参入の活性化が図られ3年後には全販売電力量に占める割合は15%に増加しました。しかし、原発再稼働による電気料金値下げによる2017年度以降の主に特別高圧・高圧分野での巻き返しにより、2020年4月段階で未だ16%と大きな進捗には至らず、新電力の既存大手電力会社のほぼ独占状態が続いています。そのため、2020年4月に廃止される予定だった「総括原価方式による電気料金制度」(託送料金は別途総括原価方式が続く)が、電力会社(旧一般電気事業者)の支配力が弱まるまで当面の間、存続されることになっています。電力会社の支配力の源泉は電源の83%独占と政府の原発・石炭優遇政策にあり、電力会社への取引所市場への電力供出強制と再エネ優先政策への転換を政府に求めていかねばなりません。
2020年4月には発送電分離が実施されました。しかし、「所有分離」ではなく別会社化(東電は持ち株会社化)して情報を遮断する「法的分離」に留まったため、送配電網の公平で中立的な管理運営が行われているとは言えません。送配電網を独占する大手電力会社の送配電網子会社は、電力需給面からの「接続可能量」に基づく無制限・無補償の出力制御、送電容量面からの送電線への接続拒否・接続制限、高額の接続工事費など三大制約を再エネ事業者に課し、電力会社の支配力を維持しようとするでしょう。脱原発を基本方針に、地域送電網の構築を含めて、再生可能エネルギーの優先接続・優先給電など脱原発へのエネルギー政策の転換を掲げ、「法的分離」ではあっても中立的な全欧州統一の送電網管理で再生可能エネルギーを40%程度へ高めているドイツなどの先進事例に学び、送電網の中立的な全国統一管理体制の実現を求めていくことが重要です。2020年7月3日、経産省は送電線の利用ルールを見直し、旧式の古い発電設備が優先的に接続されるしくみを改め、再生可能エネルギーを優先し、発電量が大幅に増えたときに再エネの接続が制限されないようにすることを表明しました。旧式の火力発電を抑制することが目的で、市場価格が安い順に電気を接続させる方法が有力視されているとしていますが、FITからFIPへの移行と連動している可能性があり、そうであれば、再エネの優先接続・優先給電にはほど遠いと言えます。
2020年6月5日、参議院本会議で電気事業法やFIT法(再生可能エネルギー特別措置法)などの改正を盛り込んだ「エネルギー供給強靱化法」が可決・成立しました。2022年4月に施行されます。これまでの再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度(FIT)の一律適用を廃止し、再エネを競争電力と地域活用電力に大別し、地域活用電力にだけFIT適用を認め、その適用条件を自家消費30%以上などと厳しくし、入札範囲拡大と合わせてFIT適用を抑制する方針です。また、事業用太陽光発電と風力発電を競争電力に位置づけ、FITからFIP(フィード イン プレミアム)に移行するとしています。この制度は、再エネ価格を市場価格に移行しながら一定のプレミアムを(固定か変動がある)かけるものです。FITが電力価格を引き上げるという批判がありますが、FIT賦課金は増えていても電気料金単価そのものは上がっておらず、根拠はありませんし、これからはFIT期間の切れる再エネが増えてくるため賦課金はむしろ減っていきます。電力会社の電力供出が限られていて取引所取引が停滞している中で、FITを制限してFIPへ移行させるのは再エネの普及を妨げることになります。2020年7月を目途に、将来の発電容量を取引する「容量市場」の入札を開始するとしています。政府は、電力の自由化によって計画的な設備容量確保が難しいために、「容量入札」を実施して発電所を確保しようというのです。しかし、その裏で原子力や石炭火力発電所の維持・延命の方向に使われる可能性があります。様々な電力システム改革が進行している中で、脱原発・再生可能エネルギー社会の構築がきわめて重要な課題であり、その方向を阻害する電力システム改革を許してはなりません。
再生可能エネルギー推進によってこそ、地域の経済が新しく豊かになります。地域分散型のエネルギーのあり方は、地方再生を謳う政府の政策とともにあるものであり、政府が地方再生を真剣に考えるなら、再生可能エネルギーの推進はその一端を担うものであること考えていかなくてはなりません。地域からのエネルギー革命が、日本の将来をつくり出すと言えます。
■高レベル放射性廃棄物問題
経済産業省資源エネルギー庁は、2017年7月28日に、高レベル放射性廃棄物(核のゴミ)の最終処分場を選定するための「科学的特性マップ」(適地マップ)を公表しました。適地マップは、日本の65%にもおよぶ地域で地層処分が可能としており、8割の自治体が誘致可能となっています。放射能の半減期が2万4000年ときわめて危険性の高いプルトニウムの地層処分が、地震国、火山国である日本において65%の地域で可能であるとする適地マップは、地層処分ありきで、受け入れ可能自治体の範囲を拡大しようとする意図さえ感じられます。
高レベル放射性廃棄物の最終処分場建設に関しては、政府は、自治体に対して多額の「交付金」を支給することで誘致の実現を図ろうとしてきました。原子力発電環境整備機構(NUMO)は、電気料金に付加され電力消費者から徴収してきた資金で、シンポジウム、意見交換会、地層処分展示車ジオミライ号を使ったイベントなど、地層処分誘致に向けた広報活動を行ってきました。学生アルバイトをつかったやらせ参加などの不正も明らかになっています。しかし、現状で処分場受け入れを表明する自治体はありません。
2019年12月の和歌山県白浜町議会は、「安心・安全な町づくり推進条例」を全会一致で可決し、同月19日に施行しました。条例は、「まちづくりに影響を及ぼすと危惧される事項を認めない」とし、具体例として「使用済み核燃料などの持ち込み、貯蔵または処分する施設を建設すること」を挙げています。条例制定には、地元市民活動の働きかけがありました。市民のとりくみの中で、核のゴミを受け入れない自治体の姿勢づくりが大切です。「脱原発」を国の方針として確立させ、これ以上高レベル放射性廃棄物などの核のごみを増やさないことが、一番重要であり、これを棚上げにしたまま、原発の再稼働や六ヶ所再処理工場など核燃料サイクル計画を進め、あらたに多くの核のごみを生みだすことは、そのツケを将来世代に回すもので許されません。
■重要性を増す「さようなら原発1000万人アクション」と原発ゼロ基本法案
2011年3月の福島原発事故に際して、原水禁は、作家の大江健三郎さんやルポライターの鎌田慧さんらの協力で、「さようなら原発1000万人アクション」を立ち上げ、2011年9月19日(明治公園:6万人)、2012年7月16日(代々木公園:17万人)と脱原発の大集会を開催し、以降さようなら原発1000万人署名、集会や学習会、ニュースの作成・発行、フクシマ連帯ととりくみを、様々な市民団体・個人の協力の下ですすめてきました。原発立地県を中心とした全国各地の運動と市民社会をつなげ、脱原発のとりくみの原動力ともなっています。とりくみは市民社会の中に「脱原発」をしっかりと根付かせてきました。「脱原発」の実現のために、「さようなら原発1000万人アクション」の運動の進化が求められています。
「いばらき原発県民投票の会」は、コロナ禍の中で、約8万6703人の署名を集め、大井川和彦知事に対して、「日本原電東海第二原発(東海村)の再稼働の賛否を問う県民投票」の直接請求を行いました。条例案の提出を受けた茨城県議会は、2020年6月23日の本会議で、反対53(自民・公明・国民民主など)、賛成5(立憲・共産など)で否決しました。
自民党は本会議で「県民投票は県民の間にしこりを残す」などと反対理由を表明しています。福島原発事故以降、新潟(2012年)、宮城(2019年)、静岡(2012年)、東京(2012年で住民投票条例制定の動きがありましたが、いずれも議会で否決されています。地方自治法第74条は「普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者は,政令の定めるところにより,その総数の五十分の一以上の者の連署をもって,その代表者から,普通地方公共団体の長に対し,条例の制定又は改廃の請求をすることができる」とされています。現在、住民投票条例の成立率は、市町村合併に関するものを除くと6%程度と極めて低いものです。住民の意思をどのように政治に反映していくかが、特に原発問題では問われています。
立憲民主党が中心となって、2018年3月9日、社民・共産・自由の3党とともに衆議院に提出した、運転中の原発を速やかに停止し、法施行後5年以内の廃炉を決定する、使用済み核燃料については再処理を行わないことなどを盛り込んだ「原発ゼロ基本法案」は、一度も審議されずに2年以上も店ざらしのままになっています。2019年6月に、国民民主党も提案者となって提出された「分散型エネルギー利用促進法案」など再エネ普及を目的とした4法案も同様に審議入りさえしていません。安倍政権は、気に入らないものは議論もしないという、立憲主義、民主主義無視の姿勢をあからさまにしています。国会での真摯な議論の展開を期待するとともに、脱原発にむけた国民的運動に結びつけていくことが大切です。
(3)ヒバクシャ・核被害者への援護と連帯を
■急がれる被爆者課題の解決
ヒロシマ・ナガサキの被爆者(「被爆者健康手帳」所持者)は、厚生労働省の統計によると2020年3月末現在で83.31才、2019年度末より9162人減って全国で13万6682人となり、1981年末のピーク時の37万2264人の36.7%、昨年度より2.5ポイント減少しています。被爆者が年々高齢化し、人数が減って行く中で、残された被爆者援護課題の前進に向けた運動を強め、解決を急がねばなりません。厚生労働省は、被爆者援護法に定める「被爆者」について、①原爆投下時に一定の地域にいた者、②2週間以内に入市した者、③被爆者の援護を行った者、④それらの者の胎児の次のいずれかに該当することを証明され、被爆者健康手帳を所持している者と規定しています。原爆投下からすでに75年を経過した今、新たに「被爆者手帳」を取得するのはきわめて困難な状況です。
■原爆症認定の拡大を
一方で原爆被爆者に対する原爆症認定は、国が認定に消極的に対応してきたことを反映して、裁判に訴えなければならないことが常態化しています。2008年に採択された新しい原爆症認定に関する方針では、「放射線起因性の要件該当性の判断は、科学的知見を基本としながら、総合的に実施するものである。」「特に、被爆者救済及び審査の迅速化の見地から、現在の科学的知見として放射線被曝による健康影響を肯定できる範囲に加え、放射線被曝による健康影響が必ずしも明らかでない範囲を含め、次のように『積極的に認定する範囲』を設定する」とし、爆心地から3.5km以内の被爆者の悪性腫瘍・白血病などの「積極認定」の方針が出されました。しかし、原爆症認定に消極的な国の姿勢は変わらず、その後も、多くの審査滞留や認定却下が生み出され、被団協と厚労省の間で改善を求める協議が続けられています。そして国によって認定を却下された場合でも、司法の場でその判断を取り消す判決が相次いで出されています。原爆の被害を過少に評価し、被爆者支援に消極的な政府の姿勢は、裁判のたびに断罪されてきました。
2020年1月21日に最高裁は、高裁で判断が別れた被爆者認定訴訟に対して弁論を開き、2月25日に、最高裁第三小法廷(宇賀克也裁判長)が、上告した被爆者3人をいずれも原爆症と認定せず被爆者側の請求を退ける判決を言い渡しました。最高裁は、被爆者援護法にある「原爆に起因し、現に医療を必要とする状態の被爆者に必要な医療の給付を行う」という条文をきわめて狭く解釈し、3人いずれも「今すぐに治療が必要な状態ではない」として、原爆症と認めないとしました。被爆者援護法にもとづく原爆症の認定は、原爆の放射線で病気になったこと(放射線起因性)と現在医療が必要な状態にあること(要医療性)の2条件をみたす必要があります。最高裁判決は、要医療性の判断を狭め「治療に必要な経過観察を医療行為に含まない」として、被爆者援護法に基づく原爆者認定を狭めるものです。これまでの司法判断を否定し、認定に消極的な政治の誤った姿勢に追随するもので、司法の役割を放棄する決して許されなものです。
被爆75年を迎えて、今もなお被爆者の闘いは続いています。私たちは被爆者の闘いを支援し、政府の姿勢を正していかなければなりません。
■在外被爆者への差別なき援護を
戦後、祖国へ帰還した在外被爆者への援護は、日本の戦争責任・戦後責任と重なり、戦後75年を過ぎても重要な課題です。原水禁は、「被爆者はどこにいても被爆者」であるとして、差別のない援護の実現に向けてとりくみ、在外被爆者を縛っていた厚生労働省公衆衛生局長の402号通達(被爆者手帳を交付されていても、外国に出国や居住した場合は、健康管理手当の受給権が失効する)の違法性を問い、2015年9月8日、最高裁で「在外被爆者にも医療給付がなされるべき」との判決を下し、制度上の不平等は大幅に改善しました。しかし、長い年月の経過の中で、国外移住によって被爆を証明する証人が見つけられない、国交がないことで在朝被爆者には実質的に適用されていないなど、被爆者健康手帳の交付にさえ多くの課題が残されています。
原水禁などで組織される在朝被爆者支援全国連絡会は、朝鮮に訪問団を派遣し、在朝被爆者の実態把握と今後のとりくみを協議してきました。2019年4月22日には、在朝被爆者に対して、早急に医療支援をするよう厚生労働省に求めました。日本と国交がない北朝鮮に住む被爆者には「被爆者援護法による援護も補償も何ら実現していない」と指摘して、日本政府による人道上の緊急支援などを求めました。在朝被爆者も含めて、戦争責任・戦後責任の問題とともに、高齢化する在外被爆者の課題前進に向けたとりくみも強化しなくてはなりません。
■「被爆体験者」に援護法の適用を
被爆者認定の地域である爆心地より12km圏内で被爆したにもかかわらず、長崎市域外(長崎市は東西約7km)であったことを理由に「被爆体験者」と呼ばれ、被爆者援護法の枠外に置かれている被爆者は、自ら課題の解決を司法の場に求め、裁判闘争を続けてきました。「被爆体験者」は、爆心地から半径12キロ圏内だが、国が被爆地域に指定していない地域で原爆被害に遭いました。原爆体験に起因する精神疾患で医療費の給付が受けられるが、被爆者とは援護の内容に差があります。被爆者の認定を、長崎市域・市街で区分けすることに科学的根拠はありません。
2007年と2011年に、第1次(原告388人)、第2次(原告161人)の被爆体験者訴訟が提訴され、第1次訴訟は、2017年12月最高裁で敗訴が確定しました。第2次訴訟は、2016年2月の長崎地裁判決では「自然放射線による年間積算線量の平均2.4mSvの10倍を超える25mSv」前後の被曝での「健康被害の報告、研究に照らすと、原爆の放射線により健康被害を生ずる可能性」があったとし、米軍による空間線量率測定値に基づいて推定した、放射性降下物による外部被曝線量が25mSv(原爆投下後1年間)を超えた原告10人のみについて「被爆者健康手帳」を交付すべきとしました。原告は「25mSvでの線引き」は納得できないとして控訴しました。2018年12月10日の控訴審判決では、被曝量を一審より少なく見積り、内部被曝も「かなり微量」と決めつけ、重要な争点のひとつであった低線量被曝の人体影響は、100mSv以下で「健康への影響があることについて、確立した科学的知見に関する証拠はない」と断定し、一審で手帳交付を認めた10人についても訴えを退け、原告161人全員の敗訴を言い渡しました。
上告審においても、最高裁第一小法廷は、2019年11月21日付けで、「被爆体験者」第2次訴訟で、原告側の上告を退ける決定をしました。10人に対する手帳交付を命じた一審判決を取り消し、全員の訴えを退けた二審福岡高裁判決が確定することとなりました。この決定は病気も抱えながら裁判を闘ってきた高齢の「被爆体験者」にとって、許し難いものです。
最高裁の判決は、原告側が裁判で提出した、「小児のCT検査による白血病・脳腫瘍のリスク増加に関する英国での調査」「被曝によるガン死亡の『閾値なし直線関係』(LNT)を明らかにした原爆被爆者『寿命調査』」「米英仏三か国の核施設労働者の長期低線量被曝によるにガン・白血病リスク増加の調査」などで示されている低線量被曝の健康被害を全く考慮せず、国の「LNTは単なるモデルである」とし、100mSv以下の健康影響を全面否定した反論を一方的に支持するもので許しがたい判断です。これらの疫学調査は、低線量被曝の健康影響を示す重要な科学的根拠であり、全国の原発差し止め裁判や福島事故被害者の人権と補償を求める訴訟や対政府交渉などでも提示され闘われているものです。脱原発と福島原発事故被害者の運動の強化とも結んで、引き続き「被爆体験者」訴訟を支援していくことが重要です。被爆地域の拡大と被爆者認定、被害の実態に見合った援護を勝ち取っていく必要があります。
■被爆二世・三世の人権確立を求める運動を支援しよう
被爆二世・三世は、父母や祖父母の原爆被爆による放射線の遺伝的影響を否定できないなか、「健康不安」や「健康被害」、社会的偏見や差別などの人権侵害の状態に置かれてきましたが、被爆者援護法の枠外に置かれてきました。被爆二世は「全国被爆二世団体連絡協議会(全国被爆二世協)」を組織して「被爆二世の被爆者援護法への位置づけと国家補償を求めて「被爆者援護法」の改正を求めてとりくんできました。
全国被爆二世協は、国内での課題解決の進展が全く見られない中にあって、現在、国連人権理事会への場で被爆二世の人権保障を日本政府に求める運動や広島・長崎両地裁での「原爆被爆二世の援護を求める集団訴訟」にとりくんでいます。また、2020NPT再検討会議の準備委員会に代表を派遣し、サイドイベントを開催するなど、自らも核被害者として、国際的な反核運動の中での役割を果たすための活動を開始しました。再検討会議の延期に伴い、予定していた計画も延期を余儀なくされていますが、今後も世界の核被害者、そして二世・三世と連帯したとりくみを含め、全国被爆二世協のとりくみの強化が求められます。父母や祖父母の被爆体験を家族として身近に受け継ぎ、自ら核被害者としての権利を求め、核廃絶を訴えている被爆二世協の運動は、今後の原水禁運動の継承・発展にとっても重要です。
■被曝労働者との連帯を
政府は、電離放射線障害防止規則(電離則)・省令の改定で2016年4月から労働者の緊急時被曝限度は100mSvの原則に加えて、特別緊急被ばく限度を250mSvとしました。「通常被ばく限度を超えた者の線量管理(大臣指針事項)」の中では、生涯被曝線量1000mSvが導入されてしまいました。労働者の健康を軽視し、事故収束・廃炉作業の実態に合わせる法改正は許せません。
これまで福島第一原発では、未成年者の被ばく労働、暴力団の介在、違法派遣や偽装請負、労働者に労働条件を明示しない、健康保険に加入させない、さらには、本来は会社が負担すべき健康診断費や、放射線管理手帳の作成費を作業員の給料から天引きするなど、様々な違法労働の実態が発覚してきました。また、高線量の中で長時間労働を可能にするために、警報付ポケット線量計(APD)を鉛ケースに入れる、線量計の不携帯などが報告されています。問題は、東電が実態を把握しながら公表しなかったことです。作業優先の企業姿勢を許してはなりません。
2020年2月19日、東電は協力会社社員の内部被曝を発表しました。高濃度の汚染水をためているプロセス主建屋で全面マスクなどを着用しての作業中、鼻腔内などに汚染が確認されました。東電は、点検のため全面マスクを着用する一部作業を中止しました。2月7日にも同様の内部被曝が確認されています。その後、4月13日にも同様の内部被曝の事例があったことを東電は発表しています。3件とも全面マスクが必要な高汚染の労働環境での作業に従事していた労働者の被ばくです。(初めの2件はマスクを外した際に吸い込んだものとされている。)3件目は変形したマスクの排気弁から吸い込んだことが確認されており、東電の不作為による事故といっても過言ではありません。どの事故も同様に被ばく量は微量で健康に問題は無いと発表していますが、繰り返される事故の情報は、きびしい条件下で労働者の健康が確保されていないことが懸念されるものと言わざるを得ません。
原発労働は、従来から高次の下請け企業による雇用が中心で、雇用や労働環境の問題はなおざりにされてきました。被曝問題だけでなく、危険手当てのピン撥ね、パワハラ、等々、労働者の基本的な権利が侵害される事例が日常的に起きています。積層的な下請け構造を口実にした責任逃れを許してはなりません。廃炉・事故処理作業に携わる被ばく労働者も、福島事故の被害者です。事故を起こした東電と国の責任を問い、被ばく労働者の安全と権利の確保に向けて、東電の企業責任と、東電を監督・指導すべき国の責任を厳しく追及なければなりません。
2018年5月1日には、「技能実習制度」で来日したベトナム人実習生など6人が、放射線教育も行われないまま、福島第一原発でがれきなどを焼却する施設の建設工事に従事していたことが、明らかとなっています。雇用契約書には「除染作業」は記載されておらず、実習生によれば作業内容や放射能の危険性についての説明もなかったといいます。そもそも原発のない国の人々に原発労働の実習を組み込むことは制度の目的から逸脱しています。東京電力は、2019年4月から始まった新たな在留資格「特定技能」の外国人労働者を、福島第一原発の廃炉作業などで受け入れる方針を表明しましたが、日本語に不慣れな外国人労働者を放射性物質が残る現場で働かせることは労災事故につながりかねないとする厚生労働省の指導により5月22日、「当面の間、発電所での特定技能外国人労働者の就労は行わないこととする」と発表しました。
原発労働者をはじめ全ての被ばく労働者に健康管理手帳を交付し、個人被ばく線量を記録し、定期的に健康診断を実施し、退職後も含めて継続して労働者の健康を管理し、被ばく作業に起因する疾病の医療を保障することが大切です。法の遵守を含め、被ばく労働者の権利を守るとりくみが必要となっています。
■被爆の実相を次の世代につなげ
核兵器禁止条約は、核兵器の非人道性をきびしく断罪していますが、被曝75周年を迎えて原爆被害の実相が風化しつつあることも事実です。ヒ口シマ・ナガサキの被爆者は高齢化し、その子ども世代も高齢者に近づきつつあります。本当に限られた時間の中で、核兵器廃絶とヒバクシャ課題の解決とともに、被爆の実相をどの様に語り伝えていくか、次世代につなげて行けるのかが、平和運動の重要な課題となっています。
長崎から始まり全国に拡がってきた「高校生平和大使」の活動は、20年を超え、外務省からも「ユース非核特使」に認定されるようになりました。これまで集めた100万筆を超える署名はジュネーブの国連欧州本部に永久保存されるなど国連からも高く評価されています。高校生平和大使派遣委員会が全国各地で組織され、支援する会も積極的に動いています。これまで高校生平和大使の運動に参加したOG・OBで組織する高校生平和大使の会も発足し、平和大使の運動が2018年から毎年「ノーベル賞」にノミネートされています。若い世代の主体的で積極的な核兵器禁止・平和をめざすとりくみを、被爆体験・被爆の実相の継承などとつなげて、より広範な運動にしていかなくてはなりません。
一世被爆者と体験を共有してきた被爆二世・三世の役割、教育の中で位置づいてきた平和教育、地域や職場での原水禁運動、様々なとりくみを繋げより強力な運動の展開が求められます。平和憲法が危機にある今日、被爆体験の継承は、平和の尊さを実感する大きな力となるに違いありません。このような課題も認識し、原水禁運動の拡大が求められます。
■世界の核被害者との連帯を
核のレイシズムともいわれる差別と人権抑圧の下で、先住民などの社会・政治的弱者に核被害が押しつけられてきました。原子力利用は、ウラン採掘の最初から高レベル放射性廃棄物処分の最後まで、放射能汚染と被ばくをもたらします。原水禁は、マーシャル諸島などの核実験の被害者、米国やオーストラリアの先住民などウラン採掘現場での被害者、チェルノブイリ原発事故での被害者など、これまで世界中の多くの核被害者と連帯を深め、とりくみを共有してきました。
核社会のもたらす甚大な被害の実態は、原水禁運動が訴えてきた「核と人類は共存できない」ことを強く再認識させるものです。これ以上の核被害の拡大を、けっして許してはなりません。差別と抑圧の厳しい現実の中で闘っている世界中のヒバクシャ=核被害者と連帯し、ヒバクシャの人権と補償の確立のために、これ以上の核被害の拡大を許さず、そして核時代を終わらせることをめざして、運動を強めなくてはなりません。
(4)おわりに
■いのちの尊厳を基本に、ポストコロナ社会へむけて
2019年12月8日、中国当局が認定する最初の新型コロナウイルス感染症の患者が確認されました。2020年1月16日には、日本で初の感染者が確認されます。その後、世界の感染者は拡大を続け、7月5日現在、1126万7309人、死者数は53万754人になりました。現在も毎日17万人以上の新規感染者が出ています。全世界は今、新型コロナウイルス感染症に席巻されています。
国連グテーレス事務総長の呼びかけ、安保理決議等に答え世界の国々が協力して新型コロナ感染症の拡大を抑え込まなければなりません。核軍拡競争をやめ、軍事費を削減し、資金を感染症克服に注ぎ込まなければなりません。医療や生活支援体制の脆弱な途上国に資金や人材の支援を行わなければなりません。それは、人道上重要であるだけでなく、先進国や世界中の感染拡大を止める手段でもあります。今や、世界は一つです。自国だけが危険な感染症から逃れることはできないのです。
ポストコロナ社会を差別と排除の社会にしてはなりません。そして、自国第一の国家主義的対立の世界にしてはなりません。命の尊厳を守り、それを保証する、核のない、持続可能な平和な世界の実現を基本とした社会のあり方を、対話と協調を基本に、国と国、民族と民族の対立を超えて、私たちは考えなくてはなりません。核兵器を非人道的兵器とする「核兵器禁止条約」を発効させ、NPTにおいて核保有国が約束している核軍縮を実行と、中東の非核地帯化、東北アジア非核地帯化へと前進させ、核兵器廃絶へ、平和の確立へ、確実な一歩を踏み出さなくてはなりません。「核先制不使用宣言」「即時警戒体勢の解除」「核兵器の更新の禁止」そして日本においては「プルトニウム利用からの脱却」「非核三原則の法制化」「脱原発」など、核廃絶、平和への様々なとりくみを行わなければなりません。
2019年11月24日、ローマ教皇フランシスコは、1981年のヨハネ・パウロ二世以来38年ぶり2度目となる日本訪問を果たしました。高校生平和大使は、2019年6月にバチカンを訪問し、サンピエトロ広場で教皇に「広島・長崎へ訪れて欲しい」と要望していました。高校生平和大使は、教皇の広島・長崎訪問に大きな役割を果たしました。教皇は来日のテーマを「すべてのいのちを守るため~PROTECT ALL LIFE」としました。そして、被爆地広島の平和記念公園で「平和メッセージ」を発しました。「確信を持って改めて申し上げます。戦争のために原子力を使用することは、現代において犯罪以外の何ものでもありません」と述べ「武器を手にしたまま、愛することはできません」と武力の放棄を主張し、「核戦争の脅威で威嚇することに頼りながら、どうして平和を提案できるでしょうか」と問いかけました。唯一の戦争被爆国として核兵器廃絶を主張しながら、米国の核抑止力を安全保障政策の基本に据える日本政府は、この教皇フランシスコの言葉をどのように聞いたのでしょうか。
「核と人類は共存できない」原水禁運動は、ヒバク体験を原点に、ヒバクシャの救援、即ちヒバクシャの権利としての生命と生活をかちとる運動、さらにヒバクシャを再び出させない運動として発展してきました。常にひとり一人のいのちの尊厳を基本に据えて、運動を展開してきました。そのことは、言葉の真実を生み出し、決してゆらぐことのない運動を展開してきました。暴走する安倍政権は、多くの反対の声を無視し、特定秘密保護法・戦争法(安全保障関連法)・共謀罪法を成立させてきました。沖縄県民の声を無視して辺野古新基地建設を強行しています。働き方改革・IR法の制定、入管法改正、そして原因究明もおざなりに相次ぐ原発再稼動と、人間のいのちをないがしろにする政策をすすめてきました。安倍政権が当初から主張していた「戦後レジームからの脱却」は、日本国憲法が規定する平和と民主主義、基本的人権を否定するものなのです。日本国憲法の理念の下、これまでの原水禁運動の正しさに胸を張り、これまでの成果を引き継ぎ、私たちの道をゆるぎない信念を持って進もうではありませんか。
イージス・アショアを中止に追い込んだ運動の力をさらに拡げ、結集し、辺野古新基地建設をやめさせましょう。
原水禁運動は、安倍政権の安全保障政策と原発推進政策に、ひとり一人のいのちをないがしろにする全ての政策に反対して、いのちの尊厳を守り、それを保証する核のない平和な世界の実現を基本に、闘いをすすめていきます。
ノーモア・ヒロシマ、ノーモア・ナガサキ、ノーモア・フクシマ、ノーモア・ウォー、ノーモア・ヒバクシャ
被爆75周年原水爆禁止世界大会 基調(PDF)